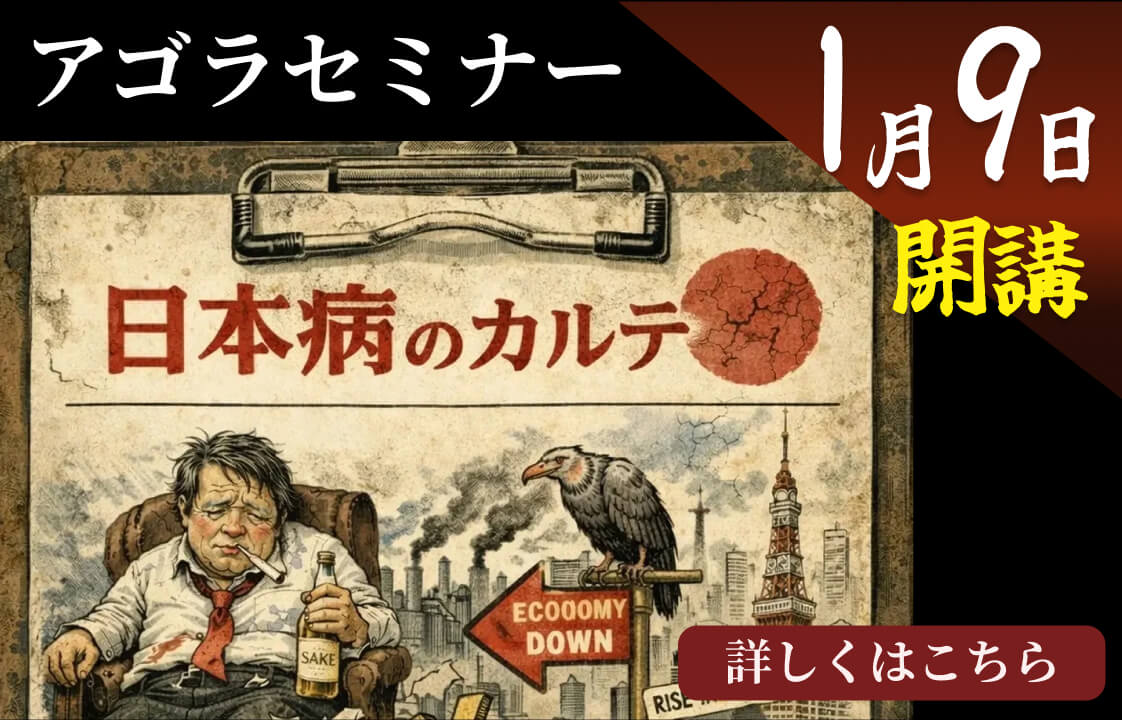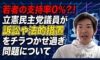元厚労省の官僚だった村木厚子氏が日経ビジネスの寄稿に「バイト年収の壁見直し、学生の可能性を潰してほしくない」と投稿しています。生活の苦しい学生のための103万円の壁の引き上げ賛成という趣旨です。たしか、同様の意見は左派を中心に広くあると認識しています。

村木厚子氏 日本記者クラブ講演動画より
年収の壁は実態としては学生に限らず、誰にでも等しく引き上げになるわけですのでその点については全く問題ありません。ずいぶん前に書いたように基本的に90年代からこの金額が見直されなかったのは財務省の怠慢というか、税収減になることを恐れ、知らんぷりしてきただけの話です。今回、最終的に何処まで引き上げられるかわかりませんが、最低賃金の上昇率から計算した178万円は一定の妥当性があり、そこにすり寄らせ、かつ、法律上、最低賃金の上昇率に沿う形で毎年、この控除額を見直す、と法律に明記すべきでしょう。
一方、村木氏の主張する学生のバイトを促進するための引上げという声には私は一定の抵抗があります。ご本人も寄稿の中で「子供の本業は勉強」という意見があると述べています。この本業である勉強という部分が昔から大学生の意識から抜け落ちている、これが日本の大学生の実態だと思います。
かつては終身雇用が主流だった時代はon the job trainingと称し、入社してから会社によってはひと月近くオリエンテーションをしてようやく配属先に赴任していました。もちろん今でも長期間にわたる新入社員研修はあり、1年もやるところすらあります。かつては長期雇用関係がある程度見込める雇用関係でしたので企業は社員を企業色に染めるための投資欲が当たり前でした。今でもそれを強く続けているところは「社員の退職率が減っている」といった声もありますが、技術系に限定されるなど必ずしも汎用的ではない気がします。
ちなみに私が入社したゼネコンは3か月の英語クラスと概ね2週間程度のオリエンテーションで、配属先に行くのは夏前でした。今でも覚えていますが、6月のボーナスをもらったのは英語クラスで塩漬けになっていた時。ボーナスではなく「寸志」だったと記憶していますが、5万円頂きました。170名強の新入社員全員が給与もらって3か月英語学校に行かせる懐の大きさに「すげぇー会社だよな」と皆で言い合ったものです。しかし、数年もすれば3割近くが退職したのも事実で会社による新入社員教育とは何ぞや、というのは当然議論されたわけです。ちなみに私がトップの秘書になった時はその制度は大きくカタチを変え、短い期間で終わるようになっていました。
終身雇用という発想がなくなってきた現在、企業は従業員により実務的なハイレベルの教育にシフトしていき、中途採用が増える中で入社〇年目の研修という形に変わっていっていると認識しています。とすれば、大学生が企業に入社する時にはある程度基礎力と社会人としての常識をもった人材に仕上がっている必要があるはずです。
ところが学生によってはバイトに明け暮れる人もいます。私もバイトは良くした方です。私は海外に行くための渡航費用稼ぎという明白な目的がありましたが、生活費と共に遊び代稼ぎやショッピング代稼ぎというのが学生バイトのほぼ主流だったと思います。
その後、何の疑いもないままカナダに来た時に「あれー?」というギャップを感じたのです。学生バイトをする人は極めて少ないのであります。理由はそんな時間はない、勉学が大変で図書館に籠るという訳です。こちらに留学している日本人学生さんともよく話をしますが、「ついていくのが大変」という話はごく当たり前でそれが言語的なギャップというより濃密な授業内容と予習復習、頻繁にあるテストに追われているという感じです。
カナダでは外国人学生が学校に行きながらアルバイトをする際、査証により一定の労働が許されます。生活費の一部という発想だと思います。その枠組みは週に20時間までです。それ以上働くのは学生が学生の本分である勉強とはかけ離れると解釈されています。
ではこの20時間を日本に当てはめたらどうなるか試算をすると時給1,100円で月80時間働くと年間で1,056,000円です。つまり103万円の壁にほぼドンピシャで合致するのです。ちなみに日本に来る学生は原則就労できません。ただし、「資格外活動の許可」をもらっている場合に限り週28時間まで可能になっています。これだと年間150万円です。
たしかこの話題が出た時、一部から「学生は学ぶことだろう。本末転倒ではないか」という意見が出たのを記憶しています。本質的にはその方の主張は正しいと私は思います。
ところで、何かを読んでいた時、ある学生が「大学に将来の実業に役立つ授業がなく失望した」という意見があったのを見て私は驚きました。この方は大いなる勘違いをされているのです。実業の学校なら職業訓練学校的な専門学校や高専に行くべきであって大学はアカデミアの世界だという意識を十分理解していないのです。
学生バイトの話もそう。もしも稼ぎたいのなら4年生の大学に行かず、高専や専門学校に行き、早く就職するべきです。経済的ゆとりがない人が大学に行く場合でも、今は星の数ほどの奨学金制度があり、その利用者は相当数に上ります。また社会人になった後の返済も無利子で収入見合いという返済プランならそれこそ月々数千円の返済というレベルなのです。
学生とはやはりしっかり勉学する、それが基本であり、103万円の壁が大きく上振れすることでバイトに執着する学生が増え、大学時代はバイト三昧だったという方が増えるのが教育の一面からは懸念されると思います。
教育の話は十人十色の価値観がありますので正解はないと思っています。ですが、議論をして様々な意見を交わすことは重要なプロセスであると考えています。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年2月12日の記事より転載させていただきました。