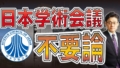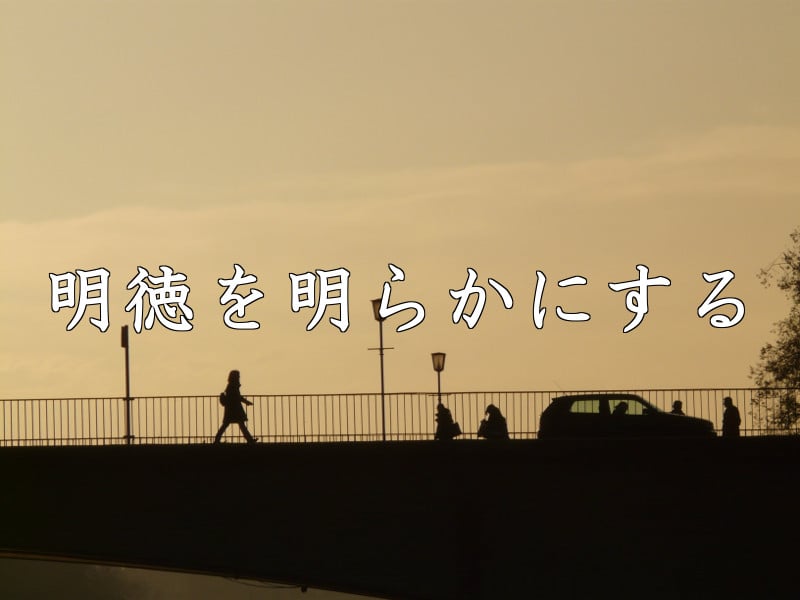
拙著『逆境を生き抜く名経営者、先哲の箴言』(09年12月)の「第3章 資本主義の危機に、一個人としてどう備えるか」の中で、私は「山中の賊(ぞく)を破るは易(やす)く、心中の賊を破るは難(かた)し」という言葉を御紹介しました。中国明代の思想家、陽明学の始祖である王陽明(1472年-1529年)の言で、物事の崩壊は内から起こることを意味しています。国語辞書には、「山中に立てこもっている賊を討伐するのはやさしいが、心の中の邪念に打ち勝つことはむずかしい。自分の心を律することは困難であるというたとえ」と書かれています。
心中の賊とは具体的には、我欲がため信念を貫くことを止めたり、心の声と実際の言動が大きく乖離したり、といった類であります。私利私欲に汚(けが)されて自分の純を出せないような形になるのは、結局自分自身の弱さからきているわけです。自分自身を知ることを、儒教の世界では「自得…じとく:本当の自分、絶対的な自己を掴む」と言い、仏教の世界では「見性…けんしょう:心の奥深くに潜む自身の本来の姿を見極める」と言いますが、ターゲットを定めるに自得・見性が出来なければなりません。
お互い人間というものは、自分の姿が一ばん見えないものであります。したがって私達の学問修養の眼目も、畢竟するに、この知りにくい自己を知り、真の自己を実現することだと言ってもよいでしょう――明治・大正・昭和と生き抜いた知の巨人・森信三(1896年-1992年)先生は、『修身教授録』の中でこう述べておられます。之は、自得・見性に相当するものでしょう。森先生のみならず、ソクラテス(前470年-前399年)も『アポロン神殿の柱に刻まれていた「汝自身を知れ」の言葉を自身の哲学活動の根底におき、探求した』とされていますし、ゲーテ(1749年-1832年)も「人生は自分探しの旅だ」と言っています。自己を得ること程難しいことはなく、又それが如何に重要であるかは、古今東西を問わず先哲が諭している所です。
『老子』第三十三章にも「知人者智、自知者明…人を知る者は智なり、自らを知る者は明なり:人を知るのは智者に過ぎないが、自分を知るのは最上の明とすべきことだ」とあります。世のあらゆる事は人間が生み出し人間が行っているわけですから、自分自身を含め人間というものを知らずして大した事は成し得ません。自得・見性こそが正に、本当の明徳であり明であり全ての出発点なのです。『マタイによる福音書』の中に、心の清き者につき「その人は神を見る」というように書いてあります。「心を清くすると神に通ずる」ということで、心を清めることはあらゆる宗教で一番大事だとされています。我々は、明徳が私利私欲の強さに応じ次第に曇らされ、結局は明が無くなって行くといったことにならぬよう、唯々修養しようという気持ちをずっと持ち続け、自らの良心に根差し自問自答する中で、心中の賊を破るべく尽力して行くしかないのだろうと思います。
編集部より:この記事は、「北尾吉孝日記」2025年2月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。