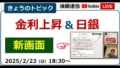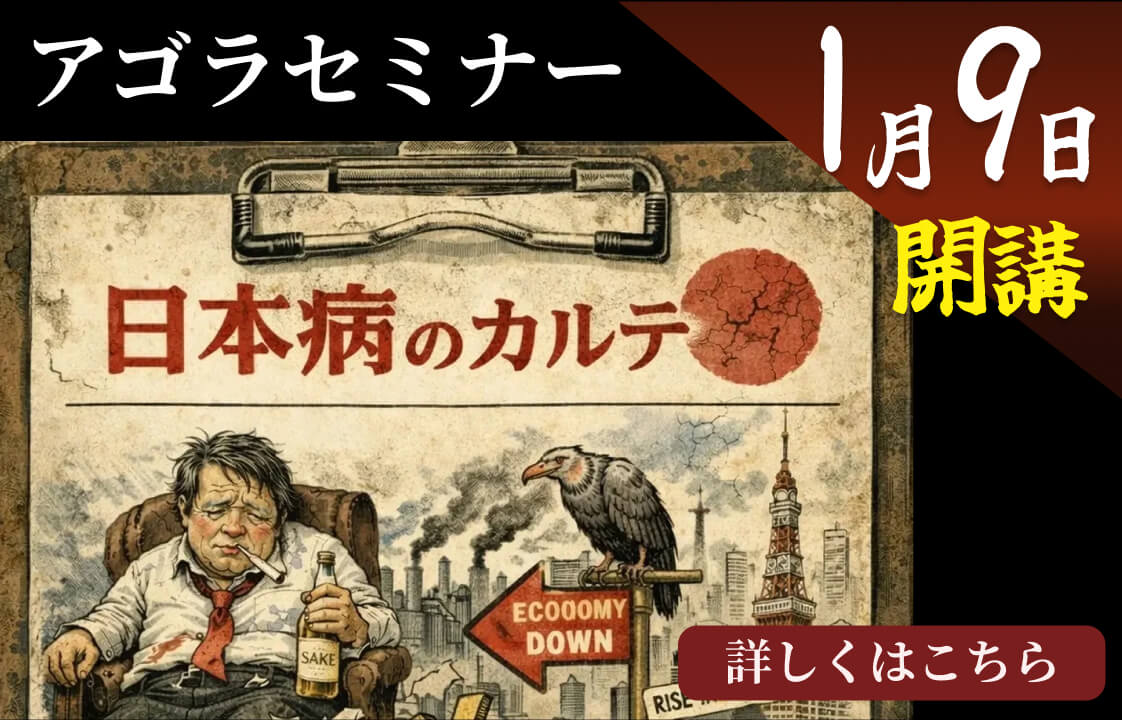住宅価格の上昇の影響で、従来の35年という返済期間から、40年や50年などのより長い返済期間を選ぶ動きが活発になっています。
住宅ローン 返済期間40年や50年に長期化の動き活発にhttps://t.co/C1sEAa4tpU #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) February 24, 2025
全国約300の金融機関を対象に行った調査でも、35年を超える住宅ローンの提供が75.8%と最も多かったそうです。

maroke/iStock
現在、金利が上昇し始めています。その影響で、特に、ペアローンでぎりぎりの返済計画を組んでいる場合は注意が必要です。
みずほリサーチ&テクノロジーズ作成の2026年住宅ローン金利はどうなるか?の予測に震えた。
そら、政策金利が2025年末までに1%になる世界ならそうなるよな。わかってる、わかってるとはいえ… pic.twitter.com/l71tvDKbxb— のらえもん (@Tokyo_of_Tokyo) February 21, 2025
金利上昇が始まっています。
住宅ローン破産が激増し、不動産市場が暴落する可能性が高いです。
大不況が到来しますが、ペアローンでギリギリで組んでいる方々は、非常にマズいです。— X (@X124839934465) February 20, 2025
住宅ローンでマイホームを購入すると、不動産を担保にして借り入れをしているため、地価が上がると利益が大きくなりますが、下がると損失が大きくなるリスクがあります。
10/21日経(夕)「住宅ローン膨張すり減る家計」総務省「家計調査」によると、平均の負債額、貯蓄に対する負債の割合が過去最高になった。30代など若い世代の負債が大きい。マイホームは不動産を担保にした信用取引なので、地価が上がれば利益にレバレッジがかかりますが、下落すると…。
— 橘 玲 (@ak_tch) October 23, 2024
今後、多くの都市で人口が減少し空き家が急増すると予測されます。
現状ではアドバイスはいろいろありますが、素人に実行するには難しい判断が求められます。
住宅ローンは完済しなくてOK!
15~20年以内に土地価格まで残債を減らせばいいだけ。これで実質ローン完済!気が楽でしょ?いつでも土地は売れるし建物価値も残ってるからプラス。
その為に
・土地はいっとけ!けちるな!不人気土地は二束三文!
・建物にお金をかけるな!でも質を担保しろ!
だよ。— せやま|ちょうどいい塩梅の家づくり (@seyaman39) February 19, 2025
それでも歴史は繰り返すのでしょうか。
私の世代は、90年代のバブル崩壊後に住宅ローン破産が続出するのを目の当たりにしましたが、そういう経験をしたひとも少なくなったんでしょうね。ちなみにこのとき自己破産が簡単になったのは、あまりに多くの破産者が出て、社会の安定が脅かされたからです。
— 橘 玲 (@ak_tch) October 23, 2024
人の不幸はなんとやらですが、そのとき日本経済はどのようなことになるのでしょうか。
私は不動産持ってないので、日銀が金利を5%くらいまで追加利上げしてくれて、住宅ローン限界まで借りてギリギリ返済してるタワマンカップルが破産して、さらに石破か百合子が外国人の不動産購入に高額な税を課すようにしてくれて、ワイが安く不動産買える日がくることを常日頃から願っております
— ゆな先生 (@JapanTank) January 22, 2025
日本人は甘え過ぎです。たかが1%程度の金利上昇に耐えられない人間は、そもそも借りるべきではないのです。住宅ローンを変動金利で組んだのも自業自得だし、企業も1%の金利上昇で返済困難になるなら延命する価値などない。借りたら利息を付けて返す。返せないなら借りない。これは世界共通の常識です。
— ちゃん社長 (@Malaysiachansan) January 25, 2025
今後も返済期間の長期化の傾向が一層進むとみられます。
低い金利を提示して変動金利住宅ローン借り手を可能な限り集めてから引き上げ始めるネット銀行。pic.twitter.com/X95EADVRMa
— Shen (@shenmacro) July 31, 2024
住宅価格の上昇に伴い毎月の返済額を抑えたいニーズや、企業の定年延長により働く期間が長くなったことが、返済期間の長期化の背景にあると考えられますが、今後は金利が上昇する可能性も懸念され、借り手は長期返済が返済負担に与える影響についても考える必要があります。