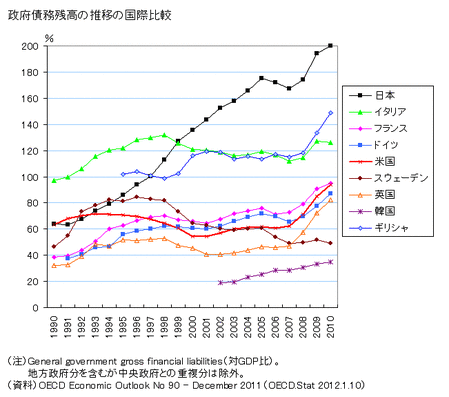霞ヶ関で、一つの抗議文が話題を呼んでいる。財務省の広報室長が朝日新聞の4月5日の記事の事実誤認を指摘し、その訂正を求めたものだ。特に私が驚いたのは、次の部分だ:
「東大在学中から勝の友人である前国交事務次官の竹歳誠が就任。」との記載がありますが、勝財務事務次官と竹歳官房副長官は、卒業年次も3年異なり、学生時代全く面識がありません。
竹歳氏は1972年東大法学部卒、勝氏は1975年卒だから、朝日の記事は明白な間違いだ。しかし昨年9月に竹歳氏が官房副長官に就任したとき、オール霞ヶ関の統括に国交省出身者が就任する異例の人事を「竹歳氏は勝氏の同級生で財務省のロボットだ」とする解説が広がり、霞ヶ関の常識になっていた。もちろん同級生でなくても仲よしということはあるだろうが、「財務省のロボット」という話はあやしい。
巷に流布している「財務省が日本を支配している」という話のほとんどは、この種の都市伝説である。そもそも財務省がそんなに強かったら、1000兆円も政府債務が積み上がるはずがない。実態は逆で、財務省は90年代以降、政治に屈服して敗退を重ねてきたのだ。次の図を見ればわかるように、1990年には先進国の平均程度だった政府債務のGDP比が、この20年で断然トップになっている。

こういうことになった原因としては、1993年の政権交代で大蔵省の斎藤事務次官が小沢一郎氏と結託したのに対して、政権を取り戻した自民党が報復したという事情もあるが、根本的な問題は「政治主導」がいわれるようになって意思決定システムが複雑化し、ステイクホルダーが増えたことだ。
昔の自民党は政策決定を霞ヶ関に丸投げし、その利権分配だけに関与していたが、90年代以降、族議員が専門化して政策決定に介入するようになり、「景気対策」の補正予算が増額された。これに対して「政権交代したら16兆円の歳出が削減できる」という公約を掲げたのが民主党だったが、実際に政権をとってみると、歳出削減どころか、昨年度は(補正を含めると)107兆円にのぼる史上最大の放漫財政になった。
一見すると無駄な歳出はたくさんあるように見えるが、事業仕分けでもわかったように、切れるのはごく一部である。それは各省庁が拒否権をもっているからだ。官庁の「製品」である法律はスパゲティ状に相互依存しているため、関連法案の所管官庁が一つでも反対すると改正できない。これは財務省も同じだから、乱暴な歳出削減をやると、協力が必要なときに拒否権を行使されてしまうのだ。
このように全員が拒否権をもつ構造は、契約理論でいう共同所有権である。普通の契約ではパートナーが1人でも反対すると決まらない共同所有権は最悪の所有形態だが、長期的関係を維持する上では最適になる場合がある。共同所有権では、1人が拒否権を行使すると組織が動かなくなるため、場の「空気」を読んで同調するプレッシャーが強まるのだ(厳密な証明は拙著を参照)。
つまり日本の法律のスパゲティ状のコードは、全省庁に拒否権を与えることによって長期的関係を維持するメンバーシップの担保になっているのだ。この起源は、日本の伝統的な村落にあるものと思われる。傾斜が急で狭い日本の農地では、中国のような大規模な灌漑設備がいらない代わりに、流出する水をせきとめて狭い水田を共同で管理する緊密な共同作業が必要になる。このためローカルな「場」に依存した共同体ができた、というのが経済史の通説である。
共同所有権では全員一致が原則だから、特定のメンバーが反対を押し切って決めることは、メンバーが増えれば増えるほど困難になる。かつては官庁間の交渉だけだったから、予算編成権をもつ大蔵省に「残余決定権」があったが、政治家が強く関与してくると、形式上は政治家が決定権者だから財務省は譲歩せざるをえず、全員が平等に拒否権をもつ構造がますます強まる。
この膠着状態を打開するため、官房副長官と各省の局長レベルの交渉が重要になる。公式の各省折衝の前に彼らが水面下で根回しして決め、ここで決まらないものは政治家がいくら騒いでも決まらない。日本の法律のほとんどは官僚が書いており、彼らの協力なしに立法はできないからだ。
このように全員が拒否権をもち、全体を統括する決定権者がいない構造は、戦争の少ないことによる平和ボケとあいまって、日本の官民共通の組織構造になっている。国会では「ねじれ」がよく話題になるが、霞ヶ関にも企業にも、ねじれは遍在しているのだ。公選法や憲法を改正しても、この構造を改めない限り「決められない政治」は変わらないだろう。