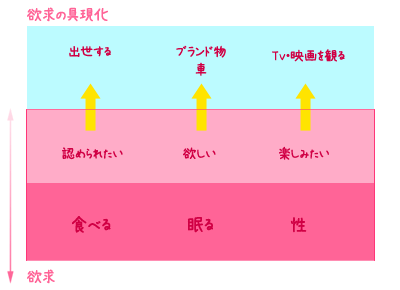「電子出版」の可能性が論じられるようになってから随分多くの年月が経った。最近は何処ででも手軽に読めるタブレット端末の類も数多く出てきたので、普及の機がようやく熟してきたとも言える。しかし、アメリカではアマゾンのプレゼンスが着実に拡大しているのに対し、日本では、コミック以外には、実際の「電子出版」は未だに微々たるものだ。
いつの時代でも、どんな分野ででも言える事だが、パラダイムシフトをもたらすような新しい技術やビジネスモデルが出てくると、殆どの既存事業者は先行きに不安を持ち、先ずは本能的に「抵抗勢力」と化すのが常だ。勿論、この様な抵抗が殆ど意味を成さない事は歴史が証明しているが、物事は或る程度は惰性で動くので、新しいビジネスモデルが定着するのに要する時間は、その為にその分だけ長くなる。
「電子出版」の普及を恐れなければならない人達は勿論大勢いる。書店、卸売(取次)業者、物流会社、倉庫業者、印刷業者、製紙会社、等々だ。現在、印刷された書籍に読者が支払っている金額の大体七割位はこれ等の人達の手に入っていると思われるが、「電子出版」になればこれが丸々なくなる事になるからだ。
しかし、こうなれば、仮に著作者の収入(印税など)が二倍になったとしても、なお、読者のコストは半分近くになるわけだから、より多くのものが書かれ、より多くのものが読まれる事に繋がるわけであり、著作者は勿論、出版社にとっても本来は望ましい事である筈だ。
こう考えると、現状では大手の出版社が電子出版の「抵抗勢力」になっている観があるのは、ちょっと不思議な現象だ。勿論、彼等はそうではないと主張するだろうが、何れにせよ、何等かの仕掛けを作って「囲い込み」を計り、これまでの収入を出来る限り守ろうとすることは目に見えている。
出版社の仕事とは、基本的には「著作者と潜在読者を繋ぐ」事だ。そう考えると、「編集」「装丁」といった仕事以上に、彼等にとって本来一番重要なのは、「著作者と読者の発掘」、即ちマーケティングなのではないだろうか。
この重要性は、紙に印刷された出版物であろうと電子書籍であろうと同じ事だから、本来なら、各出版社は「電子出版による市場拡大の可能性」に目を輝かせ、「新しいマーケティングで他社と差をつけよう」と、日夜智恵を絞っていてもよさそうなのだが、実際にはそのようになっているとはとても思えない。
出版社というものは、元々は何等かの使命感に突き上げられて生まれてきた筈だ。「こういう事を世の中の人に広く知らしめたい」という使命感だろう。その内容は、多くの人達が必要とする「知識」や「情報」だったり、編集者が認めた「作家」と呼ばれる人達の「思想」や「情感」だったりした筈だ。
しかし、今はどうだろうか? 幅広い分野に広がった、あまりに多くの「知識」や「情報」があり、多くの「作家志望者」がひしめいている。そして、その一方で、読者にとっては、自分の限られた時間をどのように使うかの判断が、極めて重要で且つ難しいものになってきている。
現実に毎日出版されている書籍類だけでも、その数は膨大なものであり、よほど大きな書店でなければその全てを書棚に並べるのは難しい。そして、多くの書籍は一週間もたてば返品され、遠からずシュレッダーにかけられる運命にある。多くの企画は最終的には赤字となり、この失敗を繰り返した編集者は、以後は万事に慎重にならざるを得なくなる。
編集者には、当然、「或る程度は売れるだろうと思われるもの」や「もしかすると大化けするかもしれないもの」を嗅ぎ分ける才覚が求められている。名の売れた作家の書いたものは当たり外れも少ないから、編集者は当然こういう作家との関係作りに注力する。また、その時点で「話題」になっている事を題材にしている本なら、「或る程度は売れる」という見極めがつくから、そういう本を書いてくれそうな著作者を探す。
それ以外で「或る程度は売れそうな本」という事になると、第一には、種々の分野での「ノウハウもの」、次に、対象は絞られてもよいから、一部の人達から「仕事上必ず読む必要がある」と見做されそうなもの、次に「健康関係」、そして、「オタク的な興味」を対象とするもの等々だろう。老若男女を問わず、これからの「生き方」に思い悩んでいる人達は常にいるので、「読者に希望や勇気を与えるような形で『生き方』について語る」類の本も、この範疇に入るだろう。成功者についての伝記的なものや、言行録の様なものもこれと同類だ。
小説の類について言うなら、「ミステリー」を筆頭に、「歴史小説」、「ビジネス小説」、「官能小説」、「伝奇小説」、等々なら、「或る程度は売れる」本の見通しがつけ易いだろう。しかし、「純文学」や「哲学的な随想」の類となると、作家の名が相当に売れているのでない限りは、先ずは絶望的だ。潜在的な読者がいたとしても少数だし、そういう人達に「彼等が潜在的に求めている著作者や著作物の存在」を認知してもらう方法もない。そもそも「マーケティング」自体が成り立たないのだ。
私が考えるには、「電子出版」の普及を最も必要としているのは、「出版社が興味を持ってくれない種類の本を書きたいと思っている人達」と、「自分が本当に読みたいと思っている種類の本に出合えていない人達」だろう。彼等は、現在の書籍の流通の仕組みの中では切り捨てられている人達だ。IT業界の用語では、こういう人達は「ロングテール(恐竜の尻尾)」と呼ばれている。
時間がゆっくりと流れていた時代には、多くの人達が、自分の周りで起こっている事に新鮮な感興を覚え、その意味を深く考え、それについて他の人達の共感を得たいと思う事が多かったのだと思う。それが「文学(文藝)」の起源ではなかろうか? 当時は書き手が少なかった事もあり、或る程度のレベルに達した作品なら、何らかの形で「読んで貰いたい人に読んで貰う」事は出来たと思われる。商業ベースに乗せる事は難しかっただろうが、他の仕事で糊口をしのぎながら、同人雑誌などを通じて作品を世に問う道はあったと思われる。
しかし、今は「マス・マーケット」の時代だ。大量の消費者を対象に、日夜大量の商品が供給されている。著作物もこういう商品の一つだ。何かの拍子で評判になれば、それを求めて驚く程大きな金銭が動くが、こういった幸運を射止めるのは、遠くの針の穴に糸を通す程に難しい。かくして、一握りの成功者の陰で、才能のある多くの人達が、失意のうちに毎日を送る事になる。
しかし、IT技術は、この状況を根本的に変える潜在力を持っている。印刷による出版と異なり、「電子出版」の場合は、「部数による損益分岐点」もなければ「在庫リスク」もないから、どんな作品でも、一定のレベルに達してさえいれば、出版社としては「門前払い」をせねばならない理由があまりない。
勿論、玉石混交の中から、「玉かもしれないもの」と「明らかに石であるもの」を分ける作業は必要だ。そうでなければ、大量の選択肢を突きつけられた「潜在読者」は途方に暮れてしまうからだ。しかし、出版社の編集部が、それぞれの作品について一応の「粗読み」をして「ふるい」にかけ、こうして選ばれた作品を「ジャンル分け」をした上で、ある程度の「背景説明」をつけてサイトに掲載し、その一方で、「アクセス数の公開」や「読者からの批評の投稿」を可能とするシステムを整備すれば、この問題は或る程度解決出来るだろう。
電子出版によって何とかして潜在読者に認知してもらおうと思っている無名の著作者は、先ずは欲を張らず、一作品に対して百円から二百円前後の値付けをし、しかもその七割程度を出版社に渡す事を許諾すべきだ。(つまり、或る程度の知名度を得るまでは、「書いたもので生活費を稼ぎだそう」等という野望は持たないことだ。)
一方、出版社は、如何なる作品についても、一つの作品の少なくとも20-30%が読まれない限りは「無料」とし、一定のパーセント以上が読み進まれた場合のみに、「課金の許諾」を恐る恐る読者に求めるようにするべきだ。こうすれば、読者は「当り外れ」を気にすることなく、色々な著作者や作品を試みる事が出来るし、退屈なら途中で読むのをやめればそれで済む。
逆に言うなら、これまで通りの印刷物で十分採算が取れると出版社が判断した作品については、無理に「電子出版」の対象にする必要はないという事だ。著作者が印刷物と並行して「電子出版」もしたいと考えた場合には、「立ち読み」のレベル以上は有料とし、価格も高い目に設定すればよい。
この記事の表題に、私は「文藝復興」という大袈裟な言葉を使ったが、それは、商業採算が全てを決めてしまう現状が、「多くの潜在的な才能」と「作家と読者の真に望ましい出会い」の芽を摘んでしまっていると考えているからだ。「電子出版」はこの状況を打破し、ジャンル別に「大規模で全国的な同人雑誌」を作り出す事になる。これを「文藝復興」と呼ばずに何と呼ぼう。
「純文学」や「哲学的な随想」の分野は、何れにせよ小さな市場であり、所詮は「ロングテール」でしかない。しかし、これが「人類の文化を形成する重要な一要素」である事には間違いはない。人類はここ数年にわたって折角IT技術を目覚しく発達させてきたのだから、その恩恵は当然この様な分野でも享受されて然るべきだ。
<追記>
この文章は本年3月29日付の電子雑誌「月刊アレ!」に掲載されたものですが、編集者の了解を頂いて、今回アゴラに転載させて頂いています。
なお、私事で恐縮ですが、私自身も、実は「電子出版がなければ潜在読者に出会えない」と考えている「無名の純文学作家」の一人です。ずっと以前には、「久慈毅」のペンネームで、読み物仕立てのビジネス書を3冊ダイヤモンド社から出して頂いた事がありますが、生きている時間が残り少なくなった昨今は、今更ビジネス書を書いても意味がないという思いが強くなり、「外村直樹」のペンネームで、中編、長編をあわせ、既に10作の純文学系の小説を脱稿しています。しかし、以前に「ふぉとん」という季刊の総合文芸誌に掲載して頂いた1作を除いては全て未公開で、上述のような「電子出版」の普及を辛抱強く待ち続けている次第です。
ちなみに、私にとってこの上なく嬉しかったのは、この「ふぉとん」の読者通信で、或る方から次のような言葉を頂いた事です。
/////////////////////////////////////
前号、外村直樹氏の「雨」を楽しく読みました。正直を言いますと、私は文学論など難しい話は苦手なたちです。(中略)ところがある休日の朝、ふと手にとって読み始めたこの「雨」が、主人公の視点がとても自分に近くて、面白くてやめられなくなったのです。そういえば私もかつては「小説」が好きだった事を思い出しました。そして読み終わったあと、こういうしっかりとした手ごたえのある小説の世界こそが、自分にとっての「小説」の意味だったのだと気がつきました。(後略)
//////////////////////////////////////
色々な事を深く考えている小説等の書き手なら、「何人の人に読んで貰えたか」という事以上に、たとえ僅かな数であっても、こういう「真の理解者」に出会える事が何よりもの喜びでしょう。それを考えると、「電子書籍の可能性」に益々期待を持ちたくなるのです。