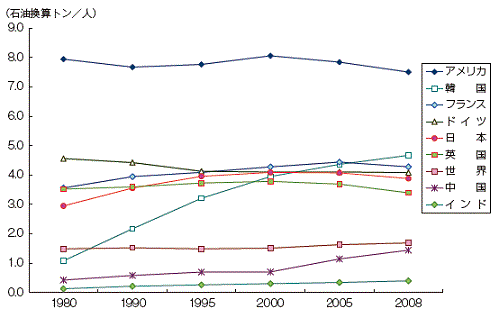私は今後我が国で、相次いで増税が行われたとしても、期待される税収が上がらないのではないかとみる。その理由は日本の課税当局の徴税能力の低さ(これは様々理由があるので後日何回かに分けて書きたい)と地下経済の拡大にある。地下経済とは、合法・違法を問わず、公式経済の範囲外で生み出される経済取引のこと。アゴラでも、最近慶応大学の池尾和人教授が欧州の地下経済(Shadow Economy)について触れている。
Bloomberg Business Weekも2010年7月に“Shadow Economies on the Rise Around the World”(世界で台頭する地下経済)と題した論評を掲載している。この分析は、ジョアン・ケプラー大学リンツ校のFriedrich Schneider教授らの調査による“Shadow Economies All Over the World”(世界の地下経済)を元にしている。これによると、地下経済の規模がGDP比で40%以上に達している国は、世界に50カ国以上もある。今何かと話題のミャンマーの地下経済の規模は対GDP比で50.3%。イタリアは27%、ギリシアは27.5%、スペインは22.5%と推計している。消費税が高い北欧諸国ではこの数字は17~19%程度となっている。アジアでは韓国が27%と断トツでこれはイタリア並みの高さ。ちなみに、この調査によれば、日本の地下経済の規模は対GDP比で11%とされる。対GDP比では世界で5番目に小さい地下経済だ。
しかし、その規模を単純計算してみれば、日本のGDPざっくり500兆円として、55兆円ほど。韓国のGDPは80兆円ほどなので、地下経済の規模は22兆円ほど。日本の地下経済は韓国の倍以上の規模で、金額としては小さいとはいえない。
Schneider教授らの分析によると、地下経済の拡大の原因は“税率のアップ”と“規制の強化”であるようだ。我が国でも今後、消費税率がアップされれば地下経済の拡大があるのではないか?
歴史を振り返れば、江戸時代にも地下経済の拡大があったようだ。徳川幕府の年貢の基本は7公3民。領主が7割取り立てて、農民の手元には3割だけ残るというもの。「百姓は活かさぬよう、殺さぬよう」ということだろうが、苛烈な税制である。学習院大学の歴史学者、故大石慎三郎教授らによれば、何も当時の農民はこの税率通りに払っていたわけではないようだ。
課税を逃れる手段は二つ。一つは過少申告。農業技術や農業器具の進化によって米は大幅に増産していたが、課税基準の石高は不変であったようだ。例えば、農業技術の進歩で実際は12俵取れても、昔ながらの10俵と申告して課税されていたわけだ。次に作物の多様化である。畑作の進化で付加価値の高い綿実油や綿花が密かに生産されるようになった一方、課題の対象はもっぱら米の石高であった。綿花や綿実油の生産については幕府も藩もノーマーク。米以外の畑作で潤った余剰は非課税であった。
このずさんな徴税の背景には、各藩の官僚となった世襲採用の武士たちの能力の低さのおかげである。彼らの徴税能力の低さが地下経済の拡大に貢献していた。大石教授は「無能なエリートの効用」を説く。世襲の武士たちが、農民たちの現場を見ずに徴税をしていたことが、実効税率が低下させた。このおかげで農村に余剰が生まれ、交換経済が発達し、この余剰は商人の手を通じて都市にも伝わった。都市の余剰が江戸中期(18世紀~)の元禄文化につながった。
当時の徴税の長閑さには理由があった。幕府や諸藩による治水や道路網、城下町整備等の公共事業はひと段落していた。そのため、幕府や藩側にも強烈に税金を取り立てる必要性はなかった。また、無理に徴税しようとすると、農民の反発は大きかった。まず、一揆で反抗された。この後の増税改革である、享保の改革、寛政の改革、天保の改革では幕府の直轄地でも一揆がおこった。上杉鷹山がいた米沢藩も一時増税で財政難を乗り切ろうとしたが、たまりかねた農民が領外に逃げ出し、課税対象の作物を打ち捨てた。この増税で藩財政はさらに一気に悪化した。
今の日本政府の財政状況は当時の江戸幕府のように課税にのどかにはなれない。しかし、“高税率イコール高税収ではない”ことは歴史や諸外国の事例が証明している。Schneider教授らの分析の結論は、「地下経済の拡大を抑えるのは、効率的な徴税や課税や規制緩和ではない」としている。彼らは、いかにして、“納税のモチベーションを高めるか”にあるとしている。つまり、日本政府が今目指す“北風政策”では地下経済拡大が免れず、“太陽政策”が待たれるということだ。それは税の徴収・分配機関である政府への信頼(使い道から徴税の公平さまで)と払った税に見合う行政サービスの構築にあるだろう。このあたりにつきあらためてアイデアを述べていきたい。