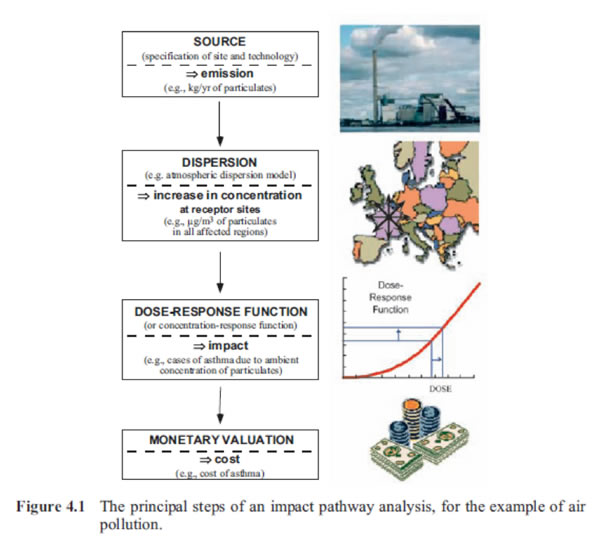宇沢の本がケインズの一般理論の解説書の中では最も優れていると思うが、どうも価値観が入りすぎている。
失業は重要だが、ケインズは組合を重要視していたわけではない。
名目賃金と実質賃金の問題は、名目と実質という言葉の表面的な意味に惑わされてはいけない。
問題は、将来は不確実で、それはインフレ率もそうであるし、何よりも将来の需要が不確実であることによっている。
つまり、金融投資、実物投資と同じで、経済が底へ向かっているときは、どんな賃金水準でも雇用を増やすことはない、ということである。名目賃金の硬直性のみならず、そもそも解雇することにはコストがかかり、それはカネだけでなく、経営者のエネルギーもそうであるし、仕事を教えるという、会社としても労働者としても、ある程度の文脈投資(その企業やビジネスに特有のやり方、他の職場ではそのままでは役に立たない)が必要であるが、すぐ解雇になるのであれば、それは手控える。手控えると仕事ができないから、仕方なく、不況なのに人手不足で、中小企業なら、社長と家族だけでなんとかしのぎきる。注文も、またすぐなくなるかもしれないから、最小限で対応する。
こういう状態では、実質賃金も名目賃金も、どちらにせよ、賃金が下がり続けても、労働需要が生まれない、ということだ。
しかし、それならば、実質ではなく、名目である、ということにこだわり続けたのは、名目で説明するとわかりやすいからである。
インフレ率がもっとも経済学者たちが反論できない、明らかな不確実性の例であるからである。
将来の需要への期待が不足する、と言っても「期待」はかなり議論の分かれるところである。(ちなみに、ここでわかりやすいとか、あやふやなものである、という実体は関係ない。伝統的な権威のある経済学者たちを論破すればいいので、本質からずれてきても、わかりにくくても、些末であっても、完璧に論破できればいいということなのだ。それがケインズのスタンス。)
明らかに将来不確実なのは、インフレ率。しかも、生産は、今投資して、今雇用して、しかし、生産が完成し、売り出すのは数ヶ月後。ここに不確実性がある。物価水準が不確実であれば、それは投資も雇用も手控える。だから、インフレ率の不確実性が、投資、雇用控えを生み出すのである。
だから、その意味でデフレはインフレよりも問題があるのである。
だから、ケインズは、一般理論の中でも、期待を強調し、実質と名目の違いを主張した。つまり、名目と実質の違いは、インフレ率の差、一般物価水準との差ではなく、今と将来の差なのである。
実質賃金とは、今の物価水準との比較ではなく、今の名目賃金と生産物が完成して、その製品を売り切る時の物価水準の差なのである。だから、不確実なのだ。
ここに、期待と不確実性と物価水準とは離れた、実質と名目の違いが有機的につながるのである。
だから、ケインズからリフレという金融政策による物価の上昇を生み出す政策をインプリケーションとして(含意として)引き出すのは、無理があるだけでなく、誤っているのである。
なぜなら、インフレ率を無理に高めるのは、将来のインフレ率に関する不確実性を増すことになるからである。
ゼロインフレ率で安定している方が、インフレ率が2から4%の間でぶれるよりも、望ましいのである。
だから、ケインズは金融政策ではなく、財政政策、しかも、穴を掘って埋めるという例示をした。その理由は、前述の文脈投資がいらないからである。無駄な仕事でも何でもいい、投資もしなくていいし、教え込まなくても良い、何か最もらしい仕事をさせて、それにより、賃金を払い所得から需要が回り出せばいい、ということなのだ。だから、むしろ、役に立つ仕事、と考えていたら、誰もが躊躇する。躊躇しなくていいのは、単純労働なのである。
こうなるといろんなことが見えてくる。
ケインズが言っている、名目賃金が下落し続けるときは、むしろ雇用が減ることもある、というのは意味不明に見えるが、この考え方で行くと、明瞭だ。
名目賃金が下落し続ける状態とは、需要が減り続けている可能性が高い、その証左だということになる。それが期待、将来不安から生まれたものであっても、結果として名目賃金が下がっていれば、それがシグナルとなって、みんながさらに雇用を控える。
それがケインズの意図、本質なのである。