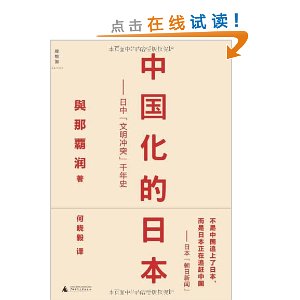
拙著『中国化する日本 日中「文明の衝突」一千年史』の中国語版が刊行されたため、発行元の招きで初めて北京を訪れ、わずか2泊3日ながら大変充実した時間を過ごすことができた。もっとも、中国に行かずに同書を書いた罰だと言われればそれまでだが、この企画は実現までが大変で、身をもって両国の文化の摩擦を体験させられることにもなったので、次第を報告してみたい。
「結果よければ過程無視?」
中国では「結果が正しければ過程はどうでもよい」が、日本では「過程が正しければ結果はどうでもよい」――というジョークがあるらしい。今回の話も、当社を翻訳元に選んでいただければ、「刊行後の北京ご招待」もつけますよという申し出はあったが、あくまでもメールでの伝達で、正規の契約条件には入っていない。そのため元々は、中国側のスタッフと内々の打ち上げをする程度のものかと思っていたのだが、先方としてはプロモーションのために私に講演や取材対応をしてもらうのが目的で、最初からその実現も込みで出版計画を立てていたらしい。
それだけ大きな話となると、草稿なしで適当にしゃべるわけにはいかないし、私は中国語ができないから、きちんと拙著を理解した通訳がつかなければ誤解される心配もある。そのため、「まずは細部を詰めましょう」と何度も連絡したのだが、とにかく「すぐ来てください。来月はどうですか」といった返事しか来ないのには閉口した。最後は、中国語版の翻訳者である山口大学の何暁毅先生が間に入ってくださって解決したのだが、その後も内容が確定するまでに、二転三転することになった。
中国で働く日本人の知人にも注意されたが、お互いの希望を少しづつ小出しにして、「すりあわせ」で物事を決めていくというやり方は中国式ではないようだ。「お願いします」と伝えると、相手がこちらの意向を汲み取ってくれて、逆に当方も向こうの事情に配慮して……というのが、日本人好みの「空気を読みあう」交渉術だが、そういうやり方は通用しない。中国の人を相手にする際はむしろ、はじめから「私の希望はこうだからやってくれ」「条件が満たされないならこの話はナシだ」と、はっきり「最終的な着地点」の方を明確にして話を進めないといけないと、複数の方に助言された。
もちろんこれは文化の相違であり、能力的・人格的な優劣とは関係がない。実際のところ、渡航する前は上記のトラブルから、出版社の仕事ぶりに正直不安を覚えたのだが、いざ行ってみると本当に至れり尽くせりで、新たなニーズを伝えても臨機応変、きめ細やかに対応してくれる。その代わり、(私のような)日本人好みの「前もって着実に」スケジュールを一歩一歩進めるという雰囲気は一切なしで、講演会の15分前まで普通にわいわい夕食をつついているから、心臓の弱いこちらは冷や汗ものであった。渋滞で到着が1時間以上も遅れ、座談会まで30分ほどしかない時点でレストランに滑り込んでも、平気で時間内に宴会する(食べきれない分は、タッパーで持ち帰る)。日本であれば夕食を抜くか、逆にイベントの開始を繰り下げるか話し合うところでも、そんなことは一切なく、最後に「帳尻」さえあえば他はすべて融通無碍という印象である。
中国文化論を体感する
現地の日本人の知人に指摘されて気がついたことだが、かように「順を追ってすりあわせ」ではなく「まず最初に結論から(それ以外はその場次第)」なビジネスマナーが定着しているのも、中国社会の流動性の高さと関係があるようだ。日本の場合は江戸時代以来、同じ村のメンバーが世代を超えてつきあい続ける「長期的関係」がベースにあるから、互いの顔色を絶えず確認し、ある地点で相手に無理をさせたら、次はこちらが折れて要求を飲むといった「微調整」でものごとを運ぶ。よくいえば「情けは人のためならず」、悪くいえば「八百長の貸し借り」と同じで、厚意をかければいつかは返ってくることが前提の社会だから、無意識のうちにそう振る舞うのである。
しかし中国の場合は、前近代から人々が根無し草のように移動し、職業も転々とする変化の速いネットワーク社会を営んできたから、長期的関係ではなくワンショット(一回きりの)ゲームを永遠にプレイし続けるのが常態である。毎回毎回が「今回限りの」つきあいだとすると、こちらが譲ったところで後で返してもらえるとは期待できない。むしろすべての希望を一方的にでも明示して、承諾した人とだけつきあうのが正しい戦略になる――とは、実は『「日本史」の終わり』(池田信夫氏と共著)でも書いたところであった。要は、頭でわかってはいても身体が実践できていなかったわけで、もの書きとしては恥ずかしい限り、本で読むばかりで現地を知らない人間の限界を痛感した次第である。
そうはいってもブッキッシュな癖はなおらないもので、島田虔次『朱子学と陽明学』の末尾に、陽明学の立場を河上肇の
たどりつきふりかえりみれば山川を 越えては越えて来つるものかな
という短歌になぞらえた箇所を、同地でふと思い出したりもした。要するにこの世界ではすべてが終わってしまっていて、そこから振り返ってはじめて物事には意味が生まれると考える、現実を「大肯定」する立場だという。一方の朱子学の立場は逆に、大西祝の
行けど行けど到らぬ空を慕いても 昇るや人の心なるらむ
なる歌に相当することが示唆されているが、つまりはこの世には常に、完全には達成しえない目標、無限に到達不可能な場所が残るという発想であろう。してみると、私はやはり後者の徒なのだろうか……などとぼんやりと考えて中国史を実感した気になるのだが、それもまた名所旧蹟を訪ねる余裕もなかったがゆえに、代わりに観念で満足する悪い癖かもしれない。
また思想でなく経済からの中国論では、しばしば目にする鍵概念に「包」(bao)というものがある。しいて日本語に訳すと「丸投げ請け負い制」くらいの意味で、その存在こそが中国経済を、いつまでも欧米流の契約社会に移行させない元凶とされることも多いのだが、何を読んでもいまひとつ腑に落ちない。しかし、要するに「出すべき結果」だけを相手に突きつけて、そのためには手段を選ばずなんでもやらせるという発想のことと考えれば、今回の件で実によくわかった気になる。まさか私の訪中程度でそんなことはあるまいが、場合によってはこの「手段を選ばず」のところに法令違反やピンハネ行為が入ってくる点が、批判されてきたのであろう。
かように書くと「やっぱり中国は野蛮だ」というふうに読む人がいそうだが、実はjob description(従事する職務内容の明確な規定書)なしで社員を雇うことで有名な日本的経営も、御社に入れたら「なんでもやります」という前提で労働者を使っているわけだから、欧米人から見れば一種の「包」だろう。ただ日本の場合は使用者との間に(江戸時代以来お得意の)長期的関係があるので、職務命令にしたがって「なんでも」やっている限り、解雇はされないという見返りがついていただけである。この慣行を悪用し「なんでも」やらせるだけやらせて、心身を壊したら使い捨てればいいというのが、昨今問題のブラック企業の発想だが、してみると、その点でもやはり日本は「中国化」しつつあると言えそうである。
與那覇潤(愛知県立大学准教授/日本近現代史)
※ 関連サイト「史論家練習帳」














