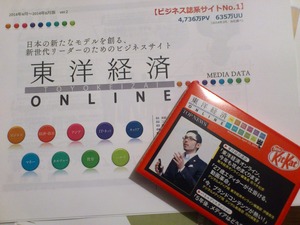科学スキャンダルと言えば、RNAをDNAへ転写する逆転写酵素の発見で1975年のノーベル生理学医学賞を共同受賞者したボルテイモア博士のスキャンダル事件ほど、米国科学界を震撼させた事件はありません。
一旦、黒と判定されたボルテイモア教授ですが、この事件発生後ほぼ10年後の1996年に、上訴委員会が再調査の上「不正の証拠は全くなかった」として、全ての処分を取り消して解決した形になっていますが、その余韻は未だに収まらない複雑な事件でした。
この事件を扱った英国の高名な科学史家ダニエル・ケヴルスの名著「THE BALTIMORE CASE : A Trial of Politics, Science, and Character」をニューヨークタイムス書評欄で紹介したROY PORTER記者は:
チャールス・ダーウインが、自分の荘園で自分のペースでひっそりと進化論を練った百五十年前とは異なり、大科学時代の到来と共に、今や血で血を洗う容赦ない研究競争と、飽く事の無い公的資金への渇望の行き過ぎが社会的な問題になっている。
にも拘らず、我々国民が科学スキャンダルと言う怪物を防ぐ術には驚くばかり無知である一方、研究資金確保の為に耳目を集めやすい研究への偏重を招いた事が、スキャンダルを増やす要因になっている。
と、小保方事件にも参考になる警告を発しています。
しかし、ボルテイモア事件以来大きく進歩したのが「ガバナンス(組織の統治形態)」です。
「ガバナンス」と言えば、直ぐに組織と規則の点検に走る日本と異なり、欧米では、トルーマン大統領の言葉として有名な「The buck stops here..( 私が仕事の全責任を取る.)」と言う一言に象徴される、「指導者」の質の点検から始まります。
“The buck stops here..”と書かれたプレーク(銘板)をホワイトハウスの執務机に置いていたトルーマン大統領は、1953年の退任演説で「誰が大統領になろうとも、物事を決めなければならない事は変らない。それは、何人たれども大統領に代って物事を決める事は出来ない大統領職とは、責任を他に転嫁せず物事を決め事が仕事だからである」と国民に説きました。
欧米の組織のトップが真剣に経営に当たる大きな要因には「責任」を取る事があり「謝罪などは仕事の範疇にない事にあります。
それに比べ、国会や記者会見の発言を見ると、理研トップの「Passing the buck(責任転嫁)」が酷すぎることは明らかです。
添付の理研トップの記者会見動画や宮崎信行氏のブロゴス記事「蓮舫さん『STAP細胞はありますか?』」をご参照頂けば、その酷さ加減はご理解頂けると思います。
これ等を見ますと、責任転嫁だけでなく愚かな部下の為に迷惑を蒙ったといわんばかりの他人事振りと「不正?」を犯した部下が真犯人でトップは寧ろ被害者の立場で何も謝罪する必要はないのだが、役職上やむなく謝罪すると言う不遜な態度には腹を据えかねます。
宮崎信行氏の記事には、理研トップの責任転嫁答弁が満載されていますが、その典型には以下のようなやり取りがあります。
蓮舫議員「野依理事長、STAP細胞はありますか?」
野依理事長「研究によって明らかにされるべきだ」
蓮舫議員「なぜ小保方さんは(切り貼りがあるなどの論文の不正について断定され)調査委員よりも先に処分されたのか」
川合理事「私が調べているわけではない」と答え、委員長不在の第三者委員会に責任を丸投げし、野依さんは「規定に基づいて処分した」
と答弁しました。
小保方さんを断罪した調査委員会の石井委員長を含め、合計三人の調査委員にも「切り貼り」があった事がネットの追求で判明しましたが、小保方さんとは異なりお三方とも「不問」に付されると言うのも理研特有の不思議さです。
しかも、内部の中間報告段階で特定の部下を「不正」と断じる事は、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という近代法の基本である「推定無罪の原則」を、法律違反でもない倫理問題である本件に適用しない事こそ重大な人権侵害です。
それでありながら、「人権には特別の配慮をしている」と嘯く理研の鉄面皮振りには呆れる他ありません。
国会での証言や記者会見の様子は、既にマスコミに溢れていますので詳細には触れませんが、「理研は優秀な人間を集め,しかも若い科学者を抜擢して世界でも輝かしい実績をあげている
と理事長が自慢する「科学者の楽園」にしては、理研に対する世界の目は厳しく、昨年の理研の評価は32位で中国科学院の8位には遠く及びません。
自己宣伝とは裏腹に、理研に対する世界の評価が低い事を知る幹部が、「有力科学誌」に早く論文を掲載せよと研究者に圧力をかけていた事は容易に想像できます。
古い文化を誇る欧米各国には、A fish rots from the head down(魚は頭から腐り出す)と言う諺があると聞きますが、この諺は理研の現状にぴったりです。
記録を見ると、理研幹部の責任転嫁「三羽鴉」が野依理事長、研究担当の川合理事、コンプライアンス担当の米倉理事の三人だと言う事はよく判りましたが、中でも野依理事長の「自分の世代には考えられなかった程、若手の倫理は荒廃しており、何とか教育し直さなければならない」と若手世代全体の倫理感の低下を嘆いたり、「中間指導者の指導力が劣る」と、ミドルマネジメントを批判し「この様な不正の再発防止には自分が先頭に立って取り組む」と自慢するのもみっともない話ですが、若い世代の倫理の低下を嘆くなら、ご自身が脱税容疑をかけられ重加算税を課せられたご経験は倫理とは関係ないとでも思われるのでしょうか?
脱税の懲罰には延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など色々ありますが、重加算税は意図的な脱税や所得隠しなど最も悪質なものだけに課される懲罰で、鳩山元首相やノーベル賞受賞者の野依理事長のような有名人とは違った一般国民なら、刑務所入りした可能性すらある重大違法行為です。
個人攻撃は禁手ですが、脱税がご自身も認めた公知の事実であるにも拘らず、若い世代の倫理観の低下を非難するとしたら、ノーベル賞を「葵の紋」と誤解されているのでは? と心配になります。
いずれにせよ、理研のトップが他人に厳しく自分には甘いと言う事だけははっきりしました。
小保方事件を受けた政府は、理化学研究所などを新設の「特定国立研究開発法人」に指定する法案の提出を見送ることを決めたそうですが、これは適切な決定だと思います。
組織が巨大化し、つぎ込まれる国費が大型になればなるほど政治の介入を招き、スキャンダルの解決を更に困難にすることは先進国共通の悩みですが、それを防止するガバナンスの要諦は、トップの人選とミッションステートメントにあり、組織や規則は補助具に過ぎません。
責任転嫁のトップの多い日本の研究組織は、組織統合による総花式大型化はやめにして、選択と集中により分散化に向かうべきだとおもいます。
ビジネスの世界では、「When an organization or state fails, it is the leadership that is the root cause.(組織や国が滅びる時は、その根本原因は決まってリーダーシップにある)」と言われていますが、頭が腐っている理研の様な組織では、先ず頭を切らない限り組織は衰えるばかりで、この改革を怠れば組織の推進力の担い手である若き研究者は浮かばれません。
したがって、鉄面皮で責任転嫁名人の現在のトップを即刻更迭する事が理研の改組の喫緊の課題だと考えます。
2014年5月21日
北村 隆司