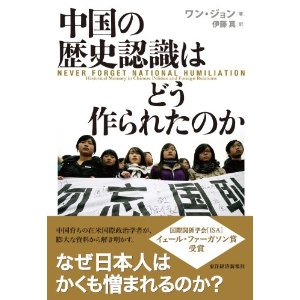「中国の歴史認識はどう作られたのか」 を読んで
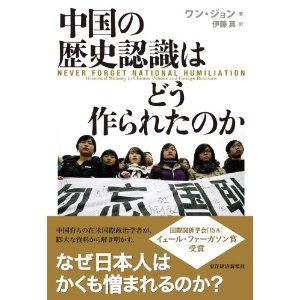
よく 「軍事的脅威は、他国の軍事力と意図の積である」 と語られる。公表される国防予算だけみても、この10年の間に4倍増を果たした中国軍事力の増強ぶりについては、いまさら語るまでもない。では、中国の「意図」とは何か。
―― 中国がその力をどのように使おうとするか ―― こそが、平和か戦争かを決するのである。(スーザン・シャーク)
“Never forget national humiliation” ( 勿忘国恥:国の受けた恥辱を忘れるな) を原題とする本書は、19世紀中葉以降100年間にわたって外国の侵略を受け、領土の割譲・賠償金の支払い・国権の喪失 (不平等条約) を強いられ、辱められてきたという 「歴史的記憶」 が中国の国民アイデンティティを形成しただけでなく、中国の内・外政に対して如何に強い影響力を与えてきたことを論ずる本である。かねて自己流で中国の「歴史トラウマ」を論じてきた私は、この本で 「我が意を得た」 だけでなく、様々な先行研究の存在を知って啓発された。
著者の汪錚 (ワン・ジョン) は、雲南省昆明生まれ、北京大学大学院を修了し、政府系シンクタンクで働いた後、米国に留学し、いまは米国の大学で教鞭を執る国際政治学者である。
著者は先行研究を引きながら、「恥辱の一世紀」 という集合的な歴史的記憶 (「歴史」ではなく 「記憶」) を 「マスター・ナラティブ」 (大きな物語) と呼び、そうして 「選び取られたトラウマ」 が中国人という集団を団結させ、そのアイデンティティを形成し、対外政策とくに外国との紛争時における行動の決定に際して決定的な役割を果たしてきた、とする。また、集合的な記憶というものが今日的な考え方や関心に合致するように再構築されること、そして支配層が国民の支持を集めるためのツールとして利用され加工されるものであることを論証する。
以上のような認識枠組みを呈示したうえで、著者は19世紀以降の中国で、ナショナリズムがどのように生成、変遷し、政治利用されてきたかを克明に追跡する。そこで紙面を割いて掘り下げられたテーマは、「愛国主義教育」の変遷や1990年代以降三度にわたる米国との外交的衝突 (注) を素材として、「歴史的記憶」が現実の対外政策決定にどのように作用したかの例証などである。
(注:1996年の台湾海峡危機、99年の在ユーゴスラビア中国大使館爆撃事件、2001年海南島沖での米中航空機衝突事件)
中国が統治の正統性を強化するためにナショナリズム (愛国主義) を利用したことは、こんにちの日本で既に 「常識」 と化しているが、最初にこの問題を指摘した鳥居民氏の「『反日』で生きのびる中国」(草思社)のインパクトが強すぎて、ややもすれば「江沢民が1994年に愛国主義教育を始めた」式に理解されていることに、私は違和感を覚えてきた。「そんな簡単な、歴史の浅い話ではないだろう!?」 と。
帝国日本が柳条湖事件を引き起こして始めた「満洲事変」を調査するため国際連盟が派遣したリットン調査団の報告書(1932年)は、国民党政府の歴史教科書が排外主義に彩られすぎていることを批判している。「愛国主義教育」は昨日今日始まった話ではなく、きっかけになった五四運動から数えれば、既に百年近い歴史を持っているのである(拙ブログ「中国の「愛国主義」について」参照)。
本書は、一面で以上のような私の違和感を裏付けてくれたが、同時に、私が見落としていた側面も教えてくれた。「愛国主義教育」は、毛沢東の時代にいったん断絶していた事実だ。国共内戦に勝利した毛沢東は「被害者の物語」を好まなかったし、階級政党だった当時の中共は「偏狭なナショナリズムや愛国主義」(本書中の表現)より 日本を含めたプロレタリア(無産階級)の国際連帯を重視したからだという。
「愛国主義教育」は天安門事件後に再開され、「被害者の物語」も復活する。本書は、愛国主義教育は天安門事件によって「思想信条の空白と共産党の正当性の失墜という問題に直面した共産党政権を改めて正当化するために利用され」、教育の内容は「中国という国に構造的に組み込まれ、政治機構に深く根を下ろし、共産党の新たなイデオロギー上のツールとなった」(145、149頁)と記すとともに、天安門事件直後に「過去の教育の誤り」を告白した鄧小平の言葉を引用して、再開が中共の総意によるものであることを示唆している。
本書が記す、この「愛国主義教育」再開の過程は、天安門事件後の中共政治路線の動揺(左傾・保守化→鄧小平の南巡講話による左派への反撃→「社会主義市場経済」 の宣言等)と時期を同じくしており、両者の関わりが非常に興味深いのだが、「オタク」過ぎるテーマになるので、後日別稿で論ずるとしよう。
さて、本書を読んでの感想を2点述べたい。
第1、中国では元「列強」の国々との間に紛争が生じると、決まってナショナリズムが大きなうねりを起こす。著者はそこで「歴史的記憶」が果たす役割を論証しているが、わたしはさらに掘り下げて、「歴史的記憶」がナショナリズムの風に異論を挟むことを許さない強烈な「集団同調圧力」を内部に生むことにも触れてほしかった。
中国では、日中関係が荒れるたびに一辺倒な反日言論が生まれ、交流事業のドタキャンが相次ぐが、そういうとき、中国人の内面には「このナショナリズムの風に抗うことは、中国人として許されるのか」という葛藤、さらには「抗えば『漢奸』(売国奴)とみなされて社会的制裁を受ける」という不安感が強く働く。
つまり、中国ナショナリズムの「易燃性」は、多分に集団同調圧力によって支えられているのだということを指摘しておきたい。いかに中共が「愛国主義教育」に力を入れたとはいえ、中国人は「それで全員洗脳されてしまう」ほど「天真爛漫」な国民ではない。
著者は多くの識者と同じく、共産党が統治の正統性の拠り所とするナショナリズムが、まま政府も統制困難な暴れ馬と化す危険を指摘して、「ナショナリズムは共産党にとっても諸刃の刃だ」とする。それは内政の困難さを増すだけではない。同調圧力に強要されたものであるにせよ、中国人の「一辺倒」な反応が、中国という国と国民に対する国際社会の違和感をどれほど高めているか分からない。この傾向に変化の兆しが見えないと、中国の平和的台頭は阻害されるだろう。
昨今は、ナショナリズムの集団同調圧力に抗して自らの意見を述べる若者も増えているが、年配者は、それを見て、社会的制裁の怖さを知らない「若者の経験不足」を危惧する。今後、年配者が「だから言わんこっちゃない」と言うのか、それとも「時代は変わった」と言うのか、中国社会の行方は未知数だが、私としては、ぜひ変わってほしいと願うばかりだ。
第二、原書は英文で書かれ、外国人に 「なぜ中国と中国人は、ああいう風なのか」 を説得的に説明する本だが、その内容だけでは物足りなさが残る。「そういう現状の功罪、さらにはあるべき論を論じないのか…」読み進めながらそんな印象が再三浮かんだのだが、それは本書末尾の数頁にあった。
ナショナリズムが歴史的記憶を目覚めさせ、歴史的記憶がナショナリズムを煽るというフィードバックのサイクルを中国が断ち切るためには、歴史を解釈する「ナラティブ」(物語)を変えなければならない。(346頁)
歴史的神話とトラウマから成る強力な心理構造 (コンプレックス) から解放されない限り、複数政党型の民主制は中国を危険な展開へと導く可能性がある。…中国は国家の復興を求めている。ただしその過程で、金融制度や高速道路網ばかりでなく、政治制度や市民教育も近代化する必要がある。すでに失われて久しい栄光を回復する夢は、国家建設のより現実的な目標に向けたものでなければならず、同時にナショナリズム色をいっそう薄めたものでなければならない。中国のリーダーやエリートたちはそのことに気づくべきである。
…本書では、中国における歴史の「大きな物語」(マスター・ナラテイブ)に注目してきた。…だからといって、過去数世紀間に中国の人民が体験してきた内戦、革命、集団的暴力、飢饉を含む残虐な国内紛争を忘れてはならない。政府の公式の説明の中では、国内的な紛争は、いまだに真実の多くがひた隠しにされているのだ。…党のリーダーたちは「国恥を忘れることなかれ」と国民に説いてきた。だが、共産党によって引き起こされたとてつもなく大きな失敗や大惨事については、議論をひたすら封じてきたのである。
政権政党たる共産党の支配の正当性は、歪曲された「歴史的貢献」の上に打ち立てられてきた。その上、ねじ曲げられた物語は人々の歴史意識にしっかりと浸透している。歴史的記憶を拠り所とするこうした政略は、大衆の支持を党に結集し、社会を結束させる手段を中国共産党にもたらしてきた。そうした事実を踏まえるなら、中国の民主化はこれらの歴史的真実を明らかにすることでようやく緒につくと言えるのかもしれない。
その意味で、中国の内政と国際的志向にとって歴史とその記憶が持つ重要さ、歴史的記憶というレンズを通して今日の中国が抱える問題を考察することの意義が、いっそう明確になるだろう。(356、357頁)
自らも 「集団的記憶」 の束縛を受ける中国人の著者にとって、こう指摘することは勇気が要るはずだ。著者は慎重に発言の間合いを計って、最後に寸鉄人を刺す言葉を放っていた。