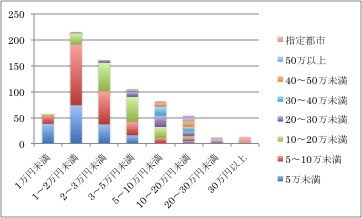きょうは「あの日」から69年目の8月15日である。あの日をリアルタイムで記憶している人も少なくなったが、あの日をめぐる論争はやまない。今年は朝日新聞が新たな「燃料」を提供して、また火の勢いが強くなった。どこの国でも敗戦体験は複雑なのだろうが、日本のそれはとりわけ屈折している。
その最大の原因は天皇である。独裁者ヒトラーがヨーロッパを征服するという明確な目的をもって始めた戦争とは違い、日本の戦争は何のために始めたのか、いまだにわからない。その責任者とされる昭和天皇は、最後まで開戦に反対していた。だとすれば「天皇陛下万歳」と叫んで死んでいった兵士は、いったい誰のために死んだのだろうか。本書は、その謎を解く鍵を靖国神社に求める。
靖国神社は「日本国のために心ならずも戦場で散った人たちを追悼する施設」ではない。あくまでも「天皇のためにみずから進んで死んでいった戦士を顕彰する施設」なのである。ここでは「朝敵」は祭られないので、戊辰戦争や西南戦争の「賊軍」側の戦死者は対象にならないのだ。(p.17)
靖国神社は「国家神道」によってできたものではない。その始まりは1862年に行なわれた「招魂祭」で、これは安政の大獄で幕府に殺された志士を慰霊する行事だった。日本の伝統には、戦死者が神になるという信仰はない。「英霊」の概念は、朱子学の理気論をもとにして藤田東湖がつくったものだという。幕末の招魂社は、幕府に殺されたテロリストをまつって同志の結合を強める施設だったのだ。
討幕運動は、祭政一致の「国体」を復興させる儒教的な革命だったが、そこに特定の政治理念があったわけではない。しいていえばバラバラの藩では外国に勝てないので統一しようというナショナリズムだが、それをまとめる政権は長州閥であり、「勝てば官軍」だった。その機会主義をカムフラージュするために「万世一系」の天皇家への大政奉還というフィクションが利用された。
明治期に靖国神社として政府が維持・管理するようになったが、国営化されず、一貫して皇室の神社だった。しかしそれは日清・日露戦争をへて「国体」を護持するシンボルになり、兵士は「靖国で会おう」を合言葉に散って行った。天皇のために戦えば、身分の違いを超えて神としてまつられることが、「皇軍」の大きなモチベーションになったのだ。
それは前近代的な非合理主義だが、戦争とはいつの時代にも非合理的なものだ。合理的に判断したら、誰も戦場には行かない。人々を戦争に駆り立てるには、ある種の宗教的熱狂が必要だ。それを実現したキリスト教徒やイスラム教徒が、神の名によって殺した人数は日本人の比ではない。
そういう一神教をもたなかった日本人が、短期間に「国体」に統合されたのは驚異的だ。薩長の藩閥が政権を私物化している実態を隠し、儒教的な革命に日本の伝統信仰の装いをもたせ、普遍的な「国家」を装うために、古来の天皇といイデオロギー装置が使われた。
それは当時の大衆はほとんど知らない存在だったが、短期間に日本の「伝統」になった。もともと同質的で、日本語という「想像の共同体」を共有していたせいもあるのだろうが、休眠状態だった天皇を引っ張り出して「機軸」にした明治国家のマーケティングは、きわめて巧妙だった。
今の靖国神社には、よくも悪くもそういう求心力はないので、首相が参拝しても実害はないが、それはいささか奇妙である。靖国はアーリントン墓地のような戦没者を追悼する国家施設ではなく、天皇家の私兵をまつる宗教法人にすぎないからだ。もちろん安倍氏個人が参拝するのは自由だが、首相が公然とテロリストを「尊崇」して、中韓に外交的カードを与えるのは賢明とはいえない。