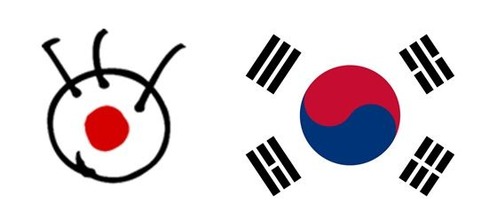「ゆきゆきて神軍」は、日本のドキュメンタリーの最高傑作である。奥崎謙三は天皇の戦争責任を問い続け、かつての上官が部下を射殺した責任を問うために自宅に乱入して傷害事件を起こすのだが、彼の問いにはだれも答えない。彼の苛立ちの中から、あの戦争の本質が浮かび上がってくる。
それが朝日新聞を初めとする戦後サヨクのいうような「天皇制国家によるアジア侵略戦争」だったら、問題は簡単だ。責任者は天皇とA級戦犯と軍部であり、彼らを処刑すれば問題は解決する。
しかし彼らの元祖である丸山眞男は、そうは考えていなかった。30年代前半までは、立憲君主制を守る官僚や知識人の重臣リベラリズムが生きていた、と彼はいう。明治憲法はリベラルな天皇と彼を取り巻くエリートが国をコントロールする立憲君主制だったが、その岐路は1935年の天皇機関説事件にあった。
右翼の「国体明徴運動」が議会やマスコミで高まると、リベラルたちは沈黙し、文部省は「国体の本義」を出し、明治憲法は万世一系の「現人神」による統治に変質していった。軍部に対抗する立憲主義の拠点だった昭和天皇は結局、軍民の作り出す「空気」に抵抗できなかった。
明治憲法は、その権威主義ゆえに反動化したというより、その立憲主義にもかかわらず戦争を止めることができなかったのだ、と丸山はいう。1946年に有名な「超国家主義の論理と心理」を書く中で、彼は重臣リベラリズムの限界に気づく。
敗戦後、半年も思い悩んだ挙句、私は天皇制が日本人の自由な人格形成――自分の良心に従って判断し行動し、その結果にたいして自ら責任を負う人間、つまり「甘え」に依存するのと反対の行動様式を持った人間類型の形成――にとって致命的な障害をなしている、という結論にようやく到達したのである。
あの論文を原稿用紙に書きつけながら、私は「これは学問的論文だ。したがって天皇および皇室に触れる文字にも敬語を用いる必要はないのだ」ということをいくたびも自分の心にいいきかせた。のちの人の目には私の「思想」の当然の発露と映じるかもしれない論文の一行一行が、私にとってはつい昨日までの自分にたいする必死の説得だったのである。(「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」『丸山眞男集』15)
この論文で彼は「無責任の体系」を生み出した原因を天皇制に求めるが、それは講座派のいうような絶対君主制ではない。むしろまったく権力をもたない天皇がこれだけ大きな精神的権威をもった点に、その特徴がある。天皇はつねに臣下の上奏を受けて「しらす」とか「きこしめす」という受け身の形で意志を表明するので、意思決定はボトムアップであり、国家としての目的がないのだ。
これは日本の伝統ともいえる。最近の研究によると、織田信長でさえ統一国家を企図してはいなかったという。明治維新は一挙に国家統一をなしとげたようにみえるが、それを支えたのはナショナリズムではなく「天皇家への忠誠」という私的な心情倫理だった。よくも悪くも国家意志の欠如は、現代の政治にも受け継がれている。