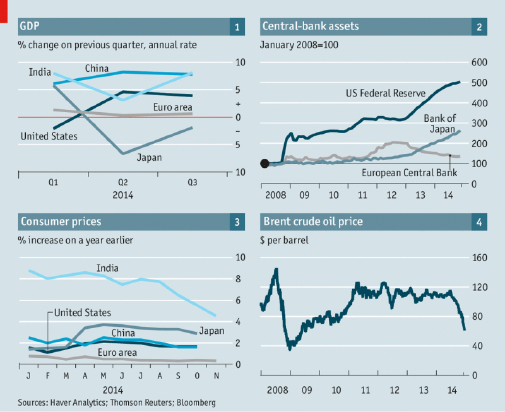団塊世代が75歳以上となる2025年には高齢患者が激増し、医療費は現在の1.5倍、介護費は2.4倍になる。今年の新語・流行語大賞にもノミネートされた「2025年問題」である。
社会保障にとっての当面のヤマ場ともいうべき2025年問題を乗り越えるため、政府が出した答えが「在宅」での医療・介護の推進であった。
「高度急性期」→「急性期」→「回復期」→「慢性期」と4つの医療機能の流れをスムーズにし、さらに訪問サービスを充実させることで、老後は自宅などで暮らすようにしようというのだ。
こうした構想を実現するため、政府は2つの政策を急いでいる。(1)都道府県ごとの病床機能の再編、(2)地域包括ケアシステムの構築─だ。診療報酬が高くつく高齢の入院患者を減らし医療費を抑制しようというのが大きな狙いだが、高齢者数の急増に病院や介護施設の建設が追いつかないという事情もある。地価が高く用地確保の難しい東京圏などでは高齢者向けベッドの整備は社会問題に発展しそうでもある。
■病床機能の再編は実現可能か
とはいえ、これらの政策が簡単に実現するわけではない。まずは、1つ目の柱である病床機能の再編から見ていこう。
各都道府県が策定する「地域医療構想」の区域ごとに、医療関係者が集まり「地域医療構想調整会議」を開いて協議するというのだが、各病院とも長年培ってきた地域の患者からの信頼、医療機関としての“暖簾”がある。急性期病院と回復期や慢性期の病院とではイメージも、扱う患者も大きく異なる。各病院の経営者とすれば、再編の必要性は
理解をしていても、長年かけて築き上げてきた“暖簾”を積極的に下ろして病床機能の転換に協力しようとはならないだろう。
それでも再編に応じる病院というのは、生き残りをかけ悩み抜いてのことだ。決断に足る説得力のある患者数予測がなければ無理な話である。1カ月先を見通すことさえ困難な時代に、将来の患者数をどこまで正確に言い当てることができるのだろうか。
病床機能の再編にはもう一つ困難がある。長期展望が見えないことだ。
高齢化が行き着くところまで進んだ地域では、高齢者が死亡すると直ちに人口が減る。すなわち、不足する医療機能を一時的に充足できたとしても、患者の総数そのものが減ったのでは4つの医療機能すべてで過剰となりかねない。病院にしてみれば、高齢者数が増えている間は患者数も増え経営も安定するが、人口減少局面に転じた途端に患者不足に陥るということだ。病床転換を図ったところで患者不足問題の根本解決に至らないのでは、リスクを冒そうという気にはならない。すでに「患者不足に陥る前に」といった理由で、大都市圏での展開を図る地方の医療機関もある。
そもそも、政府が都道府県単位で医療計画を立てることが疑問だ。東京圏への人口集中が加速し、民間有識者からなる「日本創成会議」の分科会などは2040年までに自治体の半数が「消滅」の危機にさらされると指摘している。人口移動予測をどう加味するからよって推計は大きく変わるのではないのか。
■地域包括ケアシステムの課題
次ぎに、2つ目の柱である地域包括ケアシステムを考えてみよう。地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、医師や介護職員、ケアマネジャー、ボランティア、企業などが連携し、往診や訪問介護、生活支援といったサービスを提供する構想のことで、厚生労働省が力を入れている。区域ごとの病床機能の再編がうまく行ったとしても、退院後に行き場が確保されなくては在宅での療養は実現しない。
ところが、地域包括ケアシステムの普及も遅々として進んでいないのが実情だ。
なぜ、地域包括ケアシステムの立ち上げが難しいのか。その要因はいくつもあるが、そもそも「包括ケア」という名称からしてイメージが掴みづらい。調整役を果たすべき自治体の担当者からして試行錯誤の連続なのである。
システムを有効に機能させるには医師のリーダーシップが不可欠だが、医療関係者には「医療と介護は別もの」と考える人が少なくない。担当者会議を開いても医師が欠席するケースは珍しくないのである。一部で成功している例もあるが、その多くはノウハウと熱意を持った自治体担当者や厚労省出身者が深く関わっていたり、人柄のよい医師の積極性によるところが大きかったりするところである。
地域包括ケアシステムを機能させるには、高齢者本人や家族はもとより、事業者や地域住民に在宅医療・介護への理解と覚悟が問われるが、家族や親族のサポートが得られにくくなっていることが第2の要因である。
介護事業所の人員確保が難しいことなどもあって「定期巡回・随時対応サービス」を提供するところは2014年8月時点で525カ所にとどまる。24時間のサービスを受けられることになっても、患者にしてみれば必ずしも利用したいタイミングで受けられるとは限らない。一人暮らしや夫婦とも高齢者という世帯が増え、これを補完することも困難だ。住民同士の支え合いもコミュニティーがしっかりしていない大都会などではより難しい。
第3の要因は、人口の減少だ。激減地域では地域包括ケアシステムを作ろうにも医療・介護スタッフが集まらない。診療所すらなくなった地域では作りようもない。
一方で、高齢者が激増する大都市部では、システムを構築できたとしてもサービスを利用したい高齢者数にスタッフが追いつかず、サービスが疎かになるとの懸念もある。一極集中が続いてきた東京圏では、高度経済成長期以降に上京した”かつての若者”が高齢化したことに加え、現在の勤労世代が老いた親を地元から呼び寄せていることもあり、高齢者数が激増しているからだ。
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、東京圏の65歳以上は2010年の731万8千人が、2025年には955万人、2040年には1,119万5千人と1.5倍増となる。2025年には東京都の介護施設利用者数が2010年の定員数比で2.5倍程度に膨れあがるとの国土交通省の予想まである。介護を要する高齢者向けベッドが極度に不足するということだ。これらのベッドからあふれ出た人たちを、地域包括ケアシステムですべて対応するのはかなりの無理がある。
認知症患者も増え、往診や訪問看護・介護を行っている現場の医師や看護師、介護職員からは高齢者のみの患者宅における劣悪な衛生環境に悲鳴の声も上がっている。病院機能再編も地域包括ケアシステムも乗り越えなければならないハードルがあまりに高く、医師の人柄任せ、地域力任せの地域包括ケアシステムの現状はあまりに心許ない。
治療の必要性の低い患者を入院させ続けている「無駄」は排除しなければならないが、厚労省は条件付きながら介護型療養病床の全廃方針を転換せざるを得なかったことも事実だ。
■在宅シフトの社会コスト
在宅シフトの議論では、医療・介護費用が高くつく入院や施設での療養に比べて在宅は安く済むということが前提となってきた。社会保障費だけに限れば抑制効果はあるのかも知れないが、在宅を成り立たせるために他の政策経費が膨らむのでは、トータルとしての社会コストが高くつくことになる。
在宅シフトは本当に2025年問題の切り札と成り得るのか。国民には在宅に対する不安が広がっている。“理屈”が正しくとも実現しなければ、そのツケは国民が支払うことになる。
河合 雅司
ジャーナリスト
編集部より:この記事は「先見創意の会」2013年12月23日のブログより転載させていただきました。快く転載を許可してくださった先見創意の会様に感謝いたします。オリジナル原稿を読みたい方は先見創意の会コラムをご覧ください。