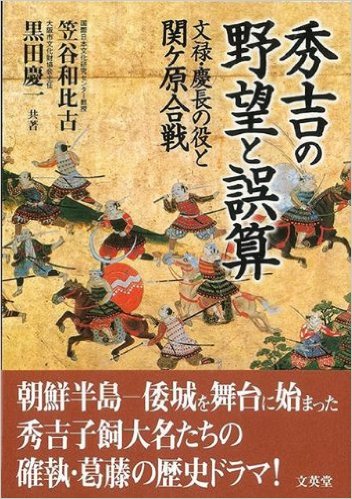林千勝著「日米開戦 陸軍の勝算―「秋丸機関」の最終報告書』(祥伝社新書)を読んだ。
本書の白眉は目からウロコの史実の発掘である。今日の近現代史は「日本軍、特に陸軍は無謀な戦争に走った」という見方が定着している。
だが、実は、陸軍は「陸軍省戦争経済研究班」のもと日米欧の経済力と軍事力を徹底的に調査、研究し合理的判断のもと「勝てる戦略」を準備して、開戦に臨んだという。著者の林氏はその歴史的史料を入手し、本書で詳細かつ具体的に検証している。
「無謀な戦争突入」という史観は左翼・リベラル系の学者やメディアによってのみ出されているのではなく、保守層の間でも幅広く定着している。その大きな要因の1つに、元都知事の猪瀬直樹氏が1883年に出版した「昭和16年夏の敗戦」がある。
安倍晋三首相の後継を狙う石破茂・地方創生担当大臣(元防衛庁長官)は同書を高く評価、「全日本人必読の書だ」と絶賛している。
猪瀬氏の著書は、昭和15年に開設された総理大臣直轄の「内閣総力戦研究所」の研究経過とその結論を綴ったものだ。同研究所は軍部・官庁・民間から選りすぐりの若手エリートを集め、「模擬内閣」を結成、豊富なデータを基に日米開戦を分析した。兵器増産の見通し、食糧や燃料の自給度や運送経路、同盟国との連携などについて科学的に分析、机上の演習を繰り返した。
その結果、昭和16年8月に「日米が開戦すれば日本は必敗」という結論を導き出した。結論を聞いた東條英機陸軍大臣(当時、10月に首相就任)は、こう述べた。
これはあくまでも机上の空論でありまして、実際の戦争というものは、君たちの考えているようにはいかない。意外裡なことが勝利につながっていく。君たちの結論はその意外裡の要素を考慮したものではないのであります。
「意外裡の要素」という言葉が科学的、合理的な分析を無視した「ヤマト魂に敵はない」につながる精神論を意味していると戦後、解釈された。猪瀬氏に言わせれば、総力戦研究所の「日本必敗」という結論を無視して無謀な戦争に突入したということになる。
私も「昭和16年夏の敗戦」の続編である「空気と戦争」(文春新書)を読み、猪瀬氏の見解に同意した。
だが、林氏によれば、陸軍省には戦争経済研究班があって、総力戦研究所とほぼ同時期に英米との戦争を徹底的に研究していた。
その結論は次のようなものだった。
1)極東の米英蘭根拠地を攻撃して自存自衛を確立。
2)東南アジア、インド洋からの英米による蒋介石政権への軍事物資補給ルート(援蒋ルート)を攻撃、支配し、蒋政権を屈服させる。
3)独伊と連携して英国の屈服を図る。
4)最強の敵となる米国とは極力戦わず、戦闘は日本近海に米国をひきつけて行う(戦争は本拠地からの距離の二乗に比例して自陣が有利である。だからハワイ攻撃などはしない)
陸軍省の研究では戦争の舞台は東南アジアとインド洋であり、当時の日本の海軍力と英国の海軍力を比較すれば十分に勝算があった。米海軍もフィリピン基地など日本近海の西太平洋側だけならば、当時は日本側の方が物量的に優れていた。
研究班のシナリオ通りに実行すれば、緒戦で英国軍を破って、東南アジアとインド洋の制空海権を奪取、日本はインドネシアの石油を確保。援蒋ルートも断ち切り、シナ大陸の戦闘を極めて有利に展開できる。
さらにインド、東南アジアが列強から独立し、日本に味方する。のみならずドイツと提携して米国によるインド洋、スエズ運河からの英ソへの援助ルートを断ち、独伊が欧州戦線で決定的な優位に立てる。
以上は、かなりの成功の可能性に富んだ合理的な戦略であった。
東條陸相は、この「陸軍省戦争経済研究班」の結論を知っていた。だが、昭和16年夏の段階で、極秘戦略の内容を民間人を含む総力戦研究所のメンバーに軽々しく開示することはできない。だから「意外裡の要素」と言ったのだ。
林氏によれば、そもそも総力戦研究所は研究所と銘打ってはいるものの、各省庁、大手民間企業のエリートを教育・訓練するのが主目的だった。
陸軍省の専門研究班は、エリートとは言え素人にすぎない若手集団の研究をはるかに超えた視野と戦略で日米英戦を考えていたというわけだ(ただ戦闘は英国を主敵とし、米国とは極力戦わないという点は総力戦研究所の結論と重なる面がある)。
むろん実際、陸軍省の研究班の通りに戦争していて、どうなったかはわからない。だが、陸軍省の計算がそれほど間違っていないという見方は米国にもある。「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」(ジェームズ・B・ウッド著、茂木弘道訳)などだ。
では、なぜ日本は敗戦したのか。「陸軍省研究班の通りに戦争を進めなかったからである。真珠湾攻撃をして米国を怒らせてしまったからだ。山本五十六連合艦隊司令長官の『暴走』が招いた敗戦だ、と本書は指摘している。