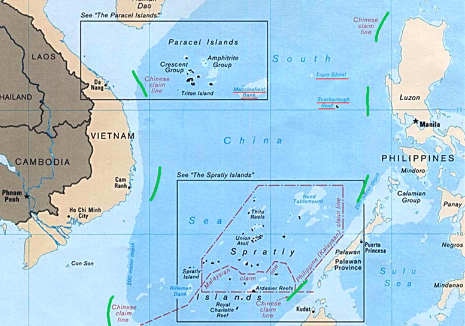安倍首相は参院選に勝って「アベノミクスの成果が認められた」と自画自賛しているが、成長率は下がってゼロに近づき、インフレ率はマイナスだ。アベノミクスは失敗したが、野党がそれよりだめなので自民党に投票した人が多かったのだ。彼が唯一の成果として誇る雇用の改善も高齢化と潜在成長率の低下によるものだ、というのが著者の見立てだ。
このへんをリフレ派(およびその影響を受けている政治家)は誤解しているが、失業率は需給ギャップの関数なので、需要が増えても供給が減っても改善する。日銀の計量モデルによれば、量的緩和で需給ギャップは2%改善したが、実質GDPは0.2%しか増えていない。つまり雇用が改善したのは成長率が上がったからではなく、その天井(潜在成長率)が下がったからなのだ。
この結果、成長率と潜在成長率は0~0.5%の間でほぼ一致し、完全雇用(自然失業率)に近い状態が実現した。現代の標準的な理解では、金融政策は需給ギャップを埋める短期的な調整だから、もはや金融政策の出番はなくなった。残る最大の仕事は、来たるべき金利上昇局面にそなえて出口戦略を考えることだ。
著者とは学生のころから意見がほぼ同じなので、ここではあえて意見の違う点を書いておこう。日本経済の最大の課題が「デフレ脱却」でも景気対策でもなく、生産性の向上だという点は賛成だが、その手段としては「働き方改革」やエレクトロニクスの国際競争力ぐらいしかあがっていない。私は金融システムが、もう一つの要因だと思う。
「メンバーシップ型」の雇用が日本企業の限界だという点は、1997年に拙著でも指摘したことだが、この対義語はオーナーシップである。企業の所有権――契約理論でいう「残余コントロール権」――の所在が曖昧になっているガバナンスが本質的な問題であり、日本的雇用慣行はその必然的な帰結なのだ。
コンセンサスで動く「家」型企業は品質管理には適しているが、イノベーションや危機管理などの大きな変化には向いていない。これは業績の好調な企業が、ユニクロやソフトバンクや任天堂などのオーナー型企業に多いという事実にも反映されている。日本の労働者管理企業の限界がみえた今は、企業買収・売却など資本市場でそれを再編成する必要がある。
しかし日本企業は持ち合いや買収防衛策で所有権の移転を極端に困難にし、経営者は保身のために余剰資金を貯蓄に回し、資本効率が低下している。おまけに経産省に支配された安倍政権は、産業政策や政府系ファンドで企業を救済しようとしている。著者の専門とする金融・資本市場の改革が、潜在成長率を上げる鍵だと思う。