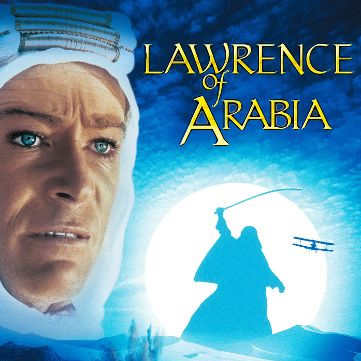当方は今年2月、駐独のシトナ・アブダラ・オスマン南スーダン大使と会見したが、インタビューを調整してくれたウィーンの「国連ジャーナリスト協会」(UNCAV)会長、アブドラ・シェリフ記者と国連記者室で会ったので、「少々、がっかりしているよ」と当方の思いを伝えた。何のことかというと、南スーダンの現状がインタビューした南スーダン大使が会見で述べた内容とは正反対の方向に流れてきているからだ。大使が強調した政府側と反政府間の和解の動きは暗礁に乗り上げているのだ(「駐独の南スーダン大使に聞く」2016年2月25日参考)。

▲映画「アラビアのロレンス」のポスター
「大使は紛争勢力間との統合政権の発足が近いと述べていたが、君も知っているように、現状は再び紛争状況だ。正直言ってがっかりしているよ」といった。それを聞いたシェリフ記者は、「僕も同じだよ。多くの国民が犠牲となっているからね」という。
「今回も部族間紛争の再熱だ。国民の中には昔のスーダン時代を懐かしく思いだす者が出てきている」という。同記者によると、「スーダン時代の問題は国政上のテーマが主だったが、南北分断後は部族間闘争だ。昔も部族間のいがみ合いはあったが、国政上の対立点の影で部族間闘争は台頭することはなかった」という。
同記者を糾弾しても南スーダンの現状は彼の責任ではない。そこでテーマを変えて話を続けた。イスラム教過激派テロ組織「イスラム国」(IS)が欧州のイスラム教徒をオルグする背後には、強い終末観があるからだといわれている。そこで聞いてみた。
敬虔なイスラム教徒のシェリフ記者は、「イスラム教にも終末観の強いグループは存在するがそれは一部に過ぎない。イスラム教徒の終末観といえば、アラブの遊牧民族、ベドウィンが放浪生活を終え、定着して建物を建て出したら、終わりの日が近い兆候だと受け取られていることだ。べドウィン民族のアラブ諸国では現在、高い建物(高層ビル)が無数、砂漠に立っている。その現象を見れば、終末が近い兆候といえかもしれないね」という。ちなみに、世界で最も知られたべドウィンは映画「アラビアのロレンス」の主人公だろう。
ユダヤ教では、ディアスポラだったユダヤ民族が再び国家を建設する日が終末の到来と受け取られている。すなわち、1948年5月14日のイスラエル建国の日から終末が始まったというわけだ。
キリスト教の場合にも多くの終末観があるが、最大のキリスト教派、ローマ・カトリック教会では終末観はあまり強調されない。むしろ好まない傾向が強い。ただし、新しいキリスト教グループでは終末観が信者を鼓舞する大きな魅力となっている。
シェリフ記者は、「イスラム教の場合はあくまで終末の“兆候”というだけで、終わりの日の到来を意味しない。兆候だから、実際の終末は数百年後到来するかもしれないし、もっと長いかもしれない。いずれにしても人知では計り知れないというわけだ」という。
聖書にも終わりの日がいつかは明記されていないが、その一方、「無花果の木からこの譬を学びなさい。その枝が柔らかにあり、葉が出るようになると、夏の近いことがわかる」(「マタイによる福音書」24章32節)と述べ、目を覚ましていなければならないと警告を発している。
シェリフ記者は、「南スーダンの和平実現の日も終末の日と同じだね。誰も分からない」と言って苦笑いした。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2016年9月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。