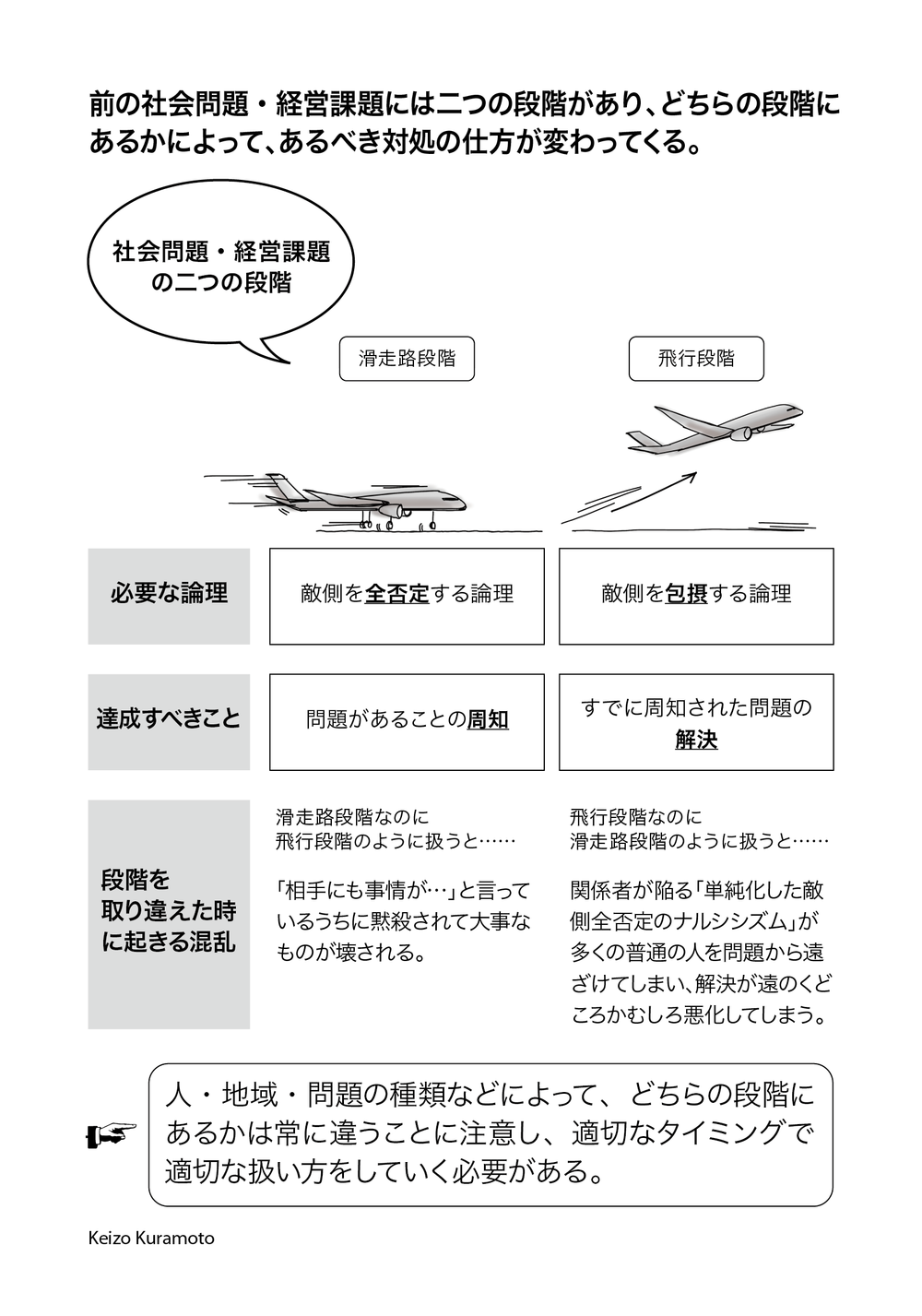郊外で小さな金属加工工場を営む鈴岡家は、夫の利雄と妻の章江、10歳の娘・蛍の3人で穏やかに暮らしていた。ある日、利雄の古い知り合いで、最近、服役を終えたばかりの八坂草太郎がやってくる。利雄は妻の章江に何の相談もなく彼に職を与え、自宅の空室を提供する。最初は不満だった妻はやがて礼儀正しい八坂に惹かれ、蛍もまた無邪気になついていき、八坂は一家になじんでいく。だが、彼はある時、一家にあまりにも残酷な事態を引き起こした末に唐突に姿を消す…。
ある一家に謎めいた男がやってきたことから起こる不条理な人間ドラマ「淵に立つ」。一見幸せな家族が、異質な闖入者によって、崩壊していくストーリーは、P.P.パゾリーニ監督の「テオレマ」を思い起こさせる。だが闖入者であるテレンス・スタンプがふっといなくなって終わる「テオレマ」と違い、本作で闖入者を演じる浅野忠信は物語の中盤で姿を消す。その後の展開にこそ、本作の凄みがあるのだ。鈴木夫婦は一見仲がよさそうだが実際は仕事の連絡以外に会話はなく、夫婦仲は冷え切っている。従順そうな娘も嘘をついている。夫の利雄は過去のある事件のことを妻に秘密にしている。八坂は一家を崩壊させるが、この家族はすでに壊れていたのだ。
中盤に起こる暴挙、八坂が姿を消して8年がたってからわかる真実とその後の衝撃。物語は、社会最小の単位である家族というつながりの常識を覆すものだ。家族を覆う欺瞞を暴力的にはぎとり、壮絶な不条理を突きつける。浅野忠信が静かに熱演する八坂が、真っ白なシャツで登場し、中盤に真っ赤なTシャツに着替えるのが象徴的だ。役者は皆、怪演に近い熱演だが、本作の本当の軸は妻を演じる筒井真理子だろう。肉体改造も含めて、この人の女優魂を見た。決して後味がいい作品ではない。いや、むしろ見たことを後悔させる恐れさえある。だが、ただ気持ちよくわかりやすいものだけが映画ではない。この衝撃はまぎれもなく観客に「映画とは何か」と問い詰める。カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員賞を受賞した、極めつけの問題作だ。
【70点】
(原題「淵に立つ」)
(日本・仏/深田晃司監督/浅野忠信、古舘寛治、筒井真理子、他)
(後味悪さ度:★★★★★)
この記事は、映画ライター渡まち子氏のブログ「映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子の映画評」2016年10月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。