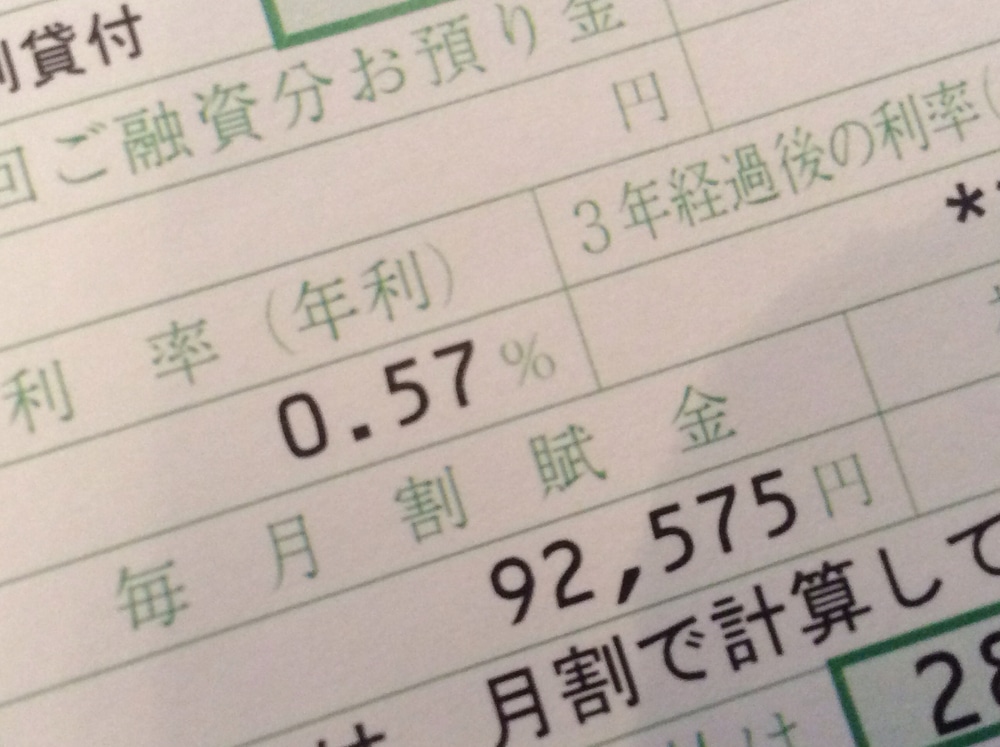マレーシアのクアラルンプール国際空港での「金正男氏暗殺事件」は実行犯が逮捕され、犯行に使用された毒薬もほぼ解明された。そして同事件の背後に暗殺計画を立案した存在は北の対外工作機関「偵察総局」と見てほぼ間違いない。もちろん、金ファミリー関係者の暗殺では金正恩労働党委員長の承諾がなくては不可能だから、異母兄殺しの最終的責任は正恩氏にあることはいうまでもないだろう。
ところで、日韓メディアを追っていると、正男氏を裏切り、そのフライト・スケジュールや動向を北側に流した人物について様々な憶測が流れている。「金正男氏暗殺事件」の焦点は、マレーシア警察の捜査当局から次第にメディア側の憶測へと移ってきた感がある。当然だ。北関連報道では憶測、推測こそ本来主流だからだ。北関連情報で「これこそ事実だ」と100%確信できる情報はほぼ皆無で、大部分は報道側の憶測、推測から成り立っているからだ。そして「最後の審判」は歴史に委ねられてきた。
そこで当方もその憶測と推測レースに参戦して、「金正男氏暗殺事件」の裏切り者は誰かを読者と共に考えていきたい。正男氏暗殺を立案する側にとって、最初に求められる情報は正男氏の動向だ。マレーシアの場合、正男氏のフライト情報だ。正男氏はインターネットでマカオまでの飛行チケットを予約しただろう。日頃利用してきた信頼できる旅行会社の知人を通じて電話一本で済ませたかもしれない。正男氏がフェイスブック上で自身のフライト情報を書き入れていたという情報が流れている。それが事実とすれば、北側が正男氏の動向を容易にキャッチできるだろう。この場合、正男氏自身の責任が大きい。危機管理ゼロと酷評されたとしても致し方がないだろう。
正男氏はさまざまなビジネスをしていたというからビジネスを通じて知り合った暗黒世界との繋がりも考えられる。正男氏との事業で大きな損失を受けたマフィアの逆襲だ。ただし、マフィアが正男氏の暗殺に使用された毒薬VXを入手できたとは考えにくい。国家レベルの組織と人材がなければVXを製造することは困難だからだ。使用者側に被害がなく、相手だけを殺害するというのは毒薬VXの製造の場合、高度な専門的な知識が不可欠となる。マフィアならマレーシアの正男氏が使うホテルを襲撃して、射殺する方が簡単だ。それとも、マファイが北側に正男氏の動向を売ったのかもしれない。
マレーシアには北朝鮮系企業のMKPグループが存在し、その責任者ハン・フニル社長の名前もメディアに上がっている。正男氏をよく知り同社長が平壌に正男氏のフライト情報を流した、というシナリオだ。知人の裏切りの場合、正男氏を欧州で世話する人物(このコラム欄では“謎の人物”O氏と紹介済み)も十分考えられる。フニル社長もO氏の場合も事実ならば、文字通り裏切り者だ。その動機は自身と家族の安全保証、利益の確保などさまざまな思惑が絡んでくる。なんらかの報復といった性格も忘れてはならないだろう。
ここにきて「愛人説」から「ボデイ―ガードの裏切り」まで、日本のメディアを飾っている。いずれも完全には無視できない。なんらかの行き違いや口が滑る、といった状況だって排除できない。ただし、マレーシア警察当局の情報によると、北側は犯行日(2月13日)の2週間から3週間前(1月下旬)に正男氏のフライト情報を獲得していたはずだ。
最後に、中国工作員の関与だ。中国当局は正男氏暗殺直後、対北石炭輸入を年内中止すると表明し、中国側の正男氏暗殺への不快の意思表示をした。そのタイミングの良さを考えると、北京の発表を素直に受け入れることはできない。
中国当局は金正恩氏といつまでも険悪関係を続けることはできない。正恩氏には北京側への不信が強い。そこで北京側は腰を上げて、正恩氏に和解へのシグナルとして正男氏のフライト情報を伝えたわけだ。例えば、マカオの正男氏の家族関係者は2月13日に父親の正男氏がマカオに戻ってくることを知っていたはずだ。正男氏のマカオ宅を盗聴する中国工作員は正男氏の家族関係者の会話からフライト情報を得ることもできる。
以上、まとめてみる
①正男氏の行きつけの旅行会社筋
②フェイスブックを通じて
③マレーシア在中の北ビジネスマン
④欧州の謎の人物
⑤愛人
⑥ボディーガード
⑦中国工作員の関与
⑧マカオの正男氏宅の盗聴工作から
もちろん、北側が自前の工作活動から正男氏の動向を掴んだ可能性も排除できない。その場合、裏切り者はいなかったということになる。いずれにしても、正男氏の動向を北側に提供した裏切り者がいたとすれば、彼は遅かれ早かれ金正恩氏から命が狙われるだろう。「裏切り者は必ず再び裏切る」ということを正恩氏は知っているはずだからだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2017年2月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。