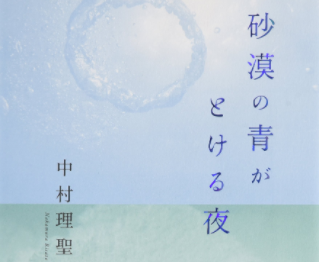&nsbp
世界が淡い滲みを手放してしまおうとする前に、再び「パッヘルベルのカノン」が奏でられる。また、世界は揺らぐ。「ぎこちない優しさ」という言葉がしっくりくる感じのたどたどしさで進む旋律を、もう一度妨げたのは準君だった。
「パッヘルベルのカノン」と聞いて脳裏の奥底に残っていた子どものころの記憶を思い出した。片田舎にあったわたしの実家の門を出て右に曲がって、緑の生い茂った住宅が並ぶゆるやかな下り坂を進んだ先にある、2階建ての幼なじみのおうちからピアノが鳴っていた。彼女のお母さんがピアノの先生をしていたからだ。いつも弾いていた曲がまさに「パッヘルベルのカノン」であることを音楽の授業で教わった。
優しい打鍵からゆるやかな旋律が奏でられる。その曲を聴きながら、幼なじみのおうちの先のお隣さんの駐車場に置いてある、生活協同組合のボックスを目指して歩いていたものだ。でも、もうあのころの景色と音色を聴くことも観ることもない。大人になることで過去の感覚を記憶として呼び覚ますことしかできなくなるのであれば、それはとっても残酷なことだと思う。
中村理聖『砂漠の青がとける夜』は第27回小説すばる新人賞の受賞作だ。この作品は、東京から京都へ帰省して姉のカフェの手伝いをしている瀬野美月(みつき)の物語。ある時、彼女はカフェにいた大人びた雰囲気を見せることも、あどけなさの残るところを見せることもいとわない少年、準君と出会った。彼は特殊な能力を宿していた。やがて二人は淡く優しく惹かれあい、美月と準君との対話から文字通りの言葉の虚しさを超えて、準君が実際に見聞きしたものとは異なった言葉や色彩の感覚をお互いに確認しあう日々を過ごすのであった。
作品序盤に、京都でカフェの手伝いをする以前に、東京で雑誌の編集者をしていた美月が20歳ほど年の離れた溝端さんという男性と不倫関係を築いている箇所がある。美月は彼から妻のことを聞きながら、中年男性として若い女性から感じとるものを聴きながら、そして、彼女じしん相手の振る舞いに戸惑いながら、対話を続けていた。だが、やがて彼の求愛の言葉すら感じられないほど愛しい思いは色あせていった。「愛してる」という言葉。その言葉自体に必ず響くものはあるのだろうか。美月はその言葉を気にかけていた。
私はためしに「愛してる」を一〇〇回、紙に書いてみたけれども、残ったのは手の疲労だけだった。
効き目が高まるどころか、物理的な痛みでしかなくなる現実。ずっと胸騒ぎはとまらないと思っていたのに、忘却してしまった彼方に抱くその感覚や記憶ははたしてなんだったんだろうか。自分がおろかだったと後悔するような虚しさにも感じ取れる。そんなわだかまりを打ち砕いたのは、冒頭に引用した準君との出会いであった。ある時、カフェにいた準君が不思議な経験について語り出す。
「美月お姉さんは、世界が一つじゃなくて、いくつも重なり合って見えたことって、ある?」
「え?」
「人の声と言葉が、僕の前ではいつも、本当にうるさいんだ」
レジから準君に目をやると、その瞳は潤んでいた。
「誰かが、何かを言うだろう。すると、その言葉の意味以外の声が、僕の耳元で響くんだ。そんで、その声の姿のようなものが見えるんだ」
「声の姿?」
「言葉の本当の色や形が見えるってことだよ。その人の言葉や声から、人のようなものが、人でない時もあるけど、ぼおっと立ち上がって、それが勝手に動き回るんだ」
わたしも聞いたことがある。言葉の本来の意味とは違った意味や感覚を抱くダブルバインドという認識だ。作中では準君がどのような幼少期を歩んできたのかはあまり分からない。でも、その時期、孤独であったり悲しさを抱いたりした経験によって、周りの人とは違う強い感性を生み出すことがある。わたし自身もある少女との出会いと彼女の告白からそのことを知った。
一方、作品中盤、井上さんや織田さんという男性との出会いや対話でさまざまなことを思いめぐらせるが、それが逆に美月と準君との対話を引き立たせてくれて、二人の対話からポリフォニック(多声的)な心象を抱かせてくれる。そして、作品終盤、美月は編集者をしていたころに書いた記事を集めたスクラップブックを姉に作ってもらっていたのだが、美月がそれに目をやり、書かれてある言葉をつぶやくと頭のなかに緑色と青色の世界が広がり始めたように感じた。準君に訊ねるとその色彩は怖くないという。なぜなら、緑色と青色は『愛してる』が一杯だからだと。ただただ繰り返す言葉とは違い、色あせないはっきりとした感覚を準君は感じ取っていた。
準君にしか聞こえない声が、彼の身体を通り抜け、そして再び私に還り、私の口から流れ出す。世界が二重になり、緑と青が夜の闇に降りてくる。目をつむるとあらゆる記憶が緑と青を帯びて蘇り、そして暗闇に還ってゆく。目を開けると、準君がいた。
夜の砂漠の青が空から舞い降りてくるような感覚。あるいは、目にやる言葉が緑や青といった色彩へと溶けてしまうようなことを確認しあうこと。それはお互いが言葉にならない愛しさを、心の深層で感じ取れる色合いによって描き出そうとしているのだとわたしは感じた。文字通りの言葉への虚しさを超えて、その関係性から奏でられる愛しさを二人で永遠に感じあえることを願いながら。
平尾あえる 会社員