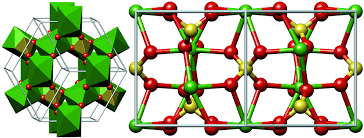世界的にも高い能力とされる空自の戦闘機。自衛隊の装備の前提は「専守防衛」だが…(空自サイト「F-15」より:編集部)
北朝鮮の弾道ミサイル開発の進展を受けて、自民党が「敵基地攻撃能力」の保有の検討を政府に提言した。この問題については、いくぶんかの議論の錯綜があるようだが、1950年代からの政府答弁の記録も明確なので、さすがに「違憲だ」というところまで言うのは、相当な少数派のようである。しかし大新聞などを見ると、「専守防衛」原則に反する、つまり日本は盾で米軍が槍だ、という原則に反する、といった論調が見られる。
米国依存を大前提にした仕組みを堅持すべきだ、という主張を、日本人が日本語で日本人同士だけで、どちらかというと日頃は米軍基地問題に批判的なメディアの主導で、進めていくのは、奇妙な光景ではある。が、これも日本的な風景ということだろう。
拙著『集団的自衛権の思想史』では、こうした日本的な風景は、「戦後日本の国体」が「表の憲法9条・裏の日米安保」という仕組みで神話化されていることによって発生している、と論じた。集団的自衛権の特異な理解も、そのような特異な「戦後日本の国体」のあり方を理解(無意識のうちに自明化)して初めて可能となる、と分析した。
拙著では、集団的自衛権は、沖縄返還を大きな政治目標とした佐藤栄作政権の政府関係者によって、1960年代末頃に国内向けに否定されるようになり、沖縄返還が達成された1972年に政府文書で初めて原則的に否定されたにすぎないものだ、と論じた。
「専守防衛」も似たような歴史を持つ概念である。「専守防衛」が日本の防衛政策の指針を表す概念とされるようになったのは、1970年に「防衛白書」第1号が公刊された際である。まさに佐藤栄作政権がニクソン政権を相手方として、沖縄返還交渉をまとめ上げていた時期であり、安保条約の自動延長を乗り切らなければならない時期であった。沖縄返還協定は1971年に調印されたのだが、日本はその代償として、「核持ち込み」や「基地自由使用(事前協議制度の骨抜き)」などの密約を交わしていた。
「専守防衛」論については、沖縄返還の直接的な帰結として、主張されるようになった、ということではない。ただ、「専守防衛」という概念を強調することによって確立しようとしていた「国家の体制」とは、日本の共産化を防ぐ、ベトナム戦争については支持はする、といった言説がアメリカに対して説得力を持った、当時の時代の雰囲気の中で確立が模索されていた「国家の体制」であったことには留意する必要がある。
「沖縄返還」は、「本土の沖縄化」であった、とする論者もいる。つまり今日までの残る地位協定の問題などが恒久制度化されたのは、占領下にあった沖縄が、抜本的な制度変革もないまま本土復帰したときであった、とする論者もいる。
集団的自衛権を違憲として確定させる政府の立場は、連日のようにベトナム爆撃のために沖縄基地を飛び立つ米軍機の行動を、日本政府が一切の責任を負うことを拒絶しながら、完全に黙認するという合意をあたえて、沖縄返還を果たしていくための政治的措置だった。そして「専守防衛」論も、全く同じ政治的含意を持つ概念だ。
本来、日本国憲法を待つまでもなく、国連憲章以降の国際法においては、憲章2条4項で武力行使が一般的に禁止されている。その例外は、自衛権と集団安全保障しかないので、国家の防衛行動の是非はすべて、「自衛権」の適用の合法性の問題に還元される。「敵基地攻撃」も、単なる先制攻撃であれば国際法で禁止されている武力行使に該当するが、武力行使が発生する蓋然性が明白であれば、自衛権で正当化される。
憲法9条1項が放棄しているのは「国際紛争を解決する手段として」の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」だけで、自衛権の行使は否定されていないとすれば、また9条2項の戦力不保持も1項で禁止されていない自衛権行使のための実力の保持は禁止していない、という政府解釈に立つのであれば、日本国憲法と敵基地攻撃との関係も、国際法と敵基地攻撃との関係と同じであるはずだ。したがって「専守防衛」とは、国際法から見ても憲法から見ても、その語義だけを単純に見ると、当然至極のことを言っているにすぎない。
この概念が日本の防衛政策の歴史の中で持つ意味を感じ取るためには、実際の歴史的経緯の文脈で、この概念が用いられるようになった様子を見ていかなければならない。
拙著では、集団的自衛権の是非を争う議論は、したがって少なくとも冷戦終焉後の日米同盟管理の観点で論じるのでなければ意味がない、と示唆した。「専守防衛」論も全く同じであろう。「憲法をよく読めば、日本は盾で米軍が槍だ、という原則がわかるはずだ」、といった、のんびりした見解では、いまだ冷戦ボケの思考と言われても仕方がない。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年4月3日の記事を転載させていただきました(タイトルは編集部改稿)。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。