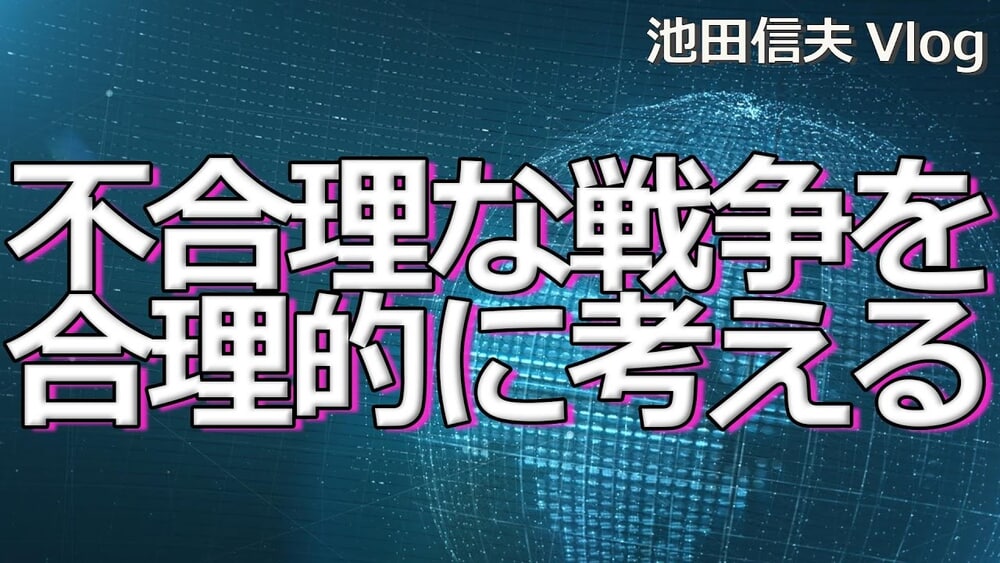画像は本記事紹介の書籍より。出版社許可にて掲載。
厚生労働省が発行する「平成26年患者調査」によれば、うつ病などの気分障害で、医療機関を受診している総患者数は111万6000人となり、平成8年の調査以降で過去最多を記録した。平成8年が43万4000人であることを考えれば、約2.6倍に増加したことになる。
企業にとってメンタルヘルス対策は喫緊の課題である。しかし、2年前に施行されたストレスチェックが、当初期待された効果をあげているとはいいにくい。企業の理解が深まらない場合、個人でのメンタルヘルス対策が必要になるだろう。
■「頑張る」ことの程度を知ることが大切
いま、注目されている書籍がある。『「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由(ワケ)』(あさ出版)だ。Twitterで30万リツイートを獲得し、NHK、毎日新聞、産経新聞、ハフィントンポストでも紹介された過労死マンガの書籍版である。
著者は、汐街コナ氏。デザイナー時代に過労自殺しかけた経験を描いた漫画が話題になり書籍化にいたった。監修・執筆は、精神科医・ゆうきゆう氏。自分の人生を大切にするための考え方が、わかりやすくまとめられている。
――今回は、汐街コナ氏に当時の状況を振り返ってもらった。
「私の話をします。うっかり電車に飛び込んで自殺しそうになるまで働いていたのかというと、理由はいくつかありますが『まだ大丈夫と思っていた』ことに尽きると思います。深夜残業なんて『あたり前』と思っていましたし決定的な体調変化もありませんでした。過労で死ぬなんて考えたこともありませんでした。」(汐街コナ氏)
「ところがうっかり自殺しかけて『判断力を失う』ことの恐さに気づきました。長時間労働は冷静な思考をむしばんでいきます。」(同)
――頑張りすぎる理由として多いのが「他のみんなも頑張っているから」というもの。汐街コナ氏が働いていた業種では、いつ寝ているかわからないような人、会社に寝袋持参の人、睡眠時間が短いことを自慢する人が少なくない。
「世の中には、200時間~300時間の残業ができる人がいます。努力なのか資質によるものかはわかりませんが、人には個体差があります。全員が全員同じことをできるはずがないのです。得意不得意や合う合わないがあるのです。無茶な努力は自分を疲弊させるだけです。」(汐街コナ氏)
「他人を基準にするのではなく、まずは自分の心と体の調子を確認しましょう。あとは、1ヶ月の残業時間80時間(厚労省の過労死基準)を一つの目安として考えてください。他の人がどうかではなく、また精神論で乗り越えられるようなものでもありません。」(同)
■好きな仕事だから頑張れという矛盾
――「好きな仕事だから頑張れ」と言う人がいる。弱音を口にすれば、「死ぬ気で頑張れ」とヒートアップする。経営者であれば、その職責からも24時間仕事のことを考えるのが当然ともいえよう。しかし、社員・スタッフは24時間働くことはできない。
私はバブル世代だが、当時はこのような風潮が強かった。熱が38度あっても解熱剤とドリンク剤を飲みながら仕事をするのが普通だったし「会社を休むこと」「有休・代休」の取得は「悪」とされ査定にマイナス影響を与えた。
「私の当時の肩書きはデザイナーですが、好きなことをしているから寝ないであたり前と考えている人が少なからずいました。『だから、どんなに辛くても逃げない』『だから、体調が悪くても休まない』『だから、限界を超えても努力する』。最初は前向きだった『だから』が思いがけず暗い道に連れていくこともあります。」(汐街コナ氏)
「その、『だから』はどこに向かっていますか。その先に夢や幸せはありますか。ちょっと注意してみてください。どこまで頑張ればいいのか、どこまでが『甘え』で、どこから『が頑張りすぎ』なのか。」(同)
――実は本書が圧倒的な効力を発揮するのは、マネジメントの局面ではないかと感じている。最近は、部下の指導に自信をもてない上司が多い。従来型のマネジメント本を読み漁り、マネジメント研修を受けても、スキルが上達することはない。理由は、テクニカルに終始しており、部下の気持ちに寄り添うものではないからだ。
本書は、読むことで部下の悩みや葛藤が手に取るように理解できる。どんな上司でも部下の気持ちに寄り添えるようになるだろう。現代社会で働くストレスを抱えるすべての人におすすめしたい。思わぬ形とはいえ「出版」の夢が叶った、汐街コナ氏の前途を祝したい。
参考書籍
『「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由(ワケ)』(あさ出版)
尾藤克之
コラムニスト
<アゴラ研究所からお知らせ>
―出版が仕事の幅を大きく広げる―
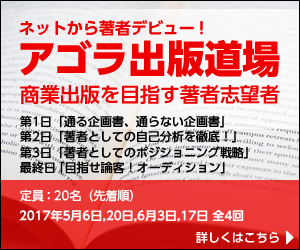
アゴラ出版道場、第2回は5月6日(土)に開講します(隔週土曜、全4回講義)。「今年こそ出版したい」という貴方の挑戦をお待ちしています。