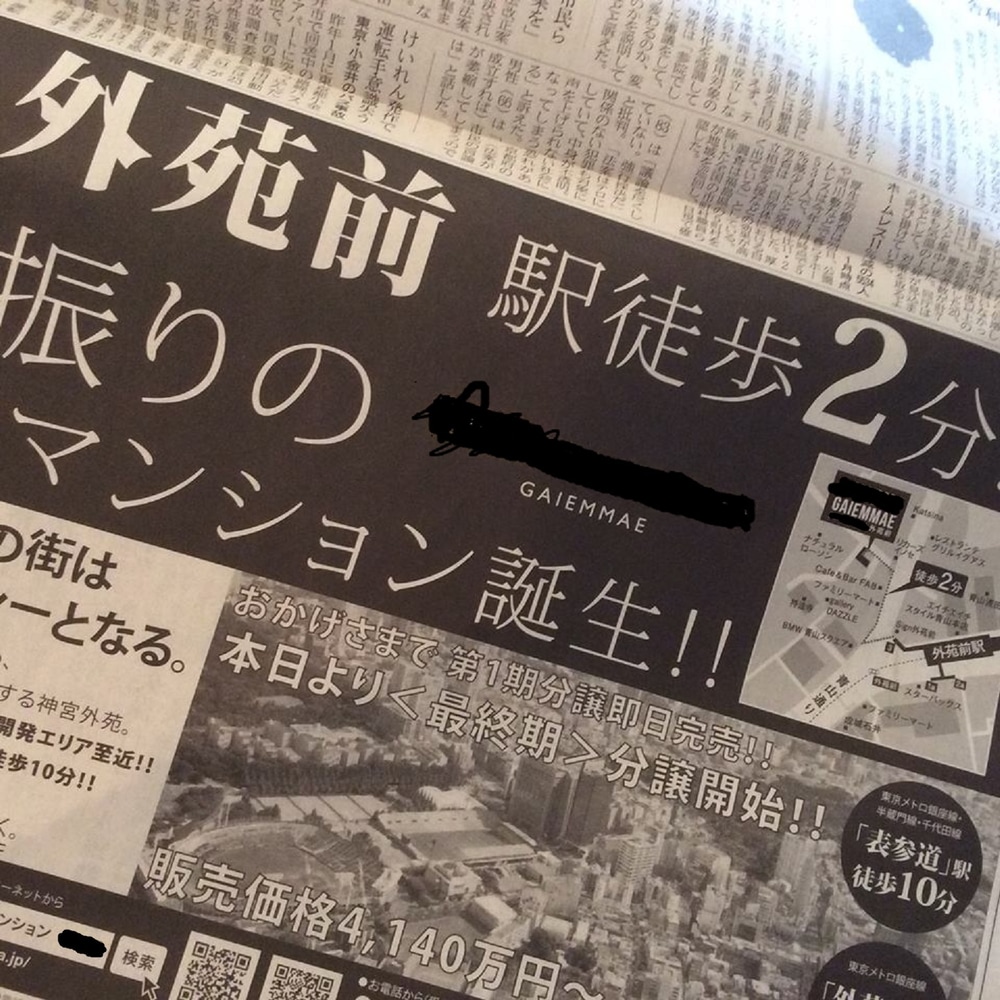昨日、日本の知り合いからメールが送られてきて、ある日本の新聞記事について感想を聞かれた。米ワシントンD.C. 郊外の名門、メリーランド大学での卒業式で、中国人女子留学生が行った代表スピーチの反響に関するものだ。スピーチの内容を要約すれば、彼女が米国のキャンパスで経験し、感銘を受けた表現の自由をたたえたもので、それを強調するため、自由を欠いた母国の言論空間をスモッグの息苦しさにたとえていた。

卒業スピーチをする中国人留学生
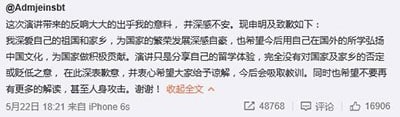
彼女がブログに公表した謝罪文。
「スピーチは自分の留学体験を披露しただけで、国や故郷を否定したり、見下したりするつもりは全くなかった」
同新聞記事は、彼女がネットで愛国世論の袋叩きに遭い、「国や故郷をおとしめる意図はなかった」と謝罪を迫られたうえ、中国外務省もコメントする事態に至ったことを紹介した。ネットで知識人らが彼女を擁護していることにも触れており、各方面へのバランスに配慮した跡がうかがえる。私のクラスでも近く学生が、国内世論の反響を分析した発表をする予定なので、その経緯を踏まえ、私の同記事に関する感想を送った。
まず、記者の仕事としてはC級である。机に座って、日本でも書ける内容だ。わざわざ現地に身を置く特派員のする仕事ではない。記者は暇に飽かせた「暇ネタ」として書いている。記者が思考し、探求するために不可欠な取材を経ていないから、何を訴えたいのか、メッセージが伝わってこない。うまくまとめようという小手先の気遣いしか感じられない。
どうして大学に行って、あるいは町中に出て、人々の生の声を聞こうとしないのか。記者であれば、規制下にある匿名のネット言論がいかに無責任で、偏っているか、十分すぎるほど理解しているはずだ。外務省のコメントも、外国人記者が聞いたからやむを得ず答えただけに過ぎない。記者が記事を作るため、意図的に問題を拡大させるよう仕組んだものだ。本当のところどはどうなのか。この疑問を発しない記者は、ジャーナリストとして失格である。
今回の話題を考える出発点は、中国人留学生の卒業スピーチである。中国の学生たちの多くはまず、中国人留学生、しかも女子が、あこがれの米国で、堂々と「総代」としてスピーチしたことに感動する。米国はダントツでトップの希望留学先で、習近平総書記からして、自分の子どもを米国の一流大学に送っている。米国の大学は中国人留学生であふれ、ハーバード大学も国別の学生数ではすでにカナダを抜いてトップだ。昨年、ハーバード大卒業式ではとうとう初めて中国人留学生がスピーカーに選ばれた。湖南省の農村出身の青年だ。
彼女の登壇は、その内容以前に、米中間の学生・学術交流がすでに強固な基盤を持っていることを象徴している。また、党幹部の米国留学研修もエリー養成として定着している。こうした脱政治の人的交流は紛れもなく、将来の安定した米中関係の構築において非常に大きな意味を持っている。この点を、特に「米中対立」「米中緊張」の図式でしか記事を書くことができない、多面的な思考的能力のない日本人記者はよく認識しておいた方がよい。
次にスピーチの内容だが、日本の同新聞記事は、彼女が触れた「米国の言論の自由」に対する賛否を取り上げている。だが、たいていの中国人であれば、中国に米国式の言論の自由がないことを十分知っている。また米国の自由が相対的なものであって、ある意味での不自由さからトランプ政権が誕生したことも、学生たちネット規制を乗り越えて研究済みだ。そもそも議論の余地がないテーマである。知識人が支持しているだけでなく、少なくとも、大学生のほぼ100%は同じ認識を持っている。
体制が自由であるかどうかということと、個人に自由な精神があるかどうかは別問題である。むしろ、自由を獲得してきた人間の歴史を振り返れば、自由が制限された環境でこそ、自由を希求し、自由の価値を重んじ、享受しようとするする精神が生まれ、育つ。彼女の発言は、不自由さを知る精神の表明であって、この点において、多くの中国人は共感するのだ。
現場を取材しないで、架空のサイバー空間を泳いでいると、自分が洗脳され、目が曇っていることに気づかない。ぬるま湯の中では、自由の精神も死んでしまう。だから彼女への批判は、ネットの不健全な民族主義勢力が意図的にスケープゴートを探し出したに過ぎないと考えなければならない。「自由」を持ち出すに値しない言論なのだ。
(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年5月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。