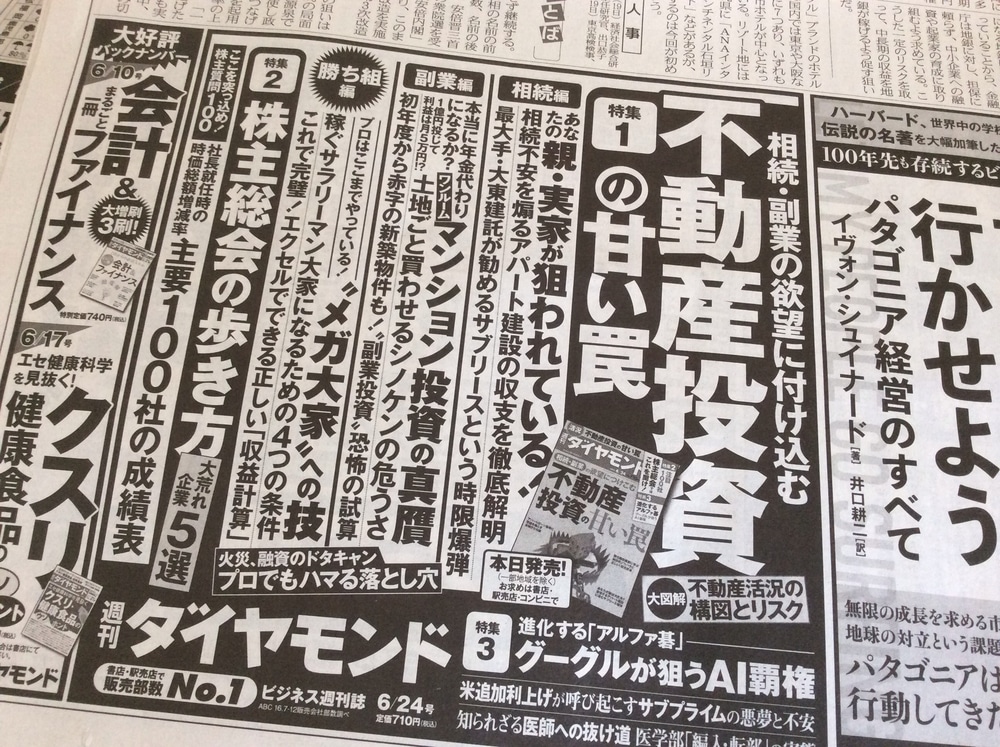冷戦時代に「保守/革新」と呼ばれていた左右対立は、いつのまにか「保守/リベラル」と名前を変えただけで、現在もなお終わりなき延長戦のようなことを続けている。「強行採決の暴挙に反対する!」云々と、時代がかった罵声も、あまりに見慣れたものになってしまった。国内スキャンダルであるかもしれないニュースの内容も、「一極支配を打破せよ!」という対立構図で、かき消されてしまう。
冷戦は良かった、と言う人はあまりいないだろう。だが冷戦時代の頃の日本は良かった、と思っている人があまりに多いことには、時々驚かされる。それが日本なのか。独特な社会的雰囲気が、21世紀の現代にも日本の独特な政治文化を維持し続けている。
10日ほど前、拙著『集団的自衛権の思想史:憲法九条と日米安保』に、読売・吉野作造賞を与えていただけることを、読売新聞と中央公論の紙上で発表していただいた。数多くの方々からお祝いの言葉をかけていただいた。時代の状況の中で書いた本であっただけに、お世話になった方々への感謝は募る。
同時に、何人かの方々からは、「いよいよ篠田さんにも人格攻撃が始まるんじゃないか」などと忠告めいたことを言ってくださった。「要するに篠田なんていうのは〇〇だ・・・」という一刀両断式の批評をされるよ、ということらしい。まあ、あくまでも私などに批評されるほどの価値があれば、という前提での話だが・・・。
私はかつて、朝日新聞社の「大佛次郎論壇賞」を『平和構築と法の支配』という国際政策研究で、「サントリー学芸賞」『「国家主権」という思想』という国際思想史研究でいただいたことがある。確かに、その時と比べると、私自身もあまり「お祝い」といった気分に100%浸れない気がしている。本の内容に同時代の論者への批判が含まれていることが一つ。自分の政策的立場が日本で推進されている気がしないのが一つ。
読売新聞のインタビュー記事では、「護憲派」でも「改憲派」でもない、いわば「国際派」だと書いておいてもらいたい、とお願いした。ご親切にも、そのように書いてもらった。しかし果たしてそれを読んでピンときた読者がいただろうか。自分で紙面を読んでみると、読売新聞に悪いことをしたような気がした。「その国際派っていう少数派閥、日本に何人くらいいるんですか?」、というようなものだろう。
先週15日、PKO協力法が25周年を迎えた。私は1993年にPKO協力法にもとづいてカンボジアの国連PKOに派遣してもらい、6週間ほど選挙関連業務にあたらせていただいたことがある。その後に書いた体験記は、ひそかに翌年の大宅壮一賞の候補作に入れていただいていた。その『日の丸とボランティア』という題名の(今は絶版となっている)書物の冒頭を、24歳の私は、次のような文章から始めた。
「僕は1968年に生まれた。その年の5月、パリでは学生たちの革命が起こった。・・・日本でも学生運動の嵐が吹き荒れ、翌年に安田講堂に籠城した者たちが東大の入試を中止させた。だがその一方で、日本はGNPで西側第二位の地位を獲得していた。・・・だから僕の属する世代は、戦前や戦後と格闘したことがないだけでなく、そうした格闘を見たこともない。自分が右にいるか左にいるかと考えたことがないだけでなく、右と左の対立図式を破壊しようとしたこともそこから逃げようとしたこともない。・・・僕が・・・大学を卒業したのは1991年だった。・・・」
思えば、24年後の今、あらためて自分自身の言葉について考えているような気がしている。あの当時、24年後の日本でも、ここまで硬直した左右対立が残存し続けていると言うことを予測できていたわけではない。
私が大学で日常的に接している学生たちは、冷戦後の世界だけしか知らない世代である。学部の学生であれば、もうすぐ21世紀生まればかりになり始める。冷戦期へのノスタルジアやその反発の言説を垂れ流しながら、彼らと接していいはずがない。
だがそうだとすれば、この国にとって、冷戦後の世界は、どんなものなのか。あらためて、問い直していかなければならないような気はしている。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年6月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。