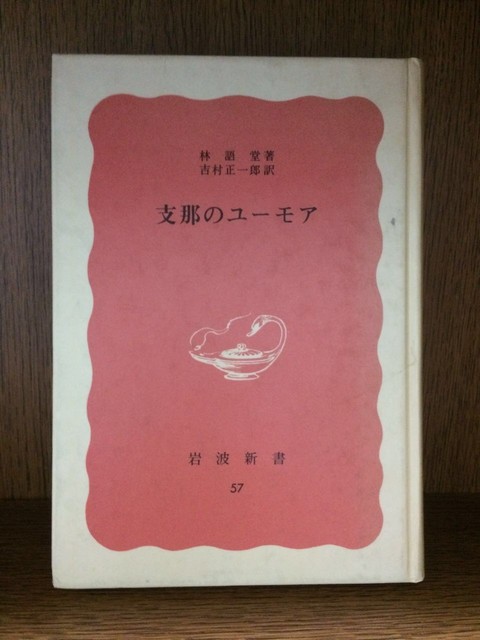来月の9月に日中国交正常化45周年を迎える。ある機関紙から「日中関係を考えるわたしの2冊」を挙げるよう求められた。中国にかかわる主要な書籍はみな中国の大学に持って行ってしまったので、記憶に残る本を選んだ。その際、東京に残っている書棚の本にも目を通したのだが、以前、古本屋で求めた林語堂(1895-1976)の『支那のユーモア』(岩波新書、1940)が目にとまった。彼が英字誌に連載したエッセイ『The Little Critic』(小さな批評)の邦訳で、タイトルはフランス語訳の本からとった。「支那」は当時の日本人が一般的な呼称として使っていたものだ。
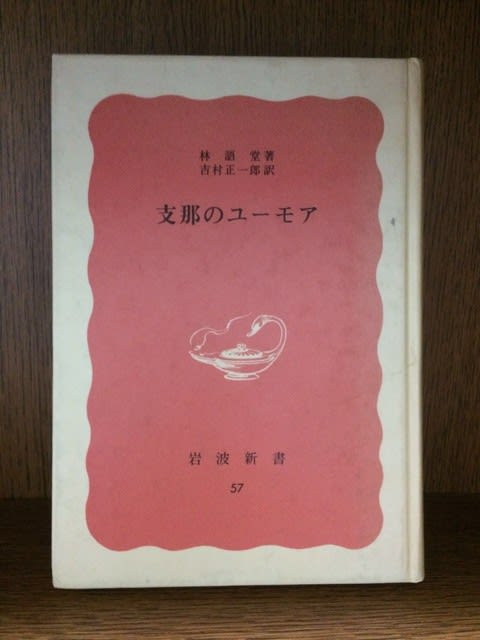 日中関係には縁遠い内容だったので「2冊」の中には入れなかったが、同書の中に「握手に就いて」の一文がある。林語堂は上海のセント・ジョーンズ大学とハーバード大学で学び、中英の翻訳や著述、教育に業績を残した。中国の古典と西洋文化の双方に通じた得難い人物だ。同文章はつぎの書き出しで始まる。
日中関係には縁遠い内容だったので「2冊」の中には入れなかったが、同書の中に「握手に就いて」の一文がある。林語堂は上海のセント・ジョーンズ大学とハーバード大学で学び、中英の翻訳や著述、教育に業績を残した。中国の古典と西洋文化の双方に通じた得難い人物だ。同文章はつぎの書き出しで始まる。
「東西文明の大きな相違の一つは、西洋人同士互に手を握り合ふのに反して吾々は自分で自分の手を握るといふところから来てゐる。あらゆる馬鹿げた西洋の風習の中でも私は握手ほど怪しからぬものはないと思ふ」
「自分で自分の手を握る」とは、、右手を上に、左手を下にして握りこぶしを作り、胸の上で上下に動かす拱手(きょうしゅ)という中国人の伝統的なあいさつを指している。彼が西洋人の握手を毛嫌いするのは、一つは衛生的な理由、もう一つは「美学的並びにロマネスクな理由」からだ。後者については明快で十分な説明がされているとは言えないのだが、意訳すれば次のようになるだろう。
握手を差し出した方は、相手がどう出るか判断できず、意のままにされる形になるので、平等の美学からすると受け入れがたい。相互の人間関係や感情が一点の肉体的接触に集約されるため、その裏にある感情や愛情を推し量らなければならいことになる。そんな面倒な気苦労はまっぴらごめんだ、というのだ。当代一流の皮肉屋によるユーモアなのだろう。
そんな林語堂が、握手のあいさつが当たり前となっている現在の中国を見たらどう言うだろうか。拱手は封建時代の名残として、近代の度重なる革命の荒波にさらわれ、ほとんど残っていない。今は男女もみな握手である。平等主義という意味では結構なことなのだろうが、なんでもかんでも伝統を捨て去り、借りてきた習慣を接ぎ木のように付け足すのもどうかと思う。拱手と一緒に敬語の多くも失われた。
私は、中国での初対面のあいさつではまず、日本式にお辞儀をする。そのうえで相手に求められれば握手に応じる。いくら長く暮らしても、抜けきれない習慣はある。初対面のあいさつはその重要な一つだ。相手に敬意を表するためにお辞儀はもっともしっくりいく。逆に、親しくなれば、久しぶりの再会でお辞儀をするのはいかにも仰々しく感じられ、他人行儀だ。この場合は、しっかり手を握り合う方がストレートに親愛の情を示しやすい。
だから、握手=平等、お辞儀=身分秩序、と簡単に色分けするのは適当でない。それぞれに伝える感情や意図があるので、時と場所に応じて使い分ければいいと思う。握手にはそれぞれが一個人として独立し、平等だという感じがあるため、逆に、お互いの立場に世間一般的な差がある場合は、ふさわしくないことも起きる。
以前、中国であるシンポジウムに参加した際、日本人の留学生からいきなり握手を求められ閉口したことがある。その学生は中国のネットを通じ、日本人としての様々な意見を公表し、ちょっとした人気があった。そこに思い上がりがあったのだろうか、親子ほど年齢差のある私に、初対面のあいさつとしていきなり手を差し出したのだ。私はそこで、「日本人であれば、日本の礼儀に従うべきだ」とたしなめた。考えてみれば、彼が私に示したマナーは、中国でもやはり受け入れられないものだ。
形にとらわれていると、心を忘れてしまう。郷に入れば郷に従えと言うのも一理あるが、やはり長年にわたり継承されてきた知恵は大切にしたい。私の周囲には形式に流れ、心を忘れている現象があまりにも多くはないか。
林語堂の「握手に就いて」は、次の言葉で締めくくられている。
「近代的な国際関係から教育制度にいたるまで、吾吾の周囲にあるものはおよそ人間の愚かしきことばかりである。人類はラヂオや無線電話を発明する知恵には事缺かないかも知れないが、戦争をやめるほどにはやつぱり賢くはないらしい。人類がほんたうに賢くなるのは一たい何時のことやら。私がいつも些細な馬鹿げたことは大目に見て一々文句を云はず、これまた一興と思つてゐる所以である」
彼の予言通り、その後、アジアは戦争の地となった。時流に流されず、些細なことにこだわることの大切さに思いを致し、私も握手とお辞儀の些事を、掘り返してみたくなった。(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年8月12日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。