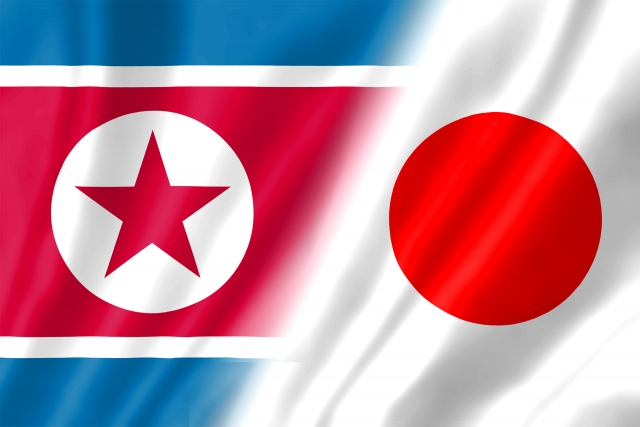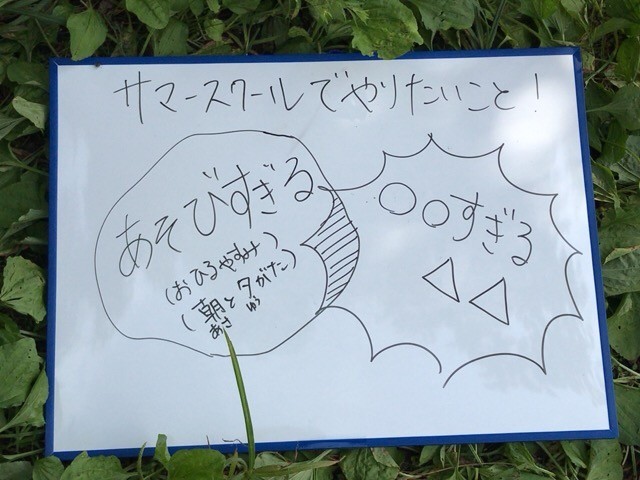東アジアで戦争が起こるリスクは、かつてなく高まった。北朝鮮がトランプ大統領を挑発し、先制攻撃すると示唆している。この場合はアメリカがただちに反撃し、その報復でソウルが「火の海」になるだろうが、日本も戦争に否応なく巻き込まれる。では「立憲主義」で戦争は止められるだろうか?
止められない、というのが本書の答である。明治憲法でも、第13条の「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」という規定で国防・外交大権は天皇にあると定め、それは内閣に委任されていた。「統帥権の独立」で軍が勝手に戦争を起こせるという解釈は誤りで、外交交渉も戦争のための財政措置も内閣の決定だった。
軍が立憲主義を踏み超えたきっかけは、満州事変を拡大した1931年の錦州爆撃だった。幣原外相はこれに強く反対し、金谷参謀総長に電話で不拡大方針を伝えた。その内容を幣原がスティムソン米国務長官に伝えたところ、これをスティムソンが記者会見で公表してしまった。幣原は「統帥権の干犯」として軍部の批判を浴び、第2次若槻内閣は総辞職した。
このあとも政府は軍部の対中膨張策に歯止めをかけようとしては失敗した。軍の予算は大蔵省が決めていたのだから、内閣が認めない限り日中戦争は不可能だったが、軍が既成事実を拡大すると内閣はそれを追認し、財政が逼迫すると国債を発行した。1932年の五・一五事件で政党内閣がなくなり、無産政党を先頭に軍に迎合する政党が勢力を拡大した。近衛内閣はそういう政党を糾合して、国民を戦争に動員したのだ。
ここから最終章で話は現代に飛び、著者は「安倍内閣は日中間の領土問題にアメリカを巻き込もうとしている」と批判するが、これはお門違いである。尖閣諸島は単なる日中の領土問題ではなく、東アジアにおける米中間の力のバランスを崩すから米軍が介入するのだ。
北朝鮮をめぐる問題でも、金正恩がグアムに向けて弾道ミサイルを発射すると、1930年代のような局地戦にはならない。戦争はただちに東アジア(あるいは西太平洋)に拡大するので、本書のような「巻き込まれ」論も「巻き込み」論も昔話である。だが戦争が始まったら、憲法で止められないことは同じだ。政治の役割は、戦争を防ぐために日米同盟の強化に手をつくすことである。