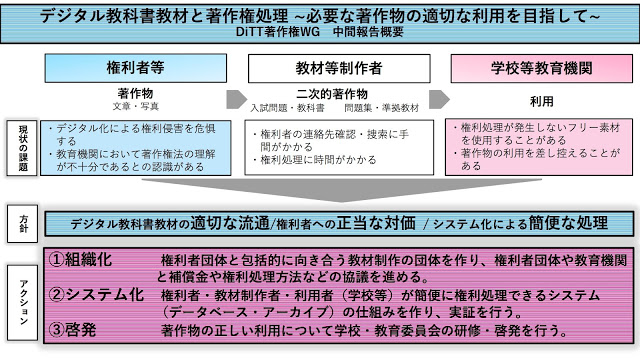父・習仲勲氏(右)、弟と写真に収まる習近平氏(Wikipedia:編集部)
習近平政権を語るときに忘れてはならないのが、父親である習仲勲(1913-2002)の存在だ。習近平政権を支えているのが、革命世代の二代目である「紅二代(ホン・アール・ダイ)の強力なバックアップであることは何度も触れた。毛沢東をリーダーとする革命世代は、建国を成し遂げた同士であると同時に、激烈な政治闘争によって戦った政敵でもある。非常に複雑な人間関係がある。
刺されたら刺し返す。相手の刀を相手自身に差し向ける。自分を守るために仲間を売る。有力者に取り入るため汚れ役を引き受ける。中国共産党史の裏側では、こんなマフィアまがいのことが繰り返された。毛沢東は約半世紀にわたる闘争を経て、個人崇拝の極致を生み出し、不動の座を築いた。
習近平政権はたかだか5年であるが、そこに至るまでに紅二代による準備期間がある。習近平に思想があるとすれば、「革命=紅い血」と「農民=黄色い土」の伝統を結び付け、政権の正統性を共産党の創設から、中華民族の誕生までに至る時間の座標軸に置いたことにある。だが、光明が大きければ、それが生む影も深くなる。影の部分を照らす役割を、習仲勲が残した遺徳が引き受けている。
党内で、権力欲に狂って失脚した薄熙来・元重慶市党委書記の父親、薄一波の悪口を言う者は多いが、習仲勲を悪く言う者はいない。この二人を比較すると、その子どもがたどった道がよくわかる。
薄一波は、保守派の元老として開明的な指導者の弾圧で先導的役割を果たした。それだけに政敵も多い。文化大革命後、失脚した多くの幹部を復権させたのは当時、党中央組織部長だった胡耀邦元総書記だ。薄一波も胡耀邦に救われた一人だが、民主化運動の処理を巡っては、なりふり構わず胡耀邦打倒に走り、「恩知らず」のレッテルを張られた。それに真っ向から対抗し、正々堂々声を上げて恩人である胡耀邦を守ろうとしたのが習仲勲である。このために習仲勲は鄧小平に排斥され、晩年の十数年は広東省深センで不遇の余生を送る。
さかのぼる1960年代、習仲勲は、毛沢東の側近として右派弾圧を担っていた康生の陰謀によって冤罪事件をでっちあげられ、「反党分子」のレッテルを貼られた。欠席裁判のまま解任され、文化大革命終了後、胡耀邦によって冤罪を晴らしてもらうまで16年間、北京での軟禁生活や河南省洛陽での工場労働を強いられたほか、陝西省で十数回にわたり見せしめの街頭引き回しを受けた。
習仲勲が尊敬を集めるのは、こうした政争の中にあっても、決してだれかを恨んだり、憎んだり、報復手段に訴えたりすることをせず、従容として運命を受け入れたところにある。恩を忘れず、人を裏切らず、人を巻き添えにせず、一人で濡れ衣を背負った。周囲には、「私は生涯、人を打倒したことがなく、真理を堅持し偽りを語ったことがない」と語り続けた。
彼の功績として伝えられるエピソードは、決して中国共産党史の大事件ではないが、庶民の生活と密接にかかわっている。1959年の建国10年を記念し、人民大会堂など大規模な建設プロジェクトが決まった際、国務院ビルの建設について、周恩来首相から意見を求められた習仲勲は「多くの庶民の家を立ち退かせることになる」と反対し、結局、見送られた。1958年、封建思想の象徴として城壁の取り壊し運動が全国規模で起きた際は、陝西省西安からの陳情を受け、旧長安の城壁保護を貫いた。習仲勲は「民衆の中にいれば安心だ」と言い続けた。
習仲勲の評を概括すれば、革命を率いた「紅い血」と中華文明を生んだ「黄土」の粋を体現した人物だと言える。習仲勲は過酷な政治的迫害を受けながらも党の事業に尽力し、農民の子として庶民の側に身を置き続けた。混じり気のない「紅」と、土とほこりにまみれた「黄」に彩られた人物である。多数の党幹部がどんなに横暴で、腐っていようとも、党の屋台骨を支えるために、「紅」と「黄」の正統を語り継がなければならない。習仲勲はそのためになくてはならない人物の一人である。
左右いずれの政治的立場からも、さらに知識人から庶民レベルに至るまで、習仲勲の評価に異論を挟む声はない。その高潔な人格は、全国民に受け入れられている。習近平が背負っている父親の遺徳は、彼の政治基盤の核心をなすものである。習近平がそれに背けば、父親に恩を感じている人々の反発はとてつもなく大きいだろう。
(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年10月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。