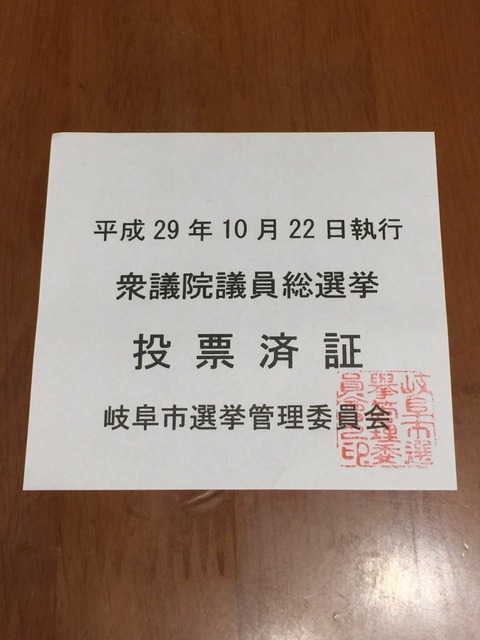AI(人工知能)に習近平政権の指導部を分析させたとしたら、習近平の赴任地である「福建」や「浙江」に加え、必ずや「陝西」のキーワードを引き出すだろう。紅二代としての習近平政権を見るうえで、欠かすことのできないのが、重要な革命根拠地であると同時に、習ファミリーのふるさとである陝西地方のネットワークだ。周辺の甘粛・青海を関連キーワードとして加えてもよい。

趙楽際氏(新華社サイトより:編集部)
王岐山の後任として反腐敗キャンペーンを引き継ぐ重責には、陝西出身で、青海・陝西省での長い実績がある趙楽際が抜擢された。習ファミリーにとっては同郷のよしみとなる。同じく政治局入りした張又侠・中央軍事委副主席も陝西の同郷だ。父親の張宗遜大将は、後述する長征にも参加した軍幹部で、張又侠は習近平と同様、紅二代を代表する人物だ。
前回取り上げた栗戦書も5年間、陝西省で党組織部長や西安市党委書記などを歴任した。政治局入りした李希・遼寧省党委書記は甘粛省出身で、甘粛と陝西でキャリア積んだ。これだけ陝西関連人脈が広がっていることは、単なる偶然とは思えない。
陝西省は、日本では古都西安に代表される唐文化、シルクロードの歴史によって親しまれるが、中国では文明が発祥した中原地区の一部、あるいは中国共産党の革命聖地・延安の所在地である。
習近平の父親、習仲勲元副首相(1913~2002)は陝西省富平県の貧しい農家に生まれた。習一族は清朝末、飢饉に見舞われた河南省南陽を逃れ、黄河の流れをさかのぼるようにして富平県にたどり着いた。習近平によっては曾祖父の代だ。習仲勲が自らを「農民の子」と呼び、習近平が「私は黄土の子だ」と一文を書いたのは、こうした生い立ちを物語る。
習仲勲は、陝西・甘粛・青海を含む革命根拠地の建設に尽力したが、この根拠地は、毛沢東率いる共産党軍が国民党の攻撃から逃れ、1万2500キロを踏破した長征の終着点である。陝西の革命根拠地がなければ、共産党が建国を成し遂げる偉業もなし得なかったことは、毛沢東が「陝北は二つの点だ。一つは着地点、一つは出発点」と認めている。
だが、その歴史的事実を突き詰めれば、「長征と陝西根拠地のどちらが正統なのか?どちらが中心なのか?」という問いかけを生み、毛沢東の正統に対する評価を揺るがせる。長征を迎えた同省指導者で習仲勲の盟友、高崗・元西北局書記は1954年、党内分裂を企てたと批判され自殺した。習仲勲もそれから12年後、康生が仕掛けた小説『劉子丹』事件で冤罪をを着せられ、「高崗の事件を覆し、陝西・甘粛辺区を革命の中心にしようとした」と指弾された。
以後、陝西人脈は正当な名誉回復を受けることなく、陝西の革命根拠地建設にかかわった人々や家族は無念の思いを抱いてきた。習仲勲も遺言として、陝西人の名誉回復を託した。それが習近平政権の誕生後、徐々に光が当てられるようになっている。
現地を歩けば変化が一目でわかる。3年前、陝西省延安にオープンした中国共産党西北局革命記念館には、習仲勲が毛沢東と机を挟んで向き合うモニュメントが置かれ、入り口に並ぶ指導者の銅像には高崗も堂々と入っている。
こうした変化の延長として、今回の指導部人事を読み込むことができる。習近平自身も2015年の春節、妻の彭麗媛を引率し、文化大革命時代に農作業を体験した陝西省の農家を視察した。そこは彼が15歳から7年間、山に横穴を掘った「ヤオトン(窯洞)」と呼ばれる横穴式住居で、同世代の農民と同居した思い出の地である。引退した王岐山もまた、陝西省の近くの農村で過ごし、習近平とは限られた本を貸し借りした仲だった。
陝西人脈の復活は、中原文化の復興を象徴し、革命聖地の名誉回復を通じた共産党革命史の見直しである。いずれも、伝統回帰を重んじる習近平の思想に合致している。
(続)
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年10月26日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。