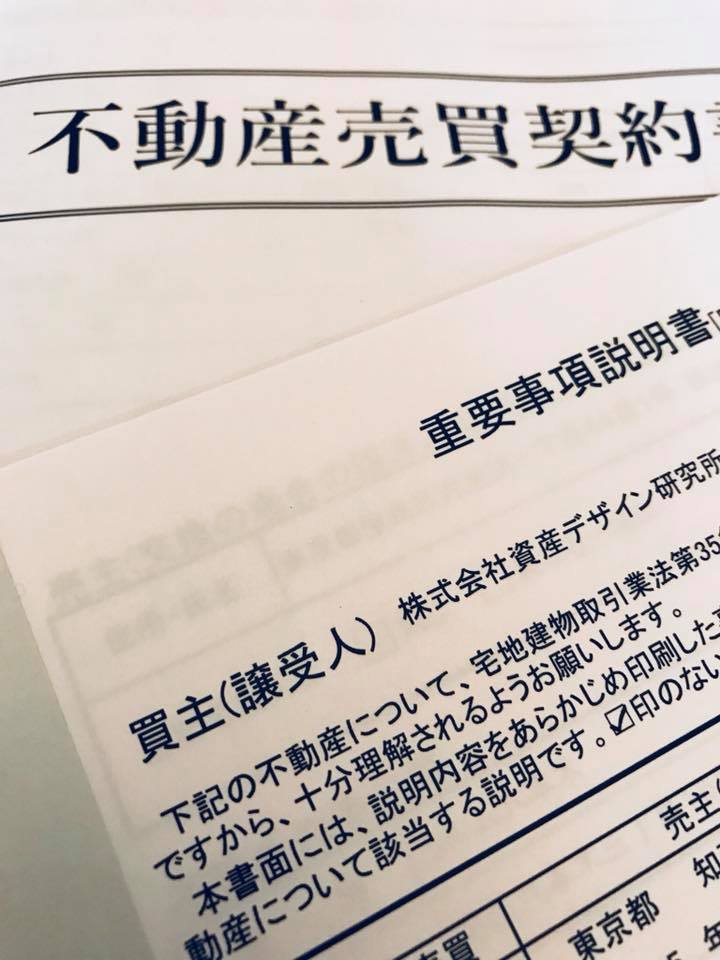ソウルの国際会議に登壇する筆者(Facebookより:編集部)
ソウルで国際会議に出席した。平和構築・紛争予防をテーマに、国際機関や各国政府の職員が議論する会議(主催:韓国政府・ハマーショルド財団・国連平和構築支援事務所)に、セッションの座長役で、招いてもらった。セッションでは、アフガニスタン、スリランカなども話したが、東ティモール出身の「G7+」という国際的プラットフォームの方が、東ティモールとインドネシアの関係改善を題材に、「最後は、政治的意思と国益判断だ」、と強調していたのが、耳に残った。(参考・筆者Facebook)

ソウルの反米デモ(筆者Facebook:編集部)
たまたまトランプ大統領の訪韓と重なったので、会議後には、反米デモと親米デモと警察部隊が渦巻いているのを見ることができた。北朝鮮との国境から約40キロ、国民性もあると思うが、韓国の人々は、熱い。アメリカ軍とともに朝鮮戦争、そしてベトナム戦争を戦った経験を持つ。アメリカとの関係は、複雑だ。
もちろん、日本も、負けず劣らず、アメリカとの関係は複雑である。ただちょっと違った様子で、複雑である。一緒に戦争を戦ったという記憶は、ない。ただ、敵味方に分かれて、片方が降伏して占領されるまで、戦い続けた。「東西の強者の代表」が「新世界出現のために避け難き運命」(大川周明)として 、「決勝戦」としての「最終戦争」(石原莞爾)を戦ったのが、日本にとっての「太平洋戦争」だった。
戊辰戦争から約10年後の東北に生まれた吉野作造は、「戦後」を語ることなく、東大教授となり、普遍主義的な立憲主義を標榜していた。彼が「英雄」と呼んだウッドロー・ウィルソンは、幼少期に南北戦争を体験したヴァージニア州出身者だ。やはり「戦後」を語ることなく、プリンストン大学教授となり、普遍主義的な立憲主義を標榜した。
太平洋戦争後の日本人は、吉野やウィルソンと、少し似ている。ただし、もう少し、屈折している。普遍主義を掲げて、あらためて勝者と対峙したい。ただし、その敵国が起草した憲法が基礎になるとしたら、敵国の文化にそって、敵国の影響下で、普遍主義を語らなければならない。そこで日本の憲法は世界に唯一で他に類例がないガラパゴスであるということにしたうえで、ガラパゴスであることこそが世界最先端だ、という理論を作り上げた。
日本の政治を、「リベラル」「保守」といった概念で見ても、理解できるはずがない。冷戦が終わったとき、「革新」政党のアイデンティティを消し去る必要があったが、代替案がなかったので、外国から概念を借りてきただけだった。「私はリベラルで保守だ」とか「本当のリベラルとは何か」、などと語り合うのは、修辞的な効果や学問的な話としては意味があるが、日本の政党政治の分析としては、的外れだ。
結局、政権与党の自民党を一極とし、冷戦時代から反対の立場を貫いている共産党をもう一方の極とし、その他の野党を順に並べていくには、アメリカとの距離、を尺度にするのが、一番わかりやすい。親米か、反米か。この尺度で、自民党から共産党までの政党を並べていけば、だいたい間違いない。
現代日本に、反米の右翼政党、がないのは、あまりにも戦前復古主義に見えるからだろう。戦前の日本では、最後の大政翼賛会の地点で、反米右翼で政治が一元化された。反米右翼で一元化されたから、泥沼の戦争に陥ったのだ。
したがって左翼的な反米主義者が、右翼的な反米主義者と大同団結するのは、全く不思議なことではない。国粋主義的と言われるか否かの相違は、反米主義的であるか否かの相違ほどには、現代日本では、重要ではないのだろう。
集団的自衛権を合憲とするか違憲とするかに関する立場の相違も、結局、アメリカに対するスタンスに還元される。何度か指摘したように、憲法学者の集団的自衛権違憲論を支えているのも、結局は、「アメリカなんかを信用するんですか?」という情緒的訴えである。(拙稿「長谷部恭男教授の「立憲主義」は、集団的自衛権の違憲性を説明しない」)
アメリカを信用するくらいであれば、どこまでも個別的自衛権を拡大解釈していったほうが、まだマシなのだろう。絶対に認めてはならないのは、日本国憲法に登場する「平和を愛する諸国民」にアメリカを含めることなのだろう。もし含めてしまったら、「われらの安全と生存」が、アメリカへの「信頼」によって成立するものになってしまう・・・。
アメリカ人が作った憲法を、反米主義の武器に作り替えるという壮大なプロジェクトこそが、集団的自衛権違憲論と合憲論の背後に控えているものだ。(拙稿「憲法学者とは、なぜ反米主義者のことなのか」)
確かに、冷戦時代後期には、談合政治的な操作で、実態としての集団的自衛と、建前としての集団的自衛権違憲論が併存するようになった。しかしそのような一時的な措置が、冷戦終焉と共に賞味期限を迎えたのは、やむを得ない事だったのだ。(現代ビジネス寄稿「立憲民主党が肝心の「立憲主義」を勘違いしてどうする 」)
ところが実際の日本の国家体制は、アメリカとの同盟関係を大前提にして構築され、運用されてきている。したがって反米主義を貫くことは、革命家になることに等しい。そこで、アメリカを批判する「理想主義」を忘れてはいけないと訴えながら、アメリカと適当に仲良くなる「現実主義」も持ち合わせています、といったくらいの玉虫色の態度を正当化することに四苦八苦することになる。
団塊の世代が去った後の時代も見据えながら、日本の野党が生き残っていくためには、「反米主義の理想を掲げながらも、現実的にアメリカとやっていくことくらいはする」、といった生半可な態度から、「親米主義の姿勢を基本にしながら、建設的にアメリカと付き合っていく」、という態度への切り替えを決断することが必要だろう。
そのような決断さえすれば、内政面の政策に特化した政策論争で、差異や優位を見せることもできるようになる。もちろん、冷戦終焉後、四半世紀にわたって、野党はそのような決断を避け続けてきた。おそらく、今後も避け続けるのだろう。しかし結局それによって選択肢を狭められ、不利益を被るのは、次世代の日本人たちである。
編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年11月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。