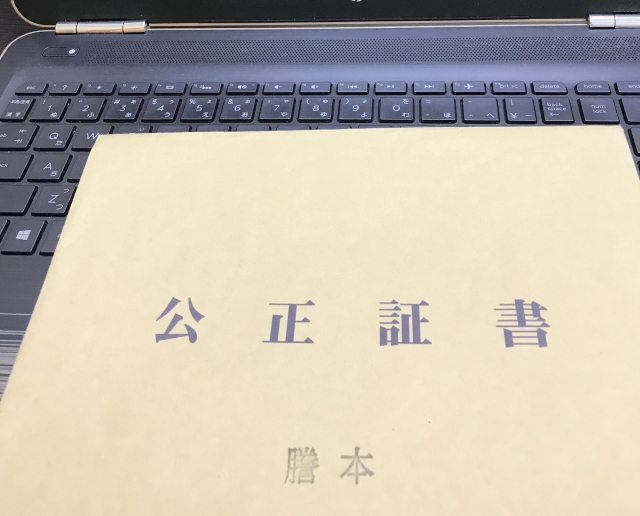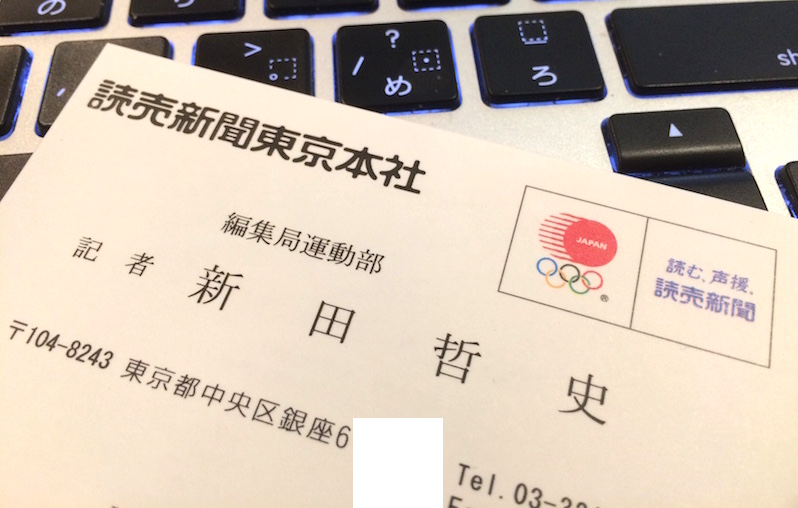
今週のはじめに、東洋経済オンラインで神田昌典氏が企業のブログ発信などでジャーナリストを雇うことを推奨するコラムが掲載されていた。本来ならすぐにでも感想を書きたかったのだが、多忙で執筆時間が取れなかった。ただ、あまり手放しで評価できるものではない。どこかザラついたものも抱えているのが本音だ。
というのも、「あぁやっと日本でもそういう選択肢が知られる段階になってきたのか」というポジティブな感想と同時に、「なにを神田さんはいまさらこんなことを言っていて、どのレベルのマーケッターに向けて発信しているのやら」というネガティブな違和感もあるからだ。未読の方も多いと思うので、リンクは貼っておく。
企業が自社の広報に元記者を雇用するという方策というのは、いわゆる「ブランドジャーナリズム」と同じことだと思う。神田氏がこの言葉を使わないのは、情弱マーケッターにレベルを合わせたのか、あるいは何かほかの意図があったのかもしれないが、いずれにせよ、神田昌典という有名マーケッターが、東洋経済オンラインという2億PVを誇る最大手ビジネスネットメディアで書いてきたというのは、「ブランドジャーナリズム」という方策の社会的認知度が、イノベーター理論でいうところの「キャズム越え」をしようとしているのだろうか。
しかし、「神田氏が情弱マーケッターにレベルを合わせた」的な嫌味ぽい表現を私があえて使ったのは理由がある。だって、ブランドジャーナリズムなんて概念は、私が新聞社を辞めた頃の7年前の時点ですでにアメリカのマーケティング業界ではすでに認知されていて、日本でも先端的なマーケッターの間で「海の向こうの最新動向」として、ちらほら取りざたされ始めていた。アメリカでは2000年代に入った時点で、バタバタと地方紙がつぶれたり、リストラが進んだりしていて転職市場に放り出された元記者たちがPR会社や企業のマーケティング部門に転身する動きが加速していた。
日本でブランドジャーナリズムの認知度が高まってきた経緯を漠然と振り返ると、朝日新聞随一の欧米のメディア事情通、平和博記者のブログで2014年には取り上げられている。
〝ブランドジャーナリズム〟はジャーナリズムの脅威か?(新聞紙学的)
日本ではそのブログが掲載された頃から、ネットマーケティング好きの企業を中心に、オウンドメディア立ち上げブームや、コンテンツマーケティングのブームが、アメリカの周回遅れでやってきた。
ところが、まさに神田氏が指摘するところの優良なコンテンツを作れる人間がいそうで意外にいない。もちろん、新聞や出版でコンテンツを作っていた人間が、企業の論理でウェブ向けのコンテンツを作ることの適性が必ずあるとは言えない。しかし、日本でもブランドジャーナリズム的アプローチで情報発信していくのなら、やはりニュース感覚、社会や時代を展望するマクロ視点を身につけた人材はある程度、そろえる価値はあろう。
しかし国情が違いすぎる。アメリカと違って、日本の新聞社は意外にしぶとかった。佐々木俊尚がかつての著書のタイトルで煽ったように2011年に新聞社は崩壊しなかった。それどころか毎日新聞も産経新聞もずっと前から「つぶれる」と言われてきたわりに、2017年現在、生きながらえている。
ここ2年ほどはNewsPicksやら、バズフィードやらネットのジャーナリズムでの「受け皿」も出てきたが、企業のマーケティングや広報部門への転身となると、日経やブルームバーグなどの経済メディアからの移籍はたまに見受けられるものの、一般紙のたとえば社会部などから転身組は難しいだろう。
それに、神田氏の記事をツイートしたところ、「(いまの)企業の広報スタッフで十分対応できるのでは」というツッコミもあった。メディア露出をしょっちゅう実現させている敏腕広報は、時流を読み、マスコミ向けにコンテンツをアレンジする力はしっかりしている。ビジネススキル未知数の元記者をわざわざ雇うリスクを取るほど、投資意欲のある奇特な企業は希少だ。
30代半ばで新聞社を辞めた後、人生棒に振りかけるような経験もしてきた身としては、そうした日本のマスコミ、特に新聞業界の人材の硬直性や、ポータブルスキルの欠落、受け入れ先の企業が極小という現実が厳然とある中で、神田氏のコラムは、ずいぶんと「浮世離れ」しているようにしか思えなかった。
まあ、もちろんジャーナリズムとビジネスの人材が活発に交流する「回転ドア社会」になるのが理想だが、この国では無理じゃないか。
このモヤモヤとした読後感、なんとかしてくれ、という週末である。