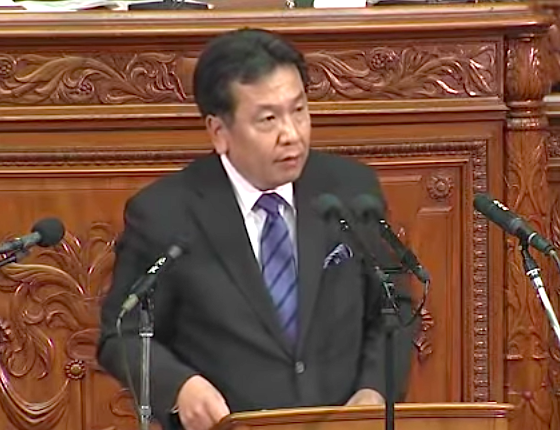夏の甲子園は折り返しを迎えたが、きのう(12日)の第3試合、済美が史上初のサヨナラ満塁本塁打で星陵を下した試合は、その劇的な展開が脚光を浴びる中、炎天下の試合中に足がつり、熱中症と疑われる選手が続出していたようだ。

済美・山口投手(NHKニュースより)
その中でも唖然としたのが、済美の山口直哉投手の「活躍」だ。愛媛大会の5試合、甲子園の1回戦もすべて1人で投げ抜き、この試合も炎天下の中を延長13回、184球の完投勝利。しかも打者として死球を受けた痛みもこらえていたというから、もはや登板過多、酷使という競技上の問題を超えて「虐待」である。ところがメディアも、主催の朝日新聞はともかく、NHKですら「エースの気迫」などと美談に仕立ててしまう始末の悪さで、甲子園の裏事情は決して社会問題にならない。
本書でも冒頭でMLBのスカウトが甲子園を取り巻く環境を「児童虐待」と指摘しているが、そうした高校野球の「不都合な真実」をあぶりだし、夏の甲子園が100回目を迎えたのを機に、根本的に問い直そうとしている。
特筆すべきは、徹底した現場視点だ。憧れの甲子園に出てきたときには山なりのボールを投げるのがやっとだった投手の話を深堀りする「玉砕球児」の実相であったり、年端もゆかぬ球児を「スター報道」が増長させて自分を見失わせて転落させた事例であったり…。
選手、指導者本人、高野連関係者らを徹底的に取材し、甲子園を取り巻く病理のリアルを炙り出しているが、朝日新聞やスポーツ紙、NHKなどの「甲子園報道」ではほとんどわからない問題点、当事者たちの本音、試行錯誤の裏にある苦悩がよくわかる。
たとえば、投手の酷使について本書では、“大谷二世”とも言われたエース投手を故障させ、その反省から複数投手制を敷いた盛岡大付属の事例をクローズアップしている。複数投手制を敷くのは誰も思いつく方策ではあるが、負ければ終わりのトーナメント制が主体のいまの高校野球において、二番手以下の投手がモノになるまで、負けるリスクを大きくする中での育成というのは、指導者に極めてタフな決断と勇気を強いるのが現実だ。
盛岡大付属の監督は自分の中の「勝ちたいエゴ」とも格闘したが、それだけでなく「エースが多く登板するもの」という高校野球界独特の空気とも向き合わなければならなかったあたり、合理性より伝統にばかり目がくらむ「甲子園の病」の深刻さをあらためて痛感させられる。
投手の酷使問題についていえば、本書でも紹介されている米国流の球数制限を導入するといった「仕組み」から変えないと現場の指導者が適応するインセンティブはできまい。
著者は本書について「指導者や高校野球を支える関係者の方々を批判し、つるし上げるためのものではない」と強調している。華やかな夏の風物詩の陰に隠れていた真実を丹念に積み上げてみせることで問題提起をし、当事者たちの自発的な改革を望んでいるようだ。
しかし、かつて読売新聞時代に高野連批判をして抗議文を送りつけられたこともある私からすれば、そのようなシナリオには悲観的だ。「甲子園」の存在は、1世紀の伝統であまりに巨大化し、しがらみができあがっているために、野球界、マスコミなどの当事者だけでの改革はもはや不可能だろう。
丹念に当事者を追いかけ、声を集めた点では出色の書であり、「甲子園」を取り巻く問題をとらえる上で視座を据えるには非常に参考になる。ただし、改革に向けた具体的な提言がいまひとつ欲しかった。著者と私の意見は異なるかもしれないが、Vlogでも述べたように、スポーツ庁や政権与党による介入がないと抜本的な改革へと動くのは難しいのではないか。