対話不能な人たちとの対話
ネトウヨもパヨクも、ネットスラングであり侮蔑語(になってしまった)。ために本書は双方の当事者からは「相手を【ネトウヨ/パヨク】と呼ぶのはいいが、自分たちを【パヨク/ネトウヨ】と呼ぶのはけしからん、という印象を持たれるかもしれない。が、そう感じた人にこそ読んでもらいたい。保守・リベラルとネトウヨ・パヨクを分けるものは何か? 自分も保守やリベラルのつもりで、実際にはネトウヨやパヨクサイドに陥っていないか?
筆者の物江氏は元電力会社勤務、福島出身であるがゆえに、原発・放射能論争において不毛で結論ありきの論調に直面した。その「対話不能なケースに直面した」経験も盛り込まれており、ネット現象の分析にとどまらない点がユニークである。
これまでのネトウヨ・パヨク分析本は、筆者の立ち位置が初めから「【ネトウヨ/パヨク】を批判する側」に置かれていることが多く、そもそも対話の可能性を探るものではなく、中には単なるディスりもあった。
しかし本書はそのような手法を取らず、ネットが深める左右の溝と、ネットであれ直であれ「意見が全く異なる人と議論することの難しさ」、それを乗り越える重要性を淡々と指摘する。この物江氏の姿勢と、「もっと過激にディスってくださいよ」と依頼しなかった(?)新潮新書の担当者には、誠意を感じる。廃刊騒ぎとなった『新潮45』についても取り上げている点は特に注目である。
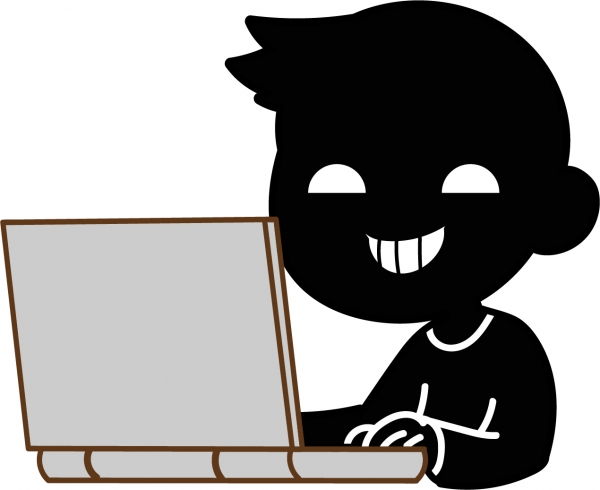
ねぎ/イラストAC(編集部)
「ディスり」から「対話」へ
「対話が大事」……などと書くと「当り前だろ」という話になりかねないが、このご時世、「右も左も似た者同士」などと書くだけで双方から「冷笑主義」「中立ぶるな」「高みの見物はすっこんでろ」などと総スカンになりかねない状況下で、「当り前」を説くのも大変なのだ。特に商業出版ともなればなおさら。そこを淡々と実体験を交えながらも煽らずに書ききっている点は左右から、あるいはどちらでもない人から評価されてほしいところ。
動機の核は第5章の「『真っ白な中高生』に迫るネットの主張」だろう。現在、福島県内で塾を経営している筆者が実際に接する中高生の間で「基礎知識がないままネットに染まって、ネトウヨやパヨクに一直線」となっているケースを見ているからだ。アクセス数が稼げるから、いいねやRTが増えるから(あるいは「これが真実だ!!」)と極端な物言いをする大人たちを、若者たちがトレースしてしまう。筆者は「まだ数は少ないが」とするものの、この傾向を「喫緊の課題」であるとしている。
これはネット以前、あるいはネットよりも本を読む中年以降の人間にも実は起きているのではないか。例えば大きな歴史の流れは実はざっくりとしか把握できていない一方で、「歴史認識問題」にかかわる事象についてだけはテンプレの物言いを身に着けていて、論争っぽいものを行える。これは自分(梶井)にも言えることで、保守側に多いかもしれない。
あるいは左派でも安倍総理の資質に疑問をつけるようなエピソードにはやたら詳しく、ネットで流布されている「安倍の失態なのに報じられない」ネタを指摘することで、さも反権力であるかのポーズをとる。それがなぜ報じられないかの「事実」は、権力批判のためには二の次になる。まともな出版社からの出版物にもこういうものはある。
そこにあるのは「相手をディスり、自分が正しいという結論を声高に言いたい」という感情だけで、民主主義の基本である「対話」などというものは存在しない。
本書は絶望的なまでの「対話不可能な事例」をとりあげつつ、それでも「対話を」と述べ、「(事例としてあげられるネトウヨ・パヨクの方々が)いたからこそ本書が出た」とお礼まで述べる。そんな筆者の姿勢には達観したものすら感じるが、「話の出来ないヤバめの人とも、それでも対話を試みる」ことで無力感や徒労感に襲われる経験を積んでこそ、この境地に至ることが可能なのかもしれない。
読者としては、そんな筆者の過程を追体験し、「開かれた対話の重要性」を知り、改めて対話の重要性を説く「旗」を掲げてくれたことに賛意を示したい。














