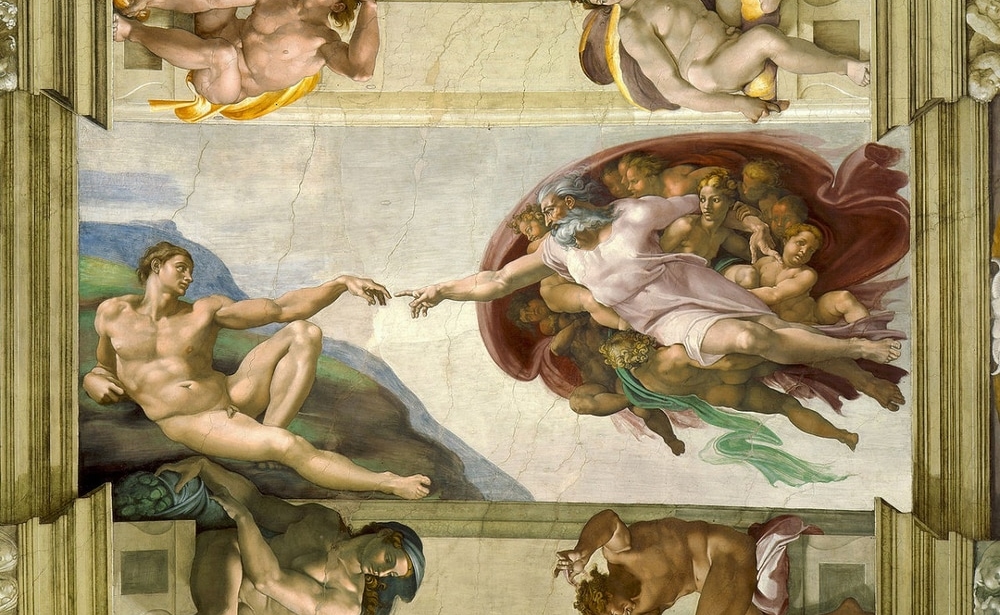スイスといえば、日本人が1度は訪問したい国の一つといわれてきた。アルプスの小国は永世中立国であり、直接民主制の国家で欧州連合(EU)にも加盟せず、独自の政治、社会体制を構築してきた。重要な法案は国民投票で決定してきた。同国では昔から世界から多くの難民、移民が避難してきた。避難民を収容する国としても知られている。レーニンはスイスに逃れ、革命を計画し、カルヴィンもスイスに逃れ、宗教改革を起こした。
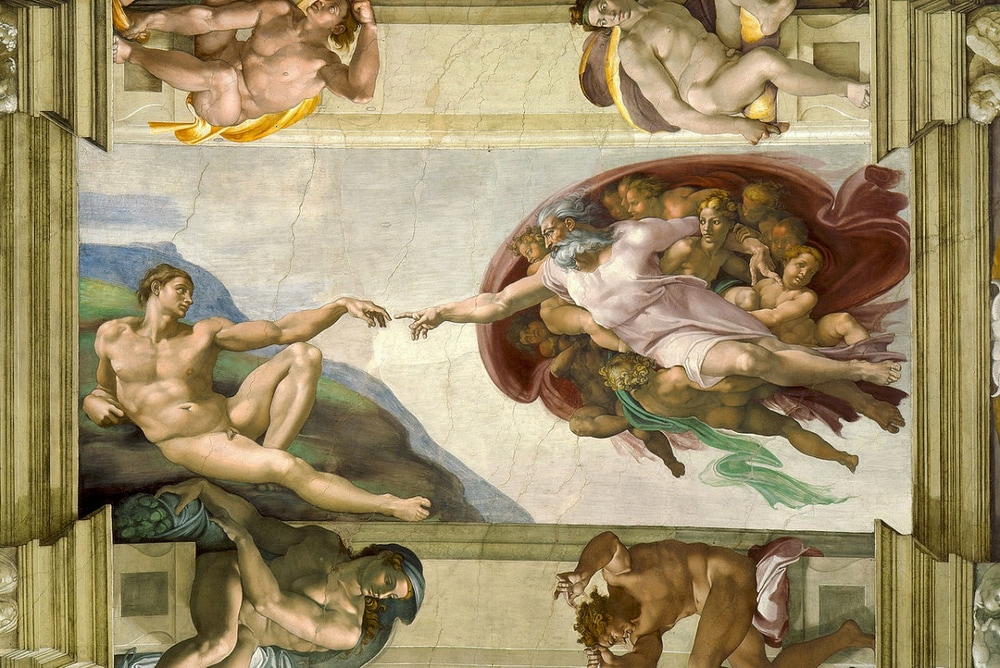
しかし、ここにきてイスラム系移民の増加を受け、2009年11月29日、世界に先駆けてイスラム寺院のミナレット(塔)建設を禁止すべきかを問う国民投票を実施し、賛成57%でミナレット建設禁止を可決した国だ。スイスの外国人率は約25%だ。スイス国民はリベラルな傾向がある一方、非常に伝統を重視する保守的国民性を有している(「ミナレット建設禁止可決の影響」2009年12月1日参考)。
ところで、大多数の欧州諸国が既に決定したが、スイスがまだ明確にしていない重要なテーマがある。同性婚の是非だ。そのスイスで今月26日、同性婚合法化に関する国民投票が実施される。ちなみに、世界でオランダが2001年4月1日、同性婚を最初に合法化した。その後、欧州を中心に同性婚を認知する国が増え、現在、29カ国が同性婚を認めている。欧州で同性愛者の婚姻を認めていない国は4カ国しかない。イタリア、ギリシャ、リヒテンシュタイン、そしてスイスだ。
スイス連邦議会は昨年12月、同性婚合法化を盛り込んだ民法典改正案「全ての人に結婚の自由を」を可決した。同案が可決された直後、保守系政党「スイス民主同盟」(EDU/UDF)や「スイス国民党」らを中心に反対の声が上がり、国民投票が実施される運びとなった経緯がある。
反対派は、「同性婚合法化は、社会的・政治的な裂け目を生み、男性と女性の間に築かれる永続的な関係としての婚姻の歴史的な定義を覆す」と指摘し、「婚姻は男性と女性の自然な関係であり、今後も保護されるべきである」(反対派の「国民投票委員会」の声明文)と強調。また、同性婚合法化が認められれば、女性への生殖補助医療の道が開かれ、近い将来代理出産の道が認められるようになる懸念が出てくる。法案はレスビアンには子供を持てることを認めているが、ゲイにはその道がないことから、「法改正で新たな男女差別を生み出す危険性がある」というわけだ(スイス公共放送協会のウェブサイト「スイスインフォ」日本語版)。
同国の同性婚支持グループ「ピンク・クロス」が2020年実施した世論調査では、国民の約80%が同性婚合法化を支持している。同性婚の合法化に賛成する人々は、「同性愛者への不平等な差別をなくし、全てのカップルが同じ権利と義務を持つことが出来る」と主張する。
なお、宗教界では、スイス福音教会連盟が2019年11月、同性婚の合法化に賛成を表明した。一方、スイスのカトリック教会司教会議やスイス福音ネットワークは同性婚合法化に反対している。
スイスでも同性婚合法化問題では支持者が声を大に叫ぶ一方、反対者が自身の信念を表明することに躊躇する傾向が見られる。同性婚反対と言えば、“ポリティカル・コレクトネス”に反するといわれるからだ。だから、同性婚問題では多数派が口を閉じる一方、少数派は自身の権利を声高く叫ぶ、といった状況がスイスでも見られるわけだ。
スイスではこれまで同性愛のカップルは「パートナーシップ制度」に登録できる。毎年約700組がこの制度を利用している。2018年以降は同性カップルでもパートナーの子供を養子縁組できる。
以下は、当方が同性婚問題で考えている内容だ。
民主主義では社会の多数派が政策や路線を決めていくが、性的少数派問題では多数派は沈黙し、少数派の声が傾聴されてきた。その結果、少数派はあたかも多数派のように受け取られ、ジェンダー問題で主導権を奪っていった。多数派は、寛容、連帯、多様性といった響きのいい言葉に酔いしれず、少数派と議論を交わすべきだろう。男女の性差は決して差別ではなく、生物的な相違だ。そして各性には生来与えられた機能、役割が備えられている。「位置」は社会によって多少の違いが出てくるとしても各性の「価値」は変わらない。同性婚は“与えられた条件”を放棄するものだ(ただし、生まれた時からホルモンの関係など生物学的な問題から性が明確ではないケースは少数だが存在することは事実だ)。
同性婚の合法化問題を契機に、“与えられた性”に対して真摯に考えていくべきではないか。同性婚支持者は性をあたかも神のように自身で選択できると考えているが、現実はそうではない。繰り返すが、与えられたものだ。性を自身の好みで選択できるものではない。性的少数派への社会的差別は可能な限り除去しなければならないが、同性婚を男女間の異性婚と同列する法改正には反対せざるを得ない(「初めにジェンダーがあったのか?」2021年5月10日参考)。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2021年9月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。