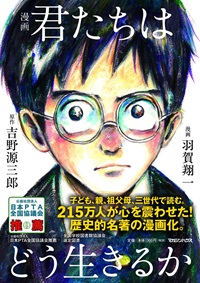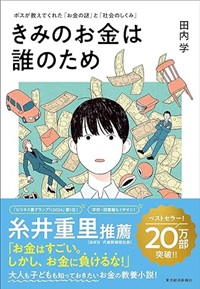昨年、吉野源三郎氏の『君たちはどう生きるか?』が脚光を浴び、宮崎駿氏バージョンの原作とは違う同名映画「君たちはどう生きるか?」も話題になりました。哲学を身近に感じた方もいらっしゃるでしょう。

bymuratdeniz/iStock
最近『君のお金は誰のため』(田内学著)が売れており、2024年ビジネス書グランプリで総合1位を獲得しました。正直、書籍の内容は「君たちはどう生きるか?」の構成をうまく流用したお金版の哲学書であります。田内氏はゴールドマンサックスで16年勤務したのち、著作業に転身した異色のキャリアの持ち主でお金をとことん知っている人が書いた書として面白い着眼点を持っています。
「お金自体に価値はない」「お金で解決できる問題はない」「みんなでお金を貯めても意味はない」の3つがキーでそれを物語風に展開しています。
人はなぜお金に執着するのか、これについて著者の指摘も含め、考えてみたいと思います。
突然話は脱線しますが、私は以前の会社で不動産開発本部と秘書に在籍していた時に社費で散々飲み食いをさせて頂きました。その前の現場勤務時代もかなりひどくてザル勘定ではないかと思ったほど当時の私の上司は私を飲み屋に連れまわしました。私自身にその癖がうつり、時たま、現場所長行きつけのスナックやバーに一人で行き、ボトルの酒を勝手に飲んだりと好き勝手やり放題でした。
秘書になるとグルメ三昧が待っていました。当時Leading hotels of the worldという世界最高峰のホテルリストに会社で所有するホテルがいくつも入っていたこともあり、ボスと出張すればホテルのベストオブベストの食事を、他の出張先ではその街の圧倒的NO1のレストランに通い続けたのです。
結果どうなったかといえば秘書を終えた時、「うまいものはもういい」と思うようになったのです。つまり完全飽和状態。それ以降、今日に至るまでたまにはおいしいものを食べるけどメリハリの中で時々それに接すればよいという気持ちに変わったのです。
私はお金も同じだと思っています。散々お金を使っても自分の人生を振り返った時、何をそんなに使ったのだろうと思うはずです。女性なら新しいバッグやアクセサリーが欲しいでしょう。「かわいいー!」という表現だと思いますが、いつまでも「かわいいー」というわけにはいかないのです。そもそもガキから紳士淑女に成長するには知性や品格といったエレガントさが備わる必要があり、一定年齢になれば人間の重みこそその人の価値になります。着る服や身に着けるアクセサリーはその気品から放たれるものなのです。つまりそれが備わっていなければ借り物の衣装でしかないのです。
私がお金を使う時に思うのは「果たしてこのお金を払う価値があるのか?」であります。例えば先日、友人と有名すし店に行きました。お任せコース2時間半。払った金額はお酒代にチップを入れて日本円で一人4万円弱。また行くか、といえば「ない」と思います。なぜかといえばおまかせにするなら店主が見せるドラマが必要なのです。ところが人材不足なのか、大将はカウンターにいる時間より裏にこもってしまい、寿司屋のカウンターに誰もいない時間が長く、客は手持無沙汰になるのです。そして10分に1貫程度の割で握ってもらっても間が抜けて空虚になってしまったのです。
私がお金を使ってよかったと思うのはみんなで楽しい食事ができた時です。あるいは良書に出会ったとき、自分に投資をしたときなどでしょうか?つまりお金を使う以上それが1000円だろうが1万円だろうが、安い高いの問題ではなく、バリューがあるのかが最大のポイントだと思います。時々私が「飛行機はエコノミーで十分。理由は低血圧なので飛行機で酒が一切飲めないし、どうせ寝ずに本を読み続けているだけだから」というのは私の価値観なのです。先日富豪なのに私と全く同じ考えの方に出会い、消費の価値感を改めて感じたところです。
ではお前は最後、死ぬときにそのカネ、どうするのだ、と聞かれたら私は「君のお金は誰のため」の著書と同じ、社会還元しかないと考えています。事業の大半は私の価値観を継承してくれる人にバトンを渡しながらも社会還元の仕組みもそこにはめ込みます。同時に個人のお金もある程度は余るでしょうから今から少しずつそのプランをどう実行すべきか考えているところです。Bottom Line は墓場に札束は持っていけない点です。ならばベストな形でそれを有効活用するのが良いですよね。つまり世の高齢者が相続税対策で血眼になる話をよく聞きますが、私は全く違う観点でアプローチしたいと思います。
ウォーレンバフェット氏は世界で最高の富豪の一人ですが、ハンバーガーを食べ、コークを飲むのが好きなのです。氏の価値観はそこにあるのです。もちろん、毎日それが食事ではないはずです。だけどバフェット氏はハンバーガーを手にする時が一番幸せな食事なのだろうと私は察しています。私も結局はそこを目指すことになるのでしょう。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2024年5月26日の記事より転載させていただきました。