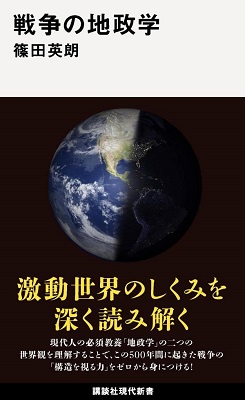国際刑事裁判所(ICC)による逮捕状請求と、国際司法裁判所(ICJ)の軍事行動停止命令で、ハマスの行動とともに、イスラエルの軍事行動の違法性が、権威的に認定されてきている。ネタニヤフ政権が、全く聞く耳を持たず、軍事行動を続けているだけに、イスラエルの横暴ぶりが目立っている。
イスラエルを擁護し続けているアメリカは、引きずり込まれる形で、窮地に陥っている。もっともジョンソン下院議長に代表される保守派は、聖書を引用してイスラエルを擁護する立場を正当化し、ICCに「制裁」を科す準備を始めるなど、言いたい放題である。

2023年9月 同首相SNSより
この状況に困惑しているのが、日本のようなアメリカの同盟国だ。どう見ても、アメリカの立場に説得力がない。しかし同盟国を公然と批判できない。日本外交は、深刻なジレンマに陥っている。
このような状況は、過去にも何度かあったかもしれない。冷戦中のベトナム戦争や、2003年イラク戦争などは、その典型例だろう。だが今回のイスラエルのガザでの軍事行動は、悪質度のレベルがさらにいっそう深刻だ。アメリカ国内で、学生運動が燃え上がっているのは、その深刻度の反映だ。
このジレンマは、今後も日本外交にまとわりつき続けるだろう。アメリカ社会は、人種問題や経済格差などで、疲弊している。アメリカの国際地位も、相対的な低下が顕著だ。これは同盟国を合算した「西側」全体に言えることである。BRICSの経済力が、G7を凌駕する時代が到来している。今までと同じ考えでは、旧来の「先進国」が行き詰まりを見せていくのは、必至だと言える。日本外交は、長期的に、この構造的なジレンマと、付き合っていかなければならないのだ。
ICCとICJがイスラエルとアメリカに批判的な内容の動きを示したことによって、アメリカが推進している「ルールに基づく秩序」を揶揄する言説が、世界的に流通している。「国際法」を守る気がないのに、他国に「ルールに基づく秩序」なるものを説教するアメリカの立場を揶揄する言説だ。アメリカが押し付ける「ルール」とは、アメリカに都合のいい「二重基準」のことであり、「国際法」を遵守する「法の支配」とは真逆だ、と感じられてしまっている。
"I think it's very dangerous what the U.S. is pushing for." UN Special Rapporteur Francesca Albanese joined @mehdirhasan to discuss attempts to undermine the ICC and replace international law with a "rules-based order." Watch the full episode here: https://t.co/LJ1swDbdem pic.twitter.com/wJVLg3q1T1
— Zeteo (@zeteo_news) May 22, 2024
元イスラエル政府スポークスマンは、「ICJが(戦闘中止命令で)『ルールに基づく秩序』を破壊した」とSNSに投稿した。
I’m not sure the reputation of the ICJ survives this. Complete breakdown of a cornerstone of the international rules-based order. https://t.co/KF3AYOBdJ4
— Eylon Levy (@EylonALevy) May 24, 2024
他方、数多くの人たちが「ルールに基づく秩序」なるものは、アメリカが「ルール(rule:支配する)秩序」のことでしかないことが白日の下にさらされた、と感想を述べている。
Every day since October, we have been reminded that when the Biden team says "Rules Based Order," they mean an order in which the US rules.
Not an order based on rules.
We will see it again if the US opposes the ICJ ruling against Israel today.
— Trita Parsi (@tparsi) May 24, 2024
If the US doesn’t abide by the International Court of Justice ruling it will be clear that our interpretation of the “rules-based order” is “We make the rules & we order you to follow them.”
— James J. Zogby (@jjz1600) May 24, 2024
The cornerstone of the rules-based order being “impunity for the West and its allies” https://t.co/oBUmM2UKQu
— Alonso Gurmendi (@Alonso_GD) May 24, 2024
日本政府は、G7広島サミットを開催した際には、国際社会に「法の支配」を強調していた。岸田首相自らも、繰り返し「法の支配」の概念を参照していた。
上川外相は、外相就任間もない頃に、わざわざハーグに行ってICJ(国際司法裁判所)とICC(国際刑事裁判所)を訪問したうえで、「国際社会における「#法の支配」の強化のための外交を包括的に進めていきます」と述べた。
だがこれは、アメリカと一緒になってロシアを非難し続けることが、日本外交の基本姿勢になった、と認識していただけの時代のことだ。昨年10月以降のイスラエルのガザにおける軍事行動に国際的な非難が集まり、アメリカだけがそれを擁護する構図がはっきりしてくると、次第に、日本政府関係者は「法の支配」を口走らなくなってきた。代わりに使うようになってきたのが、アメリカ仕込みの「ルールに基づく国際秩序」だ。


アメリカが同席する経済問題の会合に出席する場合、アメリカの意向をくんで中国をけん制して太平洋島しょ国と会議を開く場合などは、「国際社会における法の支配」よりも「ルールに基づく国際秩序」の方が都合がいい。
おそらくは、岸田首相も上川外相も、当初は、それはほんの少しの言葉遣いの調整の話で、基本的には「国際社会における法の支配」よりも「ルールに基づく国際秩序」も同じ意味だ、と信じていたかもしれず、今でも問われれば、そう答えるだろう。
しかし、もはやそんな危機意識のない認識が許される情勢ではない。両者は、はっきりと分裂している。
もし日本だけは、両者が一致する世界を求め続ける、というのであれば、精緻で体系的な説明を用意したうえで、相当な外交努力を払っていかなければならない。
実際は、全く逆に、ICCに対しても、ICJに対しても、イスラエルが関わる案件となると、日本政府関係者は途端に歯切れが悪くなり、とにかく曖昧な態度に終始し続けようと頑なになる。
「それは仕方のないことなのだ」という確信が、政府関係者の間で共有されているのだろう。「ウクライナとロシアの話をするときには、どこまでも歯切れよく行きますから、そこだけ見ておいてください、中東の話になったときには、もちろんそういうわけにはいきません」という態度をとることに、総意があるようだ。
国際政治の現実は厳しい。簡単に言語明瞭な態度だけを取り続けるわけにはいかない、と言えば、一般論としては、そうだろう。しかし「とにかく曖昧にさえしていれば、必ず上手くいく」という考えに、何か根拠があるわけではない。先行きの見通しがつかないので、やむをえず曖昧な態度に終始しているだけだ。それなのに、根拠のない正当化を図るのは、長期的には、むしろ非常に危険なことであるかもしれない。そもそもこの態度は、日本の国益を精緻に計算したうえで選択したものであるというよりは、イスラエルに泥沼に引きずり込まれているアメリカに気を遣ってお付き合いをしていることの結果でしかない。本当に合理的計算に基づいた妥当性がある態度なのかについては、大きな疑いの余地がある。
果たして日本はこの「二重基準」の態度で、長期的に外交を上手く進めていくことができるのか?
■