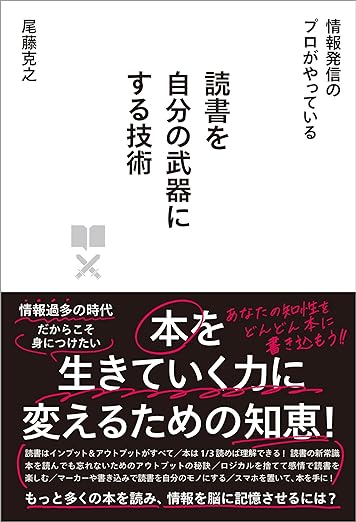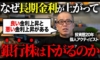「業績不振により整理解雇をおこなう」、「転職した社員が顧客情報を持ち出して懲戒解雇になった」など、解雇に関するニュースをよく見かけます。解雇に関する情報をどこまで正しく理解していますか。

PonyWang/iStock
解雇の要件を考える
解雇は「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇(懲戒免職)」の3つに分類されます。懲戒解雇(懲戒免職)はこのうち即時に雇用契約を切られ、予告手当や退職金もないなど、労働者にとっては死刑宣告を突き付けられたのと同じぐらい重い処分です。
これに当てはまらないケースとして「諭旨解雇」があります。懲戒解雇に相当するか、それよりも少し軽い非行・違法行為があった場合に、懲戒解雇を回避するために温情的に自主的に退職を求めるものだからです。「依願退職」という扱いになるのが一般的です。
懲戒解雇は労働者にとって死刑判決ですが、諭旨解雇は使用者と労働者の双方が話し合い解雇処分を受け入れるものです。諭旨解雇であれば退職金が支払われることがありますが、懲戒解雇の場合、退職金は支給されません(退職金規程の記載が必要)。
公務員は雇用保険に加入しないため、失業保険の給付もありません。懲戒免職処分を受けた日から2年間は、国家公務員もしくは当該地方公共団体の地方公務員として就職することができません。
いずれの場合も、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、「解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできない」(労働契約法第16条)と規定されています。
そのため、使用者の一方的な都合や不合理な理由による解雇は認められません。
「普通解雇」は従業員に非行・違法行為がある場合、能力不足、業務が原因ではない傷害や病気による解雇が該当します。「整理解雇」は経営悪化により人員整理を行うための解雇です。一般的には「リストラ」と言われています。
整理解雇の場合は、以下の4要件に当てはまることが必要です。
① 人員整理の必要性
② 解雇回避努力義務の履行
③ 被解雇者選定の合理性
④ 手続きの妥当性
整理解雇であっても、手続きの妥当性が問われます。正しい手続きを踏まない限り無効とされるからです。そのため、人員整理の対象はまずは非正規に向かいます。
非正規は、契約期間が過ぎてしまえば労働者でなくなるからです。パートも同じで、短期契約期間が満了すれば更新される保証はありません。
解雇の序列とは
過去の判例では、「非正規社員は正規社員より先行して解雇される」ことが明示されています。正社員を整理解雇するためには、「非正規従業員の解雇を先行させなければ解雇権の濫用にあたる」とする判断が示されているのです。
「正社員は解雇できない」という話を聞いたことがありませんか。「解雇できない」のではなく「解雇の順位が存在する」ということです。
解雇対象者の順位は、「純粋なパートタイマー」 → 「定年後再雇用者」 → 「常用的パートタイマー」 → 「常用的臨時工」 → 「正社員」の順位になります。
正社員を簡単にクビにできないのは、このような順位があるためです。
経済界からは「解雇規制の緩和」という根強い要望があります。具体的には「1年分程度の基本給を支払うことで金銭解雇を認める」という方法が検討されています。これには慎重な意見が見られ、反発する声も目立ちますが実際はどうでしょうか。
もし、会社で不要(リストラ)の烙印を捺された場合、そのまま残ったとしても明るい未来を描くことは難しいでしょう。会社と争っても得られるものは多くはありません。割増の手切れ金をもらい、次のパスに向けた準備をしたほうが得策といえるでしょう。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
2年振りに22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)