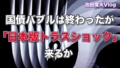ウクライナ戦争の講和がいよいよ視野に入ってきました。アメリカとロシアの高官同士の会合が18日にサウジアラビアで行われました。アメリカからはルビオ国務長官をトップに、ロシアからはラブロフ外相をトップに据えており、実質国家外交No.2同士の話ですので実務者協議というよりかなり政治的な役割を含めた内容であったと思います。
ゼレンスキー氏はこの会合の翌日である19日にサウジ入りをする予定を止めてしまいました。複数の情報を分析する限り、初期の米ロ会合はウクライナ抜き、欧州抜きにして二国間ディール主体型の取引にしたため、ゼレンスキー氏が腹を立てたとみています。ただ、同氏がこれを不服として「俺は行かない」と言ってしまえば講和の枠組みは米ロでほぼ決まってしまう形になります。

ゼレンスキー大統領インスタグラムより
この会合にはサウジのファイサル外相も参加しており、サウジの役目としては同外相がムハンマド皇太子に伝え、それをゼレンスキー氏に伝えるという役目を想定していた模様です。
講和会議は勝者や大国の役得的なところがあります。第二次世界大戦の講和であるクリミアで開催されたヤルタ会議はその好例であります。敗戦濃厚の日本、ドイツに対してヤルタに集まったのはソ連のスターリン、アメリカのルーズベルト、英国のチャーチルでありました。つまり戦争当事国の双方ではありません。極端な話、敗戦国へのペナルティや戦争責任をどう課すか、とい勝者の方程式が支配しました。
一方、日露戦争の講和会議、ポーツマス条約はアメリカのセオドア ルーズベルト大統領(上述のフランクリン ルーズベルトとは従兄弟関係)が仲介し、日本とロシアが直接交渉をしたのですが、その結果は日本国民に強烈な不満を引き起こし、のちの大戦の遠因となる国内強硬論者への刺激となりました。ちなみに司馬遼太郎は日露戦争終結から日本は別の国のように変わってしまったと述べていますが政府と国民の情報差、温度差、認識の差が不和の時代の始まりだったとも言えそうです。
今回のウクライナ戦争は日露戦争や第二次世界大戦のガチ戦争とは違い、一方的な侵略に対し、非侵略国がまだ負けを認めていないのにアメリカが「お前、もうやめろ」と介入し、ロシアを一方的にディール取引者に仕立て上げたことに特徴があります。トランプ流24時間ディールの原点です。
このサウジ講和会合から漏れ聞こえてくるのは①停戦、②ウクライナの大統領選、③終戦と講和の3ステップを基本としているようです。このウクライナの大統領選の必要性については前回のこのブログで私も強調していたところです。ただ、同国の大統領選が行われれば選挙の公正性が最大の焦点であります。もしも画策を含め、親ロシア派の大統領が選ばれればこの3年間のウクライナの戦いは何だったのか、という強烈な失望感が生まれるでしょう。同時にウクライナ人の国外脱出に拍車がかかり国家を支える人口不足に陥るリスクはあるでしょう。
さて、講和をめぐっては中国が「なぜ俺は入らない?」と躍起になっているようです。確かに一時期はそのような可能性も示唆されていただけに中国としては失望感が強いのだと思います。トランプ氏が多国間ディールを好まず、一対一の話で片づける傾向により拍車がかかっていることが大きいのでしょう。
ではその講和会議。新任のルビオ氏と百戦錬磨のラブロフ氏では交渉力が違うと思います。特に以前指摘したようにロシアとしては不毛な戦いは止めたいと思っていますが、ロシアにとって損がない結果に終わらせることが最低条件であり、それができないなら別に講和を急ぐことはないと考えています。
一方、アメリカはトランプ2.0の成果を見せたいし、ルビオ氏も将来の大統領候補になりたいはずですから凱旋したいところでしょう。となればアメリカは足元を見られやすいともいえ、外観から見たディールはアメリカ不利が自明だと思います。ただ、アメリカは戦争当事国ではなく、失うものものないのでそもそも有利不利という議論が成り立たないという意見も出てきそうです。
仮にロシア有利の内容で講和の基本方針が決まった場合、欧州はアメリカに対して強烈な不満感を抱くでしょう。既にバンス副大統領がドイツでの会議において欧州批判を好き放題したことに対して報道の一部には「前向きな刺激」と指摘するものもありましたが、実態は「ふざけんじゃねぇ」という反米の動きが当然出てくると思います。
仮にこの基本トーンの下で講和となれば世界はバラバラになる、そしてアメリカはディールで勝った気でいるけれど実は大変な目に見えない損失を抱えることになるかもしれません。
トランプ氏とプーチン氏が来週中に会談するかという議論について「それはない」とロシアの外交報道官が述べていますが、私は来週かどうかはともかく非常に近いうちに会談するであろうとみています。それは時間がたてばたつほど外野の声が入り込み、話が複雑になるため、さっさと結論付ける、これがディールを成功裏に収める勝利の方程式だからです。
今置かれている状況は山道で分かれ道に遭遇したところでトランプ氏は直感で下りの歩きやすそうな道を迷わず選びつつある、そんな感じがします。さてそれがどういう結果になるのか、我々は傍観をする以外に方法がなさそうです。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年2月20日の記事より転載させていただきました。