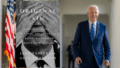日本の財政は健全だ、なぜなら日本政府が発行する国債は実質的に日本人が買っているからだ、という説明を信じている方も多いと思います。確かにひと昔前は日本の国債は直接、間接的に日本人が買っている比率は高かったのです。
では今はどうなのでしょうか?日銀の21年3月の資金循環統計によると国債とT-Bill(国庫短期証券)の合計発行額が1220兆円、これを所有する比率は日銀43%、銀行16%、生損保18%、年金6%、家計(個人)1%に対して海外が14%まで膨れ上がっています。とすれば日本の財政は健全である、という言い分は少しずつトーンダウンせざるを得ないのです。海外勢の比率が高まれば高まるほど「正論」を振りかざされる可能性が高く、市場が読みにくくなるからです。

石破首相 首相官邸HPより
もう少し詳細に見ると国債だけの所有に絞れば海外勢は8%まで下がります。一方、T-Billは海外勢が61%と大きく跳ね上がっています。(最新の日銀資金循環統計を確認しましたが海外分については有為な変化は見られませんでした。)
日本の財政状況がG7で最低水準だという意識が高まれば国の借金である国債の信認の評価が下がり、国債価格の下落(利回りの上昇)を引き起こしかねなくなります。一般社会においてはそんなことがすぐに起きるとは考えてもいないと思いますが、災いはある日、突然来るものです。
日本の国債の格付けは三大格付け機関ともAランクを維持しており、見通しも安定的になっていますが、世界ランクからすると実は24位にとどまります。不動産であれだけ苦しむ中国が25位、韓国はAA格となっていて16位、上位10か国のうち7か国は欧州の国々となっています。異論はあるでしょうが、実態としてはそれが事実です。機関投資家はデータを重視しますので「名誉回復」したいのであれば当然、格付けが良化するように努力しなくてはなりません。
日本の格付けが低い理由は政府債務がGDPの250%の域にあること、その赤字を減らす取り組みに欠けること、経済成長率が低位で推移していること、基礎的財政収支も黒字化が見えていたのですが達成できなかったこと、少子化で日本の成長における長期的展望が描きにくいことなどが上げられます。
そんな中飛び出したのが財務省が5月20日に行った20年利付国債入札の不調でした。特に平均落札価格と最低落札価格の差である「テール」が1円14銭と1987年以来の水準となり、専門家が「衝撃的」と称するほどの不調ぶりだったのです。国債入札では金融機関が買いたい金額を入札するのですが、需要が大きければテールと称する入札された価格のばらつきが少ない一方、今回のように価格差が大きい場合は需要が少ないことを意味します。
本件、ブルームバーグ、日経とも大きく取り上げています。専門的な分野になるのでかいつまんで説明すると日本の長期、超長期国債の魅力が剥がれている中、日銀が国債の買い入れを縮小させており、国債の買い手不在になっており、特に国内機関投資家の動きが弱く、海外勢頼みということです。
当然ながら市場では10年物などの長期やそれより長い超長期国債の利回りが上昇(国債価格が下落)しています。国債は満期まで持ち、その時発行者が健全であれば満額が返ってきますが、国債価格が下落している趨勢を考えると機関投資家は「買ってもすぐに含み損」が生じるわけで「そんなものは買いたくない」というわけです。ということは新発国債の利率が市場の期待度とマッチしていないということになり、日本は利上げせざるを得ない雰囲気が遠くからひたひたと迫ってくる感じがあるのです。もちろん、今日明日という話ではありません。ただ、10年単位のスパンで考えた時、その時の市場を想像しにくく、故にプロの運用者たちも萎えていると申し上げたらよいのでしょうか?
日本が長期にわたり低金利を維持できたのは黒田氏が日銀総裁の時にテクニカルにいじり過ぎた結果だと思うのです。私は当時から懐疑的なコメントを出していました。氏の時代は日本経済再生のために必死の防戦(=ゼロ金利、マイナス金利政策)をしたのです。そしてその間に経済の体力が自律回復し2%のインフレ率を達成する目論見でした。これが皮肉にも違う理由で氏が総裁在任時の最終年にインフレが実感されるようになり、植田総裁になってからはインフレ対策と黒田氏の置き土産の整理に追われている状況だと考えています。
国債の話は難しいのでわかりにくいと思います。その中で一つだけ私が言いたいのは日本の国債はもはや日本市場で全部吸収されるのではない、よって市場原理と海外のうるさ方の動き次第では日本の金融市場には利上げ圧力がじわじわかかり、10年後にアメリカ並みの水準になっていても驚くべきではないということです。株式市場が海外投資家の影響をもろにかぶっているのと同様、国債市場も変化の過程にあるということでしょう。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年5月21日の記事より転載させていただきました。