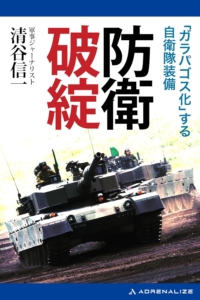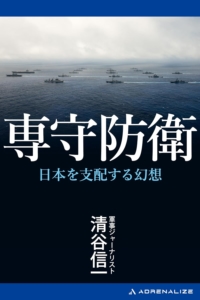1年超空室ビル、都心で急増 3年で12倍、再開発で飽和感 湾岸部の苦戦鮮明 日経新聞

こんなことは素人でも分かる話です。コロナによるリモートワークの普及は想定外だったでしょうが、その後も続々と建築が続きました。
ますます少子高齢化で労働人口が減っていきます。それは同時に建設業でも同じです。これによって工事のコストは上がって長期化します。当然採算性は悪くなります。
それが予見できなかったのでしょう。
東京都心部の大型ビルに飽和感が出始めている。日本経済新聞が1年以上にわたり20%超の空室を抱える物件の空室面積を調べたところ、2024年は3年前に比べて12倍に急増していた。湾岸部の苦戦が鮮明で、新型コロナウイルス禍後の出社回帰が進むものの、相次ぐ再開発によってオフィス市況は供給過剰に傾いている。
東京23区内の大型ビルの賃貸面積は25年末時点に約2400万平方メートルと14年末比で2割弱増える見通しだ。
長期空室ビルの立地を空室面積ベースで分析すると、地域別に優勝劣敗の傾向が鮮明だ。25年1月時点では「晴海・勝どき・月島」が全体の35%を占め、「豊洲・有明・辰巳」が26%で続いた。
「大手町・丸の内・有楽町」の長期空室ビルは同時点ではゼロだ。
今後渋谷、八重洲、中野などで続々と構想オフィスビルが完成します。行った移動するのでしょうか。新規は新規で建築費の高騰で収益還元性が低下しているので、これまた地獄でしょう。

Japanesescape_Footages/iStock
湾岸などが不利なのはアクセスもあるでしょうが、ランチや仕事の後の飲食でまともな店がないことも大きいでしょう。全国チェーンしかなくて、多様性がなくなる。これはタワマンとオフィスビルの開発でも同じです。近所の飲食店街を潰して家賃の高いビルを造れば資金力のあるチェーン店しか入居できない。そもそも湾岸はそういった既存の飲食店もない。
ある意味都心の再開発は総丸の内化ですが、実態は田舎のイオンモールと同じです。文化や食生活の多様性がない人工的な場所は都会の利点を殺すのと同じです。それを税金チューチューができると政治家や行政が後押ししてきた。
再開発で高層のオフィスビルやタワマンの乱立はやめるべきです。需要はないし、一見需要があるタワマンも投機対象が多く実体経済の底上げにならない。しかも貴重な建設業界の資源を浪費している。むしろそのようなリソースは水道や橋梁、道路などのインフラの改善や維持に使うべきです。
都心で再開発するならばむしろマッチ箱みたいなカーポート付きの二階建ての一戸建てです。スペースのムダ遣いですし、高齢になれば階段での上り下りは障害になります。
であればこれらの低層マンション化を図るべきです。一階は店舗にしてもいいでしょう。駐車場は区画に一つ立体駐車場を造ればいい。スペースに余裕があれば緑地や公園にしてもいいでしょう。
威張りの効く高層ビルだけが再開発だというのは田舎者か成金の発想です。
■
【有料記事】
Note に有料記事を掲載しました。
Japan in Depthに以下の記事を寄稿しました。
防衛省、陸自用汎用無人機開発へ
ES&D誌に寄稿しました。
Japanese MoD initiates project to develop VTOL UAV for ground forces
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
財政制度分科会(令和6年10月28日開催)資料
防衛
防衛(参考資料)
編集部より:この記事は、軍事ジャーナリスト、清谷信一氏のブログ 2025年5月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、清谷信一公式ブログ「清谷防衛経済研究所」をご覧ください。