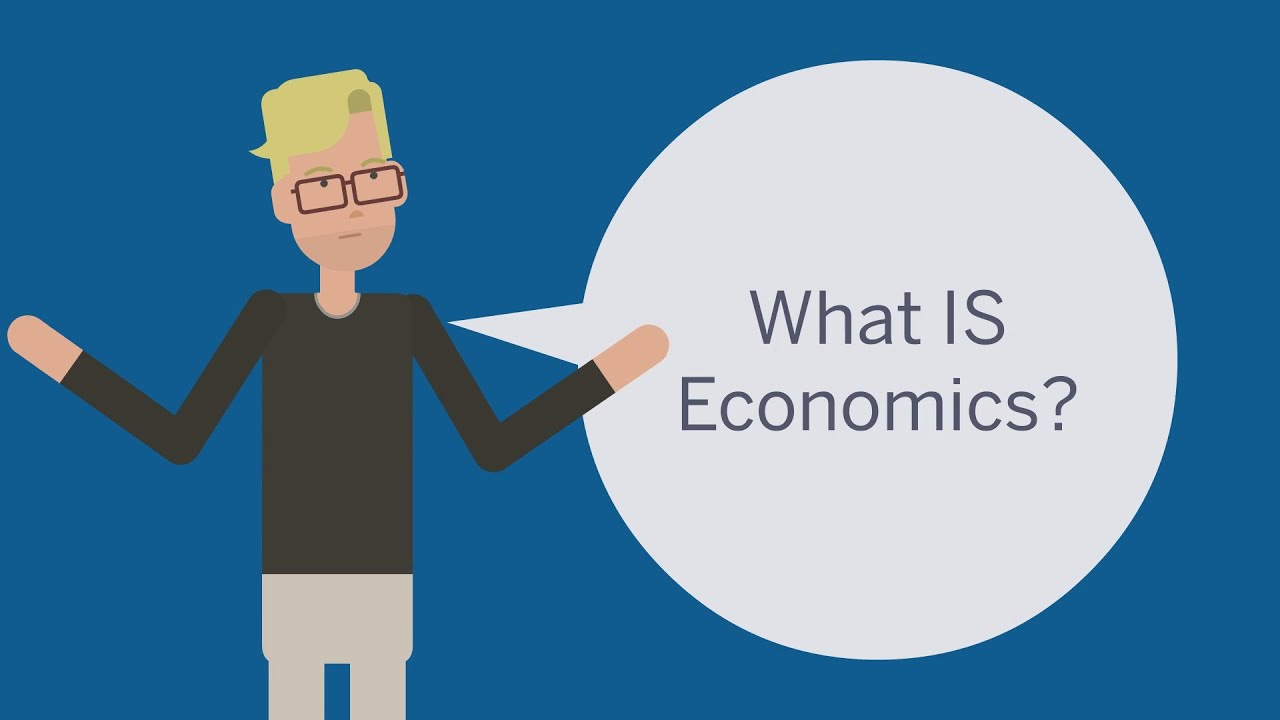
こんにちは、自由主義研究所の藤丸です。
今回から「初心者のための経済学」と題して、全10回のシリーズを書こうと思います。
これは、経済学に興味を持った人に、まず知ってもらいたい基本的な語についての全10回の簡単な解説シリーズです。
たとえば、
「経済学とはそもそも何?」
「コストとは?利益とは?何を意味するもの?」
「お金はどうやってできたの?」
「縁故主義って何?」
などについて誰かから質問された場合、皆さんはどのように答えるでしょうか?

「お金って何?」
経済学、利益、コスト、お金…などの言葉は、あまりにも当たり前のものとして使われているので、その意味について特に考える機会はないかもしれません。
しかし、耳慣れない経済政策の用語や政府の御用の経済評論家などが話す「難しそうな言葉」よりも、このような基本的な言葉が表すものについて、しっかり考えてみることは、非常に重要なことだと思います。
このシリーズは、アメリカの自由主義系のシンクタンク「ミーゼス研究所」の「初心者のための経済学」の動画シリーズ(※)を元に、一部意訳・解説を追加して紹介します。
(※)このシリーズ動画は、近々、日本語字幕を付けてyoutubeに公開予定です(許可取得済)
第一回目は、
「経済学とは何か?」
です。少し抽象的な内容ですが、短い記事なので、ぜひ最後までお読みください☺️
元の動画は以下です。
経済学は、「陰鬱な科学」と言われることがあります。
経済学の授業では、「抽象的な需要と供給のグラフや複雑な数式」を中心に教えられることが多いからかもしれません。
経済や経済学について考えるとき、私たちはお金、商品、サービス、または政府の政策などを思い浮かべます。
しかし、これらは経済の一側面にすぎません。
経済学の核心は「人間の行動」、つまり「個人として私たちが選ぶ選択や行動」にあります。
私たち一人ひとりの欲求や必要性、能力、そしてどのように互いに利益を得て社会を築くか、これこそが経済学の本質です。
例えば、もし一人の男が無人島に取り残されたと想像してみてください。
彼の名前はボブです。
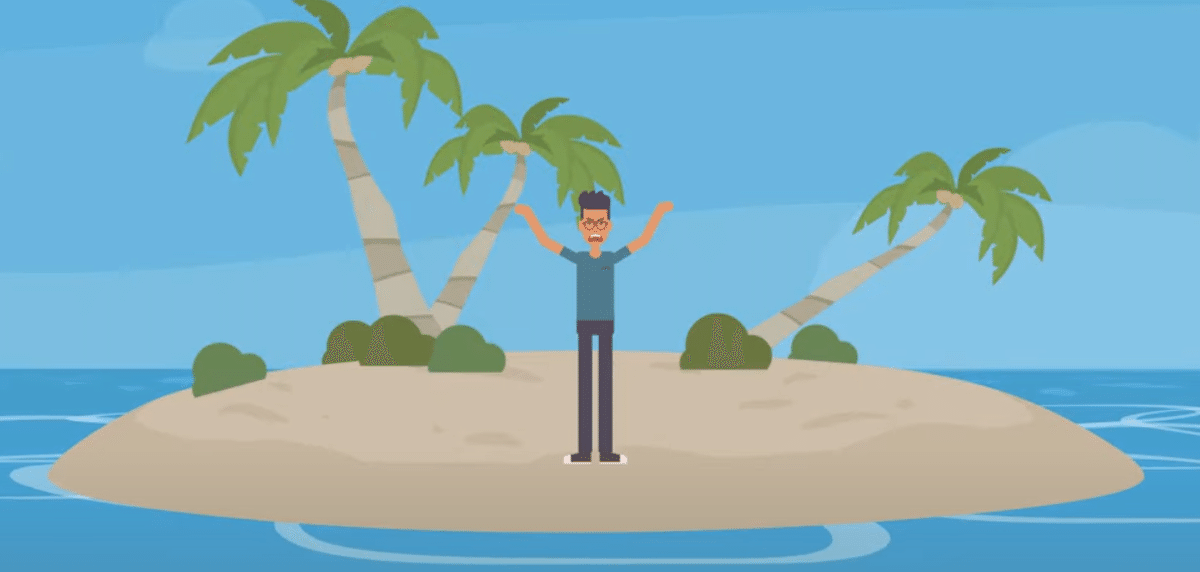
無人島に取り残されたボブ
ボブにとって最優先事項は、何でしょうか?
それは、「生き延びること」です!ボブには水や食料、それに雨風を防ぐための小屋が必要です。ボブは、島でココナッツやベリーなどの食料を採集できるかもしれません。
しかし、同じくらい重要なのは「時間」です。
つまり、ボブは自分の時間をうまく配分し、自分の生存の可能性を最大化しなければなりません。
たとえば、次のAとBの選択肢で、ボブはどちらを選ぶべきでしょうか?
- 最初の数時間を水を探すことに費やす
- まずは小屋づくりに取りかかる
ボブはこうしたトレードオフ(取捨選択)の判断を迫られます。
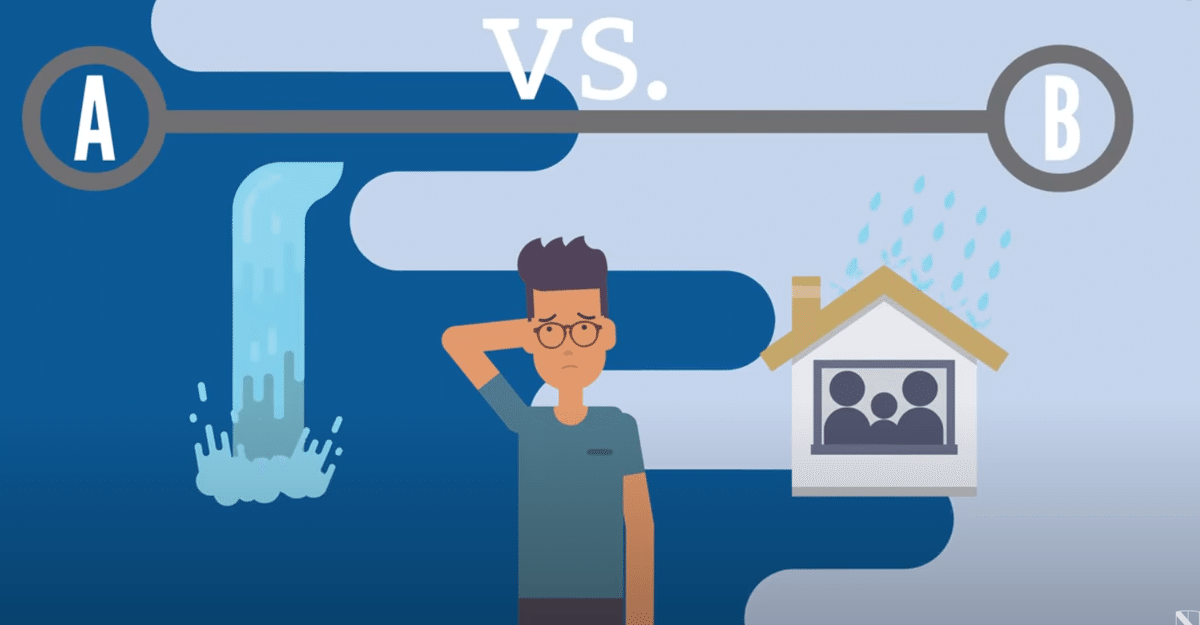
水を探すべき?小屋を作り始めるべき?
一つの決断を下すことの、実際のコストとは何でしょうか?
例えば、ボブは「水がなくても三日間は生きられる」と判断して、まずは夜過ごすための小屋を作り始めるかもしれません。
別の人なら、違う選択をしたかもしれません。
しかし、ボブが選んだ行動は、彼自身の判断に基づいています。
ボブの判断は、必ずしも正しいとは限りません。
リスクや不確実性は、人間の存在に内在する要素です。
もしかしたら、ボブは小屋作りに時間をかけすぎてしまい、水を探す時間が足りずに、いざというときに飲み水が見つからないかもしれません
その結果、ボブの生存日数は大きく減ってしまうかもしれません
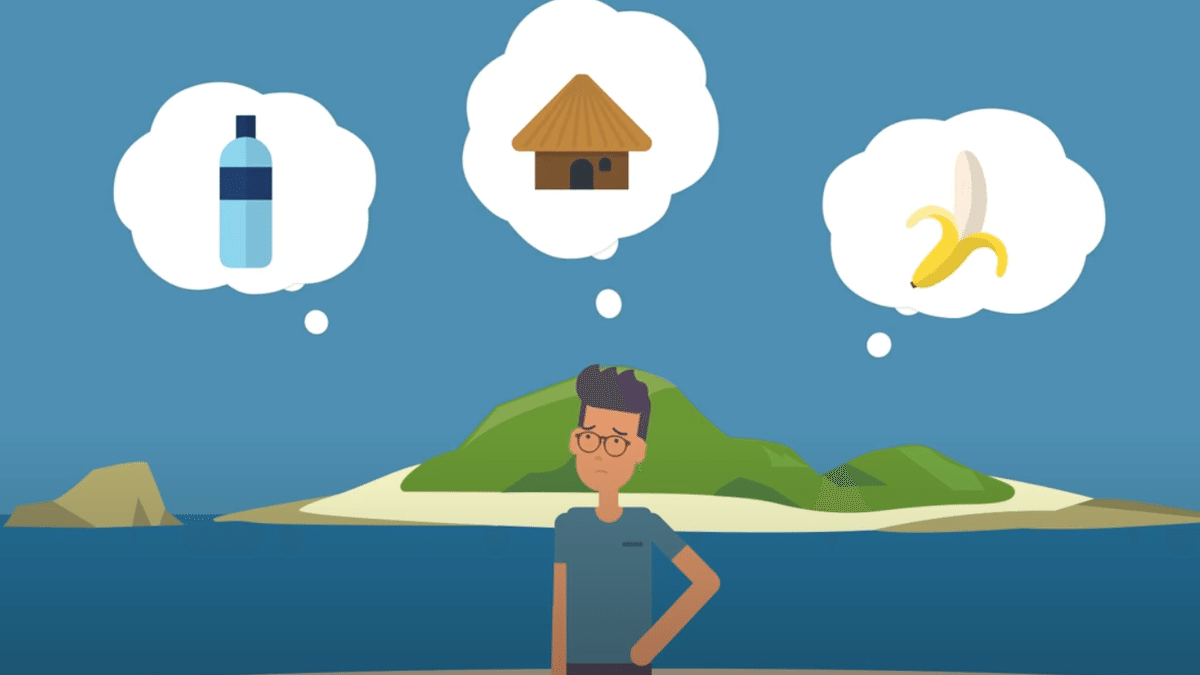
この場合、ボブの「利益」は生き延びられた日数で測られます。
そして「損失」は、彼の死を意味します。
ここで重要なのは、ボブの経済的な意思決定に、お金は無関係だということです。
それらは単に、不確実な未来に直面して彼が下す選択なのです。
幸いなことに、私たちの日常の意思決定は生死に関わる問題はほとんどなく、毎日私たちが行っている基本的な決断です。
これらの決断には、個人が比較検討しなければならないコストと利益があります。
これは、無人島にいる人と同じように世界のどこにいても、誰にとっても真実なのです。
経済学は、個人に「何をすべきか」を教えるものではありません。
そうではなく、経済学とは決断に伴うコストを理解すること、自分自身と他者の欲求を満たすことでどのように価値を創造できるかを理解すること、そして私たち個人が人類文明の興亡にどのように貢献できるかを理解することです。
私たち一人ひとりが問われるのは、どのような役割を果たしたいかです。
■
最後まで読んでくださりありがとうございました。
第一回は「経済学」についてでした。
やや抽象的な話でわかりにくかったかもしれません。今回登場した「コスト」について、第ニ回目で掘り下げます。徐々にイメージしやすくなりますので、次回もぜひお読みください。
編集部より:この記事は自由主義研究所のnote 2025年5月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は自由主義研究所のnoteをご覧ください。













