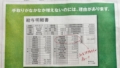黒坂岳央です。
「老後は引退してのんびり暮らすのが当たり前」という時代は終わった。SNSでは「定年退職後もコンビニやファーストフードで働く高齢者はかわいそう。政治家が日本経済をダメにした!」といった意見も見受けられるが、これは現状を正しく認識しているとは言えない。
「定年退職してのんびり暮らす」というライフスタイルは、昭和の高度経済成長期における一時的かつ特殊なモデルに限定される。今後は、一部の「特権階級」のみが享受できるものとなるだろう。現状の制度や物価水準を前提としたFIRE(Financial Independence, Retire Early)設計は、失敗に終わる可能性も出てくる。
しかし、筆者はこの状況を悲観しているわけでもなく、根拠なく不安を煽りたいわけでもない。事実に基づき、現実的かつポジティブな視点から今後の展望を考察していく。

Hanafujikan/iStock
変化する「老後の常識」
まず、我々の現在の経済環境を正確に認識する必要がある。
現代を生きる高齢者は、老後の引退生活を送ることができるおそらく最後の世代となる。老後の引退生活は、便利な生活とインフレを抑制する潤沢な労働人口、そして盤石な年金制度が前提であった。平成時代まで存在した終身雇用や年功序列、高額な退職金なども、安定した老後生活には不可欠な要素だったと言える。
しかし、現実は国際競争の激化、人口減少、そして年金支給開始年齢の後ろ倒しによって、これまでの「老後」を維持することが難しくなっている。
人口減少は今後さらに加速するため、働き手が減少すれば、それだけインフレは進行するだろう。AIの進化によって仕事がなくなるという議論もあるが、これは2000年のIT革命の際にも全く同じように言われていた話だ。結果として新たな仕事が増加し、労働時間は政策で抑制されているものの、現代人は1時間当たりの労働密度が高くなった。
確かに、今のAIは2000年代とは異なり自律型であるため、仕事に大きな影響を与えるだろう。しかし、コストやソフトウェア面を考慮すると、全ての人間の労働がゼロになるというのは現実的ではないと考える。
ここまでの状況を踏まえると、現時点の高齢者が老後の引退生活を送ることと、10年後、20年後に同じことをするのとでは、難易度が全く異なるとわかる。「日本人なら全員が定年退職後、働かずに穏やかに隠居生活を送る」という想定はしない方が賢明だろう。
海外も日本と同じ状況
ここまでの話を聞くと、「日本は最悪だ」と悲観的な気持ちになる人もいるかもしれない。だが、これは正しい認識ではない。新興国はもちろん、他の先進国も同様の状況に直面しているからだ。
世界一の経済大国であるアメリカでも、年金だけで老後を過ごせる人は少ない。SMBC日興証券の調査(2021年)によると、日本の変額年金への関心度が52%であるのに対し、アメリカでは80%の人が変額年金に関心を示しており、自助努力への意識の高さがうかがえる。
また、デロイトの2015年の調査では、55歳以上の世帯で金融資産(固定資産・年金を除く)が25万ドル以上あるのは4分の1未満と報告されており、経済的な蓄えが不十分な高齢者が多いことが示されている。
さらに米国労働統計局(BLS)のデータでは、アメリカにおける65歳以上の就業率は増加傾向にあり、1987年の11.1%から2023年には19.0%に上昇している。公的年金受給開始年齢の62歳や公的医療保険の対象となる65歳を超えても働き続ける高齢者が増えているのだ。
アメリカだけではない。ヨーロッパの事情も同様だ。欧州各国では、少子高齢化に伴う年金財政の維持のため、年金支給開始年齢の引き上げが進められている。
例えばドイツでは、2012年以降、公的年金の支給開始年齢が従来の65歳から段階的に引き上げられ、2031年初めまでに標準定年年齢が67歳になる予定だ。イギリスでは2007年の年金法で68歳まで引き上げが決定。フランスでも満額年金の開始年齢が65歳から67歳に段階的に引き上げられている。
「日本の年金はダメだ」という声も多いが、アメリカや欧州諸国でも、年金制度の持続可能性と高齢者の経済的自立のために、労働期間の延長が進められていることがデータから明らかになっている。
もう時代は変わったと受け入れ、一生働く前提で人生設計をする必要があるだろう。
令和からの新たなキャリア戦略
今後の時代、これまでのように「仕事=やりがい」「安定企業で働く」という考え方を見直すべきだろう。
どれほどの大企業でも、国際競争やAIの台頭によるゲームチェンジの影響で倒産する可能性は出てくる。そうなれば、安定企業にしがみついて働くよりも、「いつ勤務先が倒産しても働き口に困らない労働市場価値を維持する」という思考が機能する。
つまり、平成時代までの「就社」(特定の会社に所属し続けること)ではなく、真の意味で「就職」(市場で求められるスキルを持って仕事に就くこと)という考え方で働くべきだ。そう考えると、最近流行りの「静かな退職」や「上司選択制度」は、一社が長く存続することを前提とした「就社」の考え方であり、非常にリスキーになり得ると言える。
しかし、悪いことばかりではない。市場価値が高い人材は、これまで以上に高収入・高待遇を享受できる可能性が高まる。常に大きな時代の変化の中には、大きなチャンスが眠っているのだ。
どこへ行っても役に立つ高付加価値スキル、生成AIを使いこなす高い生産性、そして利他意識を前提としたビジネスマインドを持っている人材は希少だ。さらに今後、労働人口が減少することで、そうした人材はこれまで以上に引く手あまたになるだろう。
加えて、労働生産性が高まり、雇用も流動的になれば、「複数の収入源を持つ働き方」であるパラレルキャリアへのシフトも可能になる。コロナ禍で医師がアルバイトでワクチン接種を行う案件が注目されたが、それと似たようなもので、例えばエンジニアが勤務先以外にも複数のクライアントを持つことで収入を倍増させるというイメージだ。
生成AIを使いこなす人であれば、高いスキルをパラレルで提供できるため、収入を増やしていくことが可能になる。筆者自身も今年に入ってから仕事が急激に増えた。正確に言えば、大幅に生産性が高まったことで、これまで以上に仕事を引き受ける余地ができた、という方が正しいだろう。
今後はそうでない人と大きな差がついてくるはずだ。ひいては老後も見据えた生き方に多大なる影響を与えるだろう。
◇
筆者はむしろ「一生働く時代」をポジティブに捉えている。老後の悠々自適な生活、は一時的な時代のボーナスタイムだっただけで、長い歴史を見ればこれまでが特別だったのだ。
そして「老後の生活のために嫌な仕事でも我慢」という生き方は不健全に思える。それなら一生働くと割り切って、スキルアップや本当に能力を発揮できる仕事を探し、時にはパラレルワークで「労働=嫌なもの」から「労働=生活」に認識を変えてしまえばいいと思うのだ。
■最新刊絶賛発売中!





![[黒坂 岳央]のスキマ時間・1万円で始められる リスクをとらない起業術 (大和出版)](https://agora-web.jp/cms/wp-content/uploads/2024/05/1715575859-51zzwL9rOOL.jpg)