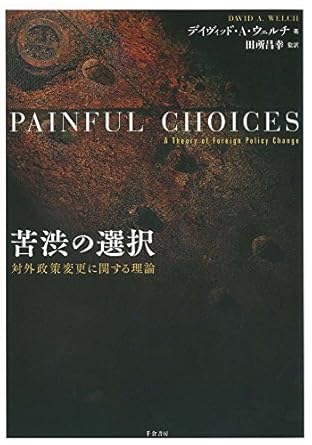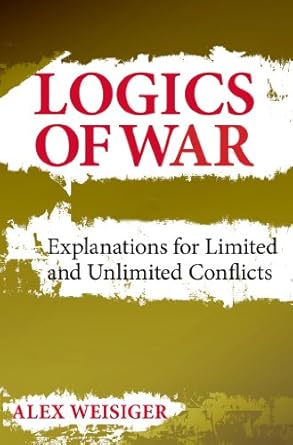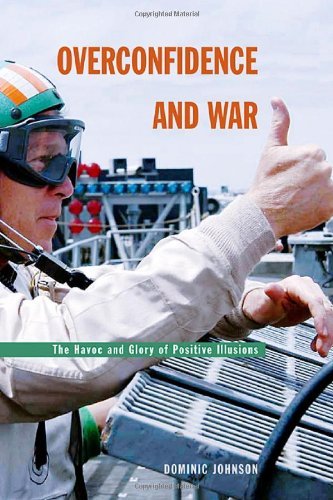President of Russiaより
ロシアの「ウクライナ戦争」開始の政策決定について、最高権力者でしばしば独裁者と呼ばれるプーチン大統領の思考がいろいろと推察されています。
我が国では、ある著名な旧ソ連地域研究者が、この事実をミステリアスだとして、「政治的整合性が全くないんですよね。全く論理的にメリットがないことであって、それをやることによって何の得もないわけですよ。どう考えても」とある雑誌のインタヴューで答えています。

はたしてプーチンとかれの側近たちが、ウクライナに攻め込むのを決めたことは、謎であるばかりでなく、国益に反する非合理的な行為だったのでしょうか。もし、こうした推論が正しいとすれば、プーチン政権のロシアは政治的に説明できない国家であり、したがって、何をやるか分からないモスクワには論理的な対応ができなくなるという、深刻で解き難い問題にわれわれは直面することになるはずです。
本当にそうなのでしょうか。わたしは、そんなことはないと判断しています。なぜならば、プーチンの決断は「政治心理学」で多くを説明できるからです。
残念ながら、日本の国際政治学・国際関係論で心理学を取り入れる研究は、あまり見かけませんが、この分野で世界をリードするアメリカでは、かなり前に「行動国際関係論(Behavioral International Relations)」が台頭した結果、心理学を取り入れた行動経済学のように、次々と画期的な研究成果が生み出されるようになりました。
大胆にいえば、戦争などの出来事を分析するために、アメリカの政治学者が心理学の知見を使うのは、ごく普通のことなのです。そして、こうした学際的アプローチの最大のメリットは、われわれが直観ではナゾに思える政治指導者の行為を論理的に説明することを可能にしてくれることでしょう。
この記事では、ウクライナ侵略に関するプーチン政権の政策決定について、政治学者のスティーブン・ウォルト氏(ハーバード大学)が心理学の基礎理論を用いて説明した、『フォーリン・ポリシー』誌のエッセイから、これに該当する部分を抜粋したうえで、わたしが解説をくわえたいと思います。
「人間は…損失回避のためなら、より大きなリスクを厭わない…プーチンは、ウクライナがアメリカやNATO(北大西洋条約機構)との連携へと徐々に傾いていると確信したなら…彼が取り返しのつかないとみなす損失を実現させないことは、一か八かの賭けに値するものなのかもしれない」。
プロスペクト理論は、ダニエル・カーネマン氏(ノーベル経済学賞受賞)とエイモン・トベルスキー氏により確立されました(Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” Econometrica, Vol. 47, No. 2, Mar., 1979, pp. 263-291)。そして、この理論は国際関係論にも広く取り入れられました。
たとえば、政治学者のデイヴィッド・ウェルチ氏(ウォータールー大学)は、開戦の決定を含む外交政策の変更を損失回避行動で説明しています。すなわち、「対外政策が最も劇的に変化しやすいのは、このまま現状が維持されることで、大きな苦痛を伴う損失をこうむり続けると指導者が判断したとき…我慢できる(損失を回避する)結果に至るかもしれない選択肢が…存在していると政策決定者が認識したとき」ということです(『苦渋の選択』田所昌幸監訳、千倉書房、2016年、17頁)。
つまり、国家というものは、利得より損失に強く動かされるということです。この視点が欠落してしまうと、前出の地域研究者のように、プーチンの決断には「政治的整合性がない、何の得もない」という結論に至っても不思議ではありません。
なお、このような説明については、「ウクライナはロシアのものではないのだから、損失ではない」と反発する人も少なくないでしょう。
ここで大切なことは、ウクライナがロシアから独立した主権国家であるという事実ではなく、プーチンがウクライナの「NATO同盟国化」への動きをどのように認識していたのか、ということです。プーチンやモスクワの指導者にとって、ウクライナが「緩衝国」から敵対する強大な同盟勢力の一部になろうとしていることは、間違いなく大きな損失に映ったであろう、ということです。
「自分の行動は環境のせいにして、他人の行動はその人の本性のせいにする傾向も、たぶん関係している。現在、西側の多くの人は、ロシアの行動をプーチンの非道な性格が反映されたものであり、以前の西側の行為への反応とは解釈していない…プーチンからすれば…アメリカとNATOの行為は生来の傲慢さから生じたのであり、ロシアを弱い立場に置き続けたい深い願望に根ざしており、ウクライナは誤導されている…と見えるのだろう」。
こうした属性バイアスは、とりわけ侵略の標的とされた国家の指導者や市民の思考に重くのしかかります。すなわち、ウクライナは、プーチンのような攻撃的で危険な人物が政治権力を握っている限り安全ではないと判断することにより、戦争に終止符を打つのをためらうのです。
こうした戦争を長期化させるメカニズムは、Alex Weisiger, The Logics of War, Cornell University Press, 2013で詳しく解説されています。
「誤認に関する膨大な文献は、とりわけ故ロバート・ジャーヴィスの画期的な研究が、この戦争について、われわれに多くを教える。今やプーチンが多くの面で深刻な誤算をしたのは明らかだ。かれはロシアに対する西側の敵意を過大評価し、ウクライナの決意をひどく過小評価し、迅速かつ安上がりな勝利をもたらすはずだと自軍の能力を過度に見積もったようだ」。
ジャーヴィス氏は、国際関係論における「政治心理学研究」のパイオニアです。かれは「戦争は、国家が敵の力を過小評価すると同時に敵意を過大評価する時に、とりわけ起こりやすい」と指摘しています(Robert Jervis, “War and Misperception,” in Robert I. Rotberg and Theodore K. Rabb., eds., The Origin and Prevention of Major Was, Cambridge University Press, 1988, p. 125)。
政治指導者が侵略する相手国のパワーを過小評価してしまう短絡的思考は、以下の自信過剰バイアスと密接に関連しています。
「(プーチンのウクライナ侵攻の決定は)恐怖と自信過剰の組み合わせの…典型だ。国家は素早く相対的に低コストで目標を達成できる確信がなければ、戦争を始めたりしない。長く血みどろの高くつく敗北に終わるだろうと信じる戦争は、誰であれ始めない」。
この自信過剰バイアスには、政治家だけでなく研究者のみならず一般市民も広く冒されやすいので要注意です。この認知の歪みは、自分の判断を過信してしまうことです。そして、不幸にも、これは戦争の主要な原因の1つなのです。
詳しくは、ドミニク・ジョンソン氏(オックスフォード大学)の『自信過剰と戦争(Overconfidence and War)』ハーバード大学出版局、2004年をお読みください。
「さらに、人間はトレードオフ(相容れない2つの選択)を扱うのは居心地が悪いので、一度戦争が必要だと決めたら、上手くことが運ぶだろうと見込む強い傾向がある…この傾向は政策決定過程から異論が排除されると酷くなり得る」。
社会心理学者のアーヴィング・ジャニス氏は、政治的意思決定において、対立する見解や行動がもたらす不快感(認知不協和)から逃れるために、「集団の凝縮性が高まると…逸脱した思考が抑制される…高い外的ストレスの条件下で、メンバーがリーダーの知恵に依存し、かつその集団の調和を維持しようとする誘因は…不安を軽減したいという動機である…『心配ない、すべては都合よく行くだろう』と…メンバーは互いの自信を高め、未知の危機にも安心感を持つ」結果、浅はかな決断をくだしてしまうと指摘しています(『集団浅慮』細江達郎訳、新曜社、2022年、403-419頁)。
どんなに優秀な人材が集まっているとしても、「仲良し集団」では、それは愚かなことだと分かっているときでさえ、同調圧力などにより異見を述べにくくなる結果、しばしばバカげた決定をしてしまいます。「ベスト&ブライテスト」集団だったアメリカのケネディ政権が、キューバへの「ピッグス湾侵攻作戦」で惨めな失敗をしたのは、その典型例です。
要するに、プーチンの決定は、かれを「非合理な狂人」と見なさなくても、政治心理学の基礎理論を使えば説明できるということです。
もちろん、これまでのプーチンの行動に対する心理学的説明は推察にすぎません。この問題に関する新しい情報が明らかになれば、上記の説明は修正や棄却を余儀なくされることでしょう。そして、それは社会科学において健全なことです。われわれはロシアのウクライナ侵攻といった重要な解くべきパズルについて、「史料が明らかになるまで分からない」と逃げずに、入手できる情報をもとに「作業仮説」による説明を行うべきです。それが事実に近づくための第一歩なのですから。
ウォルト氏は、「残念なことに、誰一人として権力の座にいる者は、学問的成果に深い関心を寄せていないようだ」と嘆いています。わたしもまったく同感であるばかりでなく、これは政治権力サークル外にも多かれ少なかれ当てはまります。
政策立案者や専門家、市民が、政治心理学をもっと活用すれば、ロシア・ウクライナ戦争への理解が広く深まり、今までとは違う対応策も考えられるようになることでしょう。