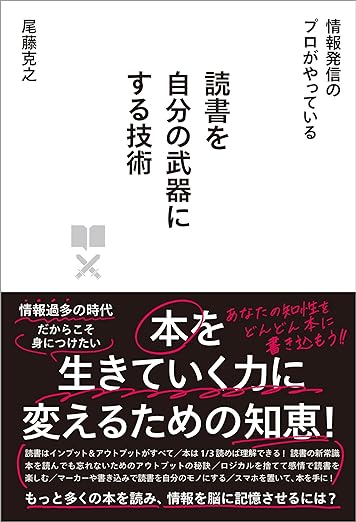Yusuke Ide/iStock
例年、就活シーズンになると様々な課題が浮き彫りになる。就活支援会社は「ミスマッチの軽減」を掲げ、企業側も「より良い人材確保」を目指して試行錯誤を続けている。しかし、現状のシステムには根深い構造的問題が存在することも直視すべきだ。
人気企業ランキングの建前と本音
人気企業ランキングは、就活生にとって企業選びの参考資料の一つとなっている。しかし、これらのランキングには「建前」が存在することも事実だ。就活支援会社にとって、ランキング上位企業は重要なクライアントである場合が多く、完全に中立的な評価とは言い難い面もある。
厚生労働省の「令和3年新規学卒者の離職状況」によると、大卒者の3年以内離職率は31.5%に達している。特に従業員規模1,000人以上の企業でも25.0%が離職しており、「人気企業=長期的なキャリア形成」という図式は必ずしも成立していない。
マイナビの「2025年卒大学生就職意識調査」では、就活開始から内定獲得まで平均8.2ヶ月を要し、学生一人当たりの平均エントリー数は23.5社に上る。この長期化は学生に多大な負担を強いている。
経済的な面では、交通費、宿泊費、スーツ代などで平均20万円近くの出費になる。就活塾やセミナーへの投資として月額3万円から5万円を支払う学生も存在する。
精神的な負担も深刻だ。不採用通知による自己否定感の蓄積、同期との比較によるプレッシャー、そして「お祈りメール」の連続による心理的疲労が、多くの学生を苦しめている。就活うつという言葉が生まれるほど、その影響は社会問題化している。
学歴フィルターの建前と本音
リクルートワークス研究所の「人材採用の動向調査2023」によると、採用時に「大学名を重視する」と回答した企業は38.2%に上る。しかし、興味深いことに「学生には公表していない」企業が全体の72.3%を占めるという結果が出ている。
実例を挙げると、ある大手総合商社では説明会予約システムで特定大学以外は「満席」と表示される仕組みが存在し、大手メガバンクではMARCH以上の学生のみにリクルーター面談の機会が与えられている。
また、学歴不問を謳う大手メーカーでも、内定者の9割が旧帝大・早慶出身者で占められているケースもある。この「建前と本音」のギャップが、多くの学生に無駄な努力と失望を強いている現実がある。
日本独特の新卒一括採用システムは、他国と比較すると特異な存在だ。アメリカでは通年採用が基本であり、インターンからの採用が主流となっている。ドイツではデュアルシステムと呼ばれる職業訓練と学業の並行制度があり、企業での実習経験を経て採用される。一方、韓国ではスペック重視の傾向が日本以上に顕著で、TOEIC、資格、学歴が重要視される。
多様化する選考方法の実態と問題点
学生への現実的なアドバイスとしては、まず「全員が大手企業に就職できる」という幻想を捨てることが重要だ。中小企業やベンチャー企業も含めた幅広い企業研究を行い、プログラミングや語学などスキル習得への投資を怠らず、就活という「ゲームのルール」を理解した上で戦略を立案することが求められる。
就職活動は、理想と現実、建前と本音が交錯する場だ。企業は優秀な人材を求めながら効率性を追求し、学生は自己実現を求めながら安定を望む。この矛盾を完全に解消することは困難だが、少なくとも現実を直視し、より透明性の高いシステムを構築することは可能なはずだ。
就活という人生の重要な岐路において、より多くの若者が自身の能力を正当に評価され、適切な場所で活躍できる社会の実現を期待したい。そのためには、企業、大学、学生、そして社会全体が一体となって、現行システムの問題点を認識し、建設的な対話を重ねていく必要がある。理想論に終わらせず、具体的な行動に移すことが、今こそ求められているのである。
尾藤 克之(コラムニスト・著述家)
■
22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)