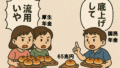かなりインパクトがある報道なのにわりとメディアの取り扱いが淡白な感じがするのはまだ取材ネタが十分揃っていないからでしょうか?日本郵便が運送に関する法定点呼を行わなかったり不適切な点呼が全国75%の郵便局で発覚し、不正の数は何と15万件に上る事態になったことを重く見た国土交通省が郵便輸送に絶対に不可欠な同社のトラック車両2500台の事業免許を取り消してしまいました。再申請まで5年必要です。つまり免停5年とも言えます。

west/iStock
今後さらに軽自動車32000台も免許取り消し検討に入るとされ、郵便輸送の幹と主要な枝部分を切られるようなもので残るは葉っぱの部分をカバーするバイク便だけになります。いくら何でも手紙やはがきをバイク便だけで全国津々浦々届けられるわけがありません。
現時点でこの判断が確定したものではなく、日本郵便の聴聞が6月18日に予定されており、その際に同社から有力な反論が出ない限り、この判断が覆されることはないとみています。
とすると売上高11兆円を超え、経常利益が1兆円のこの巨大企業の屋台骨を揺るがす大きな局面を迎えることになります。同社の社長はあの増田寛也氏です。岩手県知事、総務大臣歴任というより「地方消滅」で896の地方自治体が消滅しかねないと警鐘を鳴らした方といったほうが案外知名度的には高いかもしれません。その増田氏、地方消滅の前に地方に届ける郵便を消滅させてしまうのでしょうか?
日本郵便としては代替策を練ると思いますが、関連会社、協力会社のみならず、外部業者=同業他社との連携も取りざたされます。ただヤマトとは訴訟関係にある中、選択肢が多いわけではありません。そもそも「物流の2024年問題」で運送事業は非常にタイトな状態にあります。その中で国交省のこの判断は苦渋だと思いますが、業界大混乱、日本中の物流に影響が出ることは必至かもしれません。
もう一つは企業や個人の郵便離れを促進するだろうとみています。
カナダの郵便事業者であるカナダポストが24年11月から12月にかけて1か月間ストライキを行いました。この時期はクリスマスカードを送る時期に重なり、郵便は滞留し、パスポートやビザなどが時間内に受領できない人が続出するなど大混乱になりました。それを教訓にオンライン化が一気に進みます。私の会社を含め企業では多くの請求書業務もオンラインに切り替えたため、郵便に頼る仕組みがほぼ消えたのであります。
数週間前にカナダポストが半年前の暫定決着に不満で再びストライキに入ると予告した際には「またか!」という声が出たものの各社事前対応ができていたのか、案外落ち着いて様子を見ていましたが、組合側も「NO残業ストライキ」という一風変わった形となり、実質業務には影響が出ていません。それはカナダポストが毎年大赤字を計上しており、値上げしても値上げしても赤字が埋まらない中で従業員の給与など上げてられないという経営側と物価高の中、組合側との鋭い対立が背景なのですが、利用者無視の姿勢が結局郵便敬遠という行動に転じるわけです。
日本で「それは海の向こうの話だ」と思われては困ります。日本の郵便取扱数は2001年の262億通をピークに2023年度は136億通まで減っています。ざっと半分です。案外、郵便数を支えているのが年賀状ですが、それ以外にも時代と共に無くなりそうな郵便物は思いつきます。例えば株主総会のお知らせはその一つでしょう。あれが本当に郵便で来る必要があるのかと思うのです。私が思う一番簡単な方法は個々人が口座を持つ証券会社のネット口座に総会案内をリンクすればよいのではないかと思うのです。
また銀行の各種お知らせ郵便や動力用水会社の検針や請求書も一部はなくなりつつありますが、まだたくさん来ます。(特に東京都水道局はシステムが古すぎる!)私のように賃貸住宅の経営をすると動力用水の口座数が多いので電気、ガス、水道だけでもうんざりするほど郵便が来ていました。これもこの5年ぐらいで各社の事務効率の向上とオンライン化で半減しており、今後、各社は郵便ゼロ化を目指すのでしょう。そうなるとあと数年で郵便取扱数が100億通を下回るのではないかとみています。
つまり事業取り消しが確定したとして、5年後に日本郵政が今の体制に戻った時には多くのトラックや軽自動車は不必要になるとも言えます。そもそも今所有するそれらトラックや軽自動車、どうするのでしょうね?運送会社にリースしたり売却したりするのでしょうか?5年間保有するのはメンテと駐車場コストがかかるので維持する理由がないはずです。また運転手の業務をどうするか、つまり雇用維持問題も出てくるでしょう。
こう考えても今回の郵便車両の事業取り消しの波紋は優しい波紋ではなく、白波が立つほどの波紋であるとみています。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年6月6日の記事より転載させていただきました。