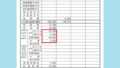国内の建設業界では、深刻な人手不足と高齢化、そして2024年から導入された時間外労働の上限規制の影響により、工事の処理能力が大幅に低下しています。その結果、建設会社が契約済みで完了していない建設工事は15兆円を超え、過去最大となっているそうです。
コレは凄いことになってきた。。。
>縮む建設業、工事さばけず 未完了が15兆円超え過去最大 – 日本経済新聞 https://t.co/TnhMn9Z1Dz
— 田端信太郎@毎朝8:45にYouTubeライブで投資情報ナマ配信 (@tabbata) June 7, 2025
とくに現場監督の不足が顕著で、職人の減少以上に深刻な課題となっており、受注ができても着工が数年後にずれ込む事例が各地で相次いでいます。
縮む建設業、工事さばけず
未完了最大級15兆円 投資に影、成長下押し
すごい額。需要は絶好調だけど全然供給能力が足りない。どんどん工事費・人件費上がるでしょうね。
それでも減り続ける人手を確保するのは至難の業出典:日本経済新聞https://t.co/4Tc6ipDbBK pic.twitter.com/NV9B5dJqYq
— 石男くん@昨日よりも面白くの建設You tuber (@Stoneman_ISHIO) June 8, 2025

west/iStock
建設業界では就業者数が減少し、高齢化も進んでいます。加齢により体力が衰える中、現場の人手確保は今後さらに困難になる見通しです。特に、大地震が起きた際にインフラや建物の復旧を担う人が不足する恐れがあり、人手不足によって当たり前だったことが当たり前でなくなる時代が近づいています。
これ、何が恐ろしいって、大地震が来た時にインフラも中々復旧しないし、建物を直してくれる人もいなくなるとこ。
人手不足で、これまでの当たり前が当たり前でなくなる。
縮む建設業、工事さばけず 未完了が15兆円超え過去最大 https://t.co/jDpX9dVrci
— 銀二 (@ksygwsh103) June 8, 2025
時間外労働の規制により、一人あたりの労働時間が減少し、現場の作業員には限られた時間でより多くの業務が求められています。しかし、建設現場は人手を要する作業が多く、生産性向上には限界があります。加えて、技能者の減少が進行中であり、円安の影響もあって外国人労働者の確保も難しくなっています。
問題は、現場施工が基本の建築では生産性向上に限界があること(やらないといけないので必要条件ではある)、現在進行系でどんどん技能者が減っていること、円レート低下で外国人労働者の確保すらも難しいこと
—-
縮む建設業、工事さばけず 未完了が15兆円超え過去最大 https://t.co/H8YFZXzJD7— マス郎(老眼) (@mansukitaleau) June 8, 2025
建物を建てたくても、人手が足りず工事が進まない時代になってきました。今見ている建物が、もしかすると最後のコンクリート建築になるかもしれません。
縮む建設業、工事さばけず 未完了が15兆円超え過去最大 – 日本経済新聞 https://t.co/FQwyZr6Rmg
作りたくても作れない時代になってきた。
目に見えるのが最後のコンクリート建築になるかもしれない。
コンサルより建設業が儲かる時代来るかもね。— のらえもん (@Tokyo_of_Tokyo) June 7, 2025
建設需要自体は旺盛で、特に設備投資を進める企業にとっては大きな機会ですが、建設会社は利益率の高い案件を優先する傾向を強めており、民間工事や公共事業の遅延も発生しています。
まだ民間工事が遅れるのは良いとして、公共事業に影響が出ると、インフラが弱くなる懸念がありますね。
縮む建設業、工事さばけず:日本経済新聞https://t.co/oGJbZ3YY6o
— ドボクヤコンサル (@digiconengineer) June 7, 2025
過去30年で建設作業員は大きく減少する一方、介護士やリハビリ職は急増していますが、その業務内容には実効性や不正請求への疑問も指摘されています。
過去30年間で建設作業員は極端に減って、一方で激増したのが介護士とリハビリです。
建設作業員はビルを作れますが、
リハビリがやっているのは寝たきり老人への形だけマッサージと不正請求です https://t.co/rDu7MJunn1— サトウヒロシ特咒サロ (@satobtc) June 8, 2025
この分析には批判的な意見もあり、国土交通省の建設工事費デフレーターによると、2015年度を100とした場合、2024年度は128を超えています。したがって、金額で議論するなら物価上昇を反映した補正が必要との指摘があります。今回も日本経済新聞の誇張された記事だと見る声もあります。
アホらしい記事。#国土交通省 が公表する #建設工事費デフレーター によれば、2015年度を100とした場合、2024年度で128を超える程度になっている。
額で見るのであれば、物価上昇分のデフレーターを考慮にいれて補正するべき。
まあ、いつもの #日本経済新聞 の「飛ばし記事」だろう。#土木 https://t.co/aHKZGrN7Uv pic.twitter.com/Pv2jJfqjg4— Takeminakata (@takeminakata_11) June 8, 2025
ゼネコンや下請け会社は、長年にわたりパワハラやカスタマーハラスメントを放置してきた結果、そのツケが今まわってきています。そんな職場環境では、若い人が建設業界に入りたいと思わないのも当然かもしれません。
ゼネコンもサブコンも長年パワハラやカスハラ黙認してきたツケが今きてんだよ
若い人なんかこの業界来ないでしょ
今さら人がいないとか騒ぐなよ https://t.co/Hfr5gAIL5I— アルルキャン (@JyuJyuyan2) June 8, 2025
建設業は日本のGDPの約5%を占める重要な産業であり、今後の経済成長やインフラの維持にとって欠かせません。AIでは代替できない仕事が多く、人手の価値がますます高まる分野でもあります。農業や建設、インフラ、介護・医療など、人の力が必要な仕事の方が、これからの時代に安定した未来があると考えられます。
今後絶対建設業は伸びると思うんですよね。AIが代替できない分野が多いから。
農業も建設業もインフラ業も、介護・医療・各種サービス業。
そっちへ転職した方が未来があると思うんだよね… https://t.co/ceQVIFf8YW— くうねると (@kuuneruto) June 8, 2025