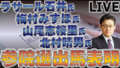黒坂岳央です。
かつては上司が部下に、教師が生徒に、問題行動に対して当たり前に注意や指摘をしていた。子供には近所の大人が注意するという場面も珍しくなかったし、筆者は実際知らない大人からいたずらをして「コラッ!」と叱られた経験がある。
だが今、世の中から「注意や指摘する人」は急速に減っている。注意は暴力という認識を超えて、今や「犯罪行為」へと変わった。こうなると誰も注意しない、いやできなくなったのだ。
これは一見すると生きやすい社会に思われるが、実際にはその逆が起きている。どんな人も必ず間違いを犯す。しかし、誰にも注意、指摘されなければ本人は行動の誤りに永遠に気づかないまま、ドンドン視野狭窄になり、思い込み、勘違いしたまま思考は硬直化。最後は人が寄り付かない「モンスター化」する。

west/iStock
注意しない社会
現代社会では、パワハラやクレームを恐れて注意を控える傾向が強まっている。
例えば、部下が問題行動をしても上司はパワハラと訴えられることを恐れて躊躇するケースが増えている。実際、そのようにパワハラだと騒ぐことで問題になってしまい、「物言わぬ上司」になってしまう人もいる。
また学校現場でも、生徒の問題行動を教師が指摘しない場面を目撃してきた。理由は保護者からクレームが入るリスクがあるからだ。
こうなると多くの人は「面倒事を回避するために注意しない」という選択を取るようになり、問題行動が放置される方向へとシフトしているのだ。
強烈な格差になる
積極的に「放置」される現代、そんなトレンドとは逆に自らフィードバックを求める人もいる。こうなると両者の間にはとてつもなく大きな格差が生じる。
成長意欲が高い人は、上司や同僚に積極的に意見を求め、自己改善を重ねていく。マーケットからの反応を真摯に受け止め、成長を続けていく。その一方、楽だから、権利を有しているからと好き勝手に振る舞う人は、問題行動を指摘されないまま長い時を過ごす。この差は、スキルや人間関係、キャリア形成、人格において決定的な影響を及ぼす。
筆者は独立前、周囲の人間から「会社やめたら誰も注意してくれないからダメ人間にならない?」と言われたことがあって、不安になったことがある。だが、そんな心配は杞憂だった。
独立するとサラリーマン時代以上に容赦なく評価され、ダメ出しされ、指摘される。記事や動画には容赦なく批判やツッコミは来るし、直接言われなくても大きく外した成果物は「アクセス数」という形で指摘が入るようになっている。
「お前のこの作品にニーズはないよ」と厳しく教えてもらえることで、毎回毎回が真剣勝負になるし、視聴者からの反応は何よりも意識が向く。
そんな生活を何年も送ることで、今やサラリーマンの時以上に自分の振る舞いを客観的に意識するようになった。この自己体験からも人は注意や指摘を受ける方が圧倒的に成長するということが分かる。
人間にはある程度の強制力が必要
人間は本質的に楽を求める生き物である。ほとんどの人は、強制力がなければ努力を怠りがちだ。「強制」と聞くと時代錯誤に感じられるかもしれないが、適切な強制力は秩序を保ち、自律を促す役割を果たす。
コロナ禍におけるリモートワークという世界規模の社会実験でもリモートワークで生産性を高める人がいる一方、「オフィス出社という強制力がないと大多数のセルフスターターでない人は労働生産性が落ちる」ということがデータドリブンの米国ITテック企業を始め明らかになったことは興味深い。
また、学校や職場というある程度の強制力があるからこそ、一人では頑張れない人もその強制力の中で仕事や学習を習慣化し、結果を出すことができる。人間はそもそもそれほど強い生き物ではない。間違いを指摘され、ある程度のプレッシャーがあることではじめて努力するし、結果にコミットできるようになる。
だが、問題行動が放置されると、成長の機会が失われるだけでなく、自己管理能力が育たないまま社会に出る人が増える。
例えば、職場で注意されないまま、上司から「戦略的放置」された若者は今後、5年、10年経って若さという魔法が解けるとマーケットニーズがなくなる。若くなくなればポテンシャルを見てもらえなくなり、プライドだけ高くて仕事ができない人材は労働市場で需要が消えてしまうのだ。
AIの使い方で広がる新たな格差
AI技術の進化も、この問題に拍車をかけている。
AIはリップサービスや共感を提供することが得意で、それに癒やしを求める人も増えているというニュースが話題になった。だが、本来は問題行動なのに「あなたはそのままでいい」と言われ続ければ、ドンドン社会性がなくなり周囲から人が離れていくと思うのだ。
たとえば、認知の歪みで物事をフラットに見られなくなれば、正しい視点へ修正した方が良いのは明らかだ。長期的には大きなつけを払うことになる。だが、そのまま長く生きて人格になればもう誰も矯正できなくなってしまう。
それがわかっているから筆者はAIに異なる役割を求めている。記事や動画、その他、自分の仕事の成果物や考え方について「多面的、建設的批判の視点でダメな点やマーケットから乖離している点をできるだけ多く指摘してください」と依頼するようにしている。
「改善しましょう」と言われると修正を余儀なくされるので大変ではあるが、目指すべきは自己成長なので厳しいダメ出しがむしろ心地良いし、リップサービスばかり続くとかえって不安になってしまう。
AIを「癒やし」に使うか「成長のツール」に使うかで、将来的な成果に大きな差が生じる。AIの使い方自体が、新たな格差の要因になり得るのだ。
◇
「注意されない社会」から脱却するには、個人と組織の両方で意識を変える必要がある。今日から簡単で無料できる具体的な策としてはAIに「自分の改善が必要な点を指摘して」と頼むことだ。しっかり頼まないと誰からも注意されない社会、そのくらいしなければモンスターになる未来が待っている。
■最新刊絶賛発売中!





![[黒坂 岳央]のスキマ時間・1万円で始められる リスクをとらない起業術 (大和出版)](https://agora-web.jp/cms/wp-content/uploads/2024/05/1715575859-51zzwL9rOOL.jpg)