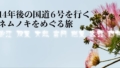ここまでAIとの対話を通じて、参政党について調査を進めてきた。その集大成として、本稿をまとめるに至った。ここに示すのは、提起した諸問題、トランプ現象との類似性、れいわ新選組との関係性などを踏まえ、それらを取り込んだかたちでAIに最終的なレポートとして作成させたものである。
序章:鏡の向こうの日本──なぜ今、参政党を論じるのか
2022年、夏の参議院議員選挙。日本の永田町を、一つの「事件」が揺るがした。 大手メディアの予測を覆し、結党からわずか2年余りの政治団体「参政党」が、比例代表で議席を獲得し、国政政党の仲間入りを果たしたのだ。その得票数は、176万票を超えていた。
彼らの選挙戦は、異様とも言える熱気に満ちていた。全国各地で開かれた街頭演説会には、既存政党のそれとは比較にならないほどの人々が詰めかけた。そこに集うのは、旧来の政治活動家とは明らかに雰囲気の異なる、子連れの母親たち、健康意識の高い若者、そして、これまでの政治に静かな絶望を抱いてきたであろう、ごく普通の人々の姿だった。彼らは候補者の言葉に熱心に耳を傾け、メモを取り、まるで質の高いセミナーに参加しているかのようだった。
この現象を、既存の政治ジャーナリズムは、いくつかの便利な言葉で片付けようとした。「ネットを駆使した右派ポピュリズム」「陰謀論に支えられたカルト的な集団」──。たしかに、それらは参政党の一側面を捉えているかもしれない。しかし、176万もの人々が投じた一票の重みを、それだけの言葉で説明し尽くせるほど、日本の現実は単純なのだろうか。
レッテルを貼ることは、思考を停止させる最も簡単な方法だ。だが、そのレッテルを剥がし、現象の奥深くを覗き込むことをしなければ、私たちは時代が発する、最も重要なシグナルを見逃すことになる。本書の目的は、まさにそこにある。参政党という「鏡」を通して、現代日本、そして世界の深層で起きている地殻変動を解き明かすことだ。
本書が提示する視座は明確である。 参政党の台頭は、日本列島だけで起きた孤立した現象ではない。それは、2016年にドナルド・トランプを大統領に押し上げ、英国にEU離脱を決断させ、ヨーロッパ大陸に右派ポピュリズムの嵐を吹き荒れさせた、あの世界的な政治潮流の、紛れもない日本版なのである。
グローバル化に取り残された人々の不満。自国のアイデンティティが失われることへの恐怖。エリート層や大手メディアに対する根深い不信感。そして、「自分たちの国のことは、自分たちで決めたい」という、素朴で、しかし強烈な主権回復への渇望。 本書は、この世界共通の「病理」と「願い」が、いかにして「参政党」という、日本独自の処方箋を生み出したのかを解き明かしていく。
そのために、まず第1章で、この世界的な潮流と、日本の「失われた30年」が生んだ特有の社会不安、そしてその不安の受け皿たりえなかった「既成政党の機能不全」という、参政党が生まれるべくして生まれた日本の「土壌」を分析する。
続く第2章では、SNSとリアルを融合させた、世界標準のポピュリスト戦略としての「参政党の戦い方」を解剖する。
第3章では、彼らの思想の核心に迫る。そこでは、作家・橘玲氏が描く冷徹なグローバル資本主義の世界観への、情念的なアンチテーゼとしての参政党の姿、そして「中国との対峙」という強力な旗印の意味を明らかにするだろう。
さらに第4章では、比較対象として「れいわ新選組」を取り上げる。なぜ、同じ「反エスタブリッシュメント」という水源から出発しながら、彼らは「右」と「左」、二つの異なる流れに分岐したのか。両党を比較することで、日本のポピュリズムの全体像を炙り出す。
続く第5章では、参政党の特異な支持層を解剖し、その成功が内包する「時限爆弾」、すなわち、カリスマ的指導部と新たに誕生するエリート議員との間に予測される深刻な軋轢について論じる。
そして最終章では、思考実験として「もし参政党が政権を取ったら、日本はどうなるか」をシミュレーションし、この運動が私たちの未来に投げかける、光と影を具体的に描き出す。
参政党を支持する者も、あるいは、その主張に強い危機感を抱く者も、もはやこの存在を無視することはできない。彼らは、好むと好まざるとに関わらず、現代日本が直面する「国家とは何か」「国民とは何か」「豊かさとは何か」という、根源的な問いを、私たち全員に突きつけている。
さあ、ページをめくってほしい。鏡の向こうに映る、あなたがまだ知らない日本の姿と、向き合うために。
第1章:世界の潮流と日本の土壌──参政党、誕生の必然
いかなる政治運動も、真空から生まれることはない。それは、時代の空気と、それが生まれる国特有の土壌、そして人々の心に静かに降り積もった、言葉にならない渇望が化学反応を起こした時に、初めて姿を現す。
2022年の夏、日本に突如として現れたかに見えた参政党という現象もまた、例外ではない。
彼らを理解するためには、まず、彼らが誕生する「前夜」の世界と日本が、どのような「病」に侵されていたのかを診断する必要がある。一つは世界を覆った急性の「熱病」であり、もう一つは日本を蝕む慢性の「持病」である。
本章では、この二つの病巣を解き明かすことで、参政党がなぜ、そして、いかにして生まれなければならなかったのか、その必然性に迫りたい。
第一節:世界を覆う「熱病」──冷戦後秩序の崩壊と、忘れられた人々の反乱
1990年代、冷戦の終結と共に、世界は楽観的なムードに包まれた。自由民主主義とグローバル資本主義が最終的な勝利を収め、世界は一つに繋がることで、永続的な平和と繁栄が訪れる──。そんな「歴史の終わり」さえ語られた時代だった。
しかし、その輝かしい未来像の裏側で、静かに、しかし確実に、病原体は増殖していた。 グローバリゼーションという名の奔流は、国境を越える巨大資本や、高度な専門知識を持つ「グローバル・エリート」層に、莫大な富をもたらした。
一方で、先進国の国内では、かつて国の屋台骨を支えていた製造業が、安価な労働力を求めて海外へと流出し、中間層は痩せ細り、賃金は停滞した。自分たちの暮らしは一向に良くならないのに、テレビの中の経済学者や政治家たちは「グローバル化は不可逆だ」と繰り返す。その言葉は、まるで自分たちの苦しみを無視する、冷たい響きを伴って、多くの人々の耳に届いていた。
この蓄積された不満と疎外感という「熱」が、最初に劇的な症状として噴出したのが、2016年である。 英国では、国民が「主権を取り戻す」というスローガンの下、エリート層の予測を覆してEU離脱(ブレグジット)を決定。米国では、不動産王ドナルド・トランプが「アメリカを再び偉大にする」と叫び、ラストベルト(錆びついた工業地帯)の忘れられた人々の熱狂的な支持を受け、大統領の座に就いた。
彼らの戦術は驚くほど共通していた。敵は、もはやソ連のような具体的な国家ではない。彼らが「敵」として設定したのは、国境を曖昧にし、自国の富を吸い上げ、伝統的な文化や価値観を破壊する、顔の見えない「グローバリズム」と、それを推進する国内外の「エリート層」、そして彼らの代弁者である「大手メディア」だった。
この反乱は、西洋社会の根幹を揺るがした。そしてこの潮流は、一過性の熱病では終わらなかった。2025年の今、世界が再び直面している米国の保護主義的な動きや、欧州各地で続くナショナリズムのうねりが示すように、それはもはや「病」ではなく、世界の政治・経済を規定する「新しい常態」となった。
それは、もはや「右か左か」という旧来の政治対立ではない。「グローバルか、ナショナルか」「エリートか、大衆か」という、まったく新しい分断線の出現であり、参政党が生まれる、世界的な「気候」がここに整ったのである。
第二節:日本の「持病」──三十年の停滞と、静かに蓄積した不安
世界がこのような激しい熱病に浮かされていた頃、日本は異なる病に静かに蝕まれていた。それは、熱狂や反乱とは無縁の、しかし身体の芯まで冷え切らせるような、「慢性的で、終わりの見えない停滞」という持病である。
バブル経済の崩壊後、日本は「失われた30年」と呼ばれる長いトンネルに入った。かつての「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の輝きは色褪せ、終身雇用や年功序列といった、国民の生活を支えてきた社会の仕組みは崩壊。非正規雇用が増大し、2025年の今日に至るまで、実質賃金の伸び悩みは国民生活に重くのしかかり続けている。若者は未来に希望を描けず、中高年は自らの生活を守るのに精一杯となった。
政治は、その絶望に応えることができなかった。この政治的な「無風状態」の水面下で、既存の政党が全く光を当ててこなかった、新しい種類の「不安」が、マグマのように蓄積していたのである。
- 「食」への不安:食料自給率の低さ、輸入野菜の農薬、食品添加物、遺伝子組み換え作物…。毎日口にする食べ物が、本当に安全なのか。自分たちの子供たちに、安心して食べさせられるものは何か。国家や大企業は、国民の健康よりも、経済効率を優先しているのではないか。
- 「健康」への不安:西洋医学や製薬会社への不信感、ワクチンへの懐疑心。病気は、医者や薬に頼るのではなく、自らの免疫力や食生活で改善すべきではないか。国際的な保健機関(WHOなど)の指針は、本当に私たちのためになっているのか。
- 「教育」への不安:子供たちは、日本の歴史や文化に誇りを持てるような教育を受けているのか。ジェンダーフリーなど、海外から入ってくる新しい価値観は、日本の伝統的な家族観を壊してしまうのではないか。
これらの不安は、従来の政治的な争点(経済成長率、安全保障、社会保障費など)とは、まったく質の異なる、「私たちの身体と、心と、子供たちの未来は、得体の知れない大きな力に乗っ取られようとしているのではないか」という、極めて根源的で、生活実感に根差した恐怖だった。
第三節:機能不全に陥った「受け皿」──既成政党が生んだ“政治的空白”
日本社会にこれほどの「不安」が蔓延していたとしても、本来であれば、それを受け止め、解決策を示すのが政党の役割である。しかし、2020年代初頭の日本の政党政治は、国民の絶望的なまでの期待不全の中にあった。与党も野党も、国民が本当に求めている声に応えられない「機能不全」に陥り、そこに巨大な“政治的空白”が生まれていた。
- 1.巨大与党(自民党)の「魂」の喪失
- 「古い自民党」の問題:長年の派閥政治と、後を絶たない「政治とカネ」の問題は、国民に根深い政治不信を植え付けた。
- 「新しい自民党」の問題:より深刻なのは、自民党自身の「変質」である。グローバル経済の要請に応え、多様性などのリベラルな価値観に配慮するあまり、本来の支持基盤であった保守層が最も大切にする「日本の国柄」「伝統」「国家としての誇り」といった“魂”の部分を、ないがしろにしてきた。対中政策における経済界への配慮も、多くの保守層に「弱腰」と映った。結果、自民党は「もはや真の保守政党ではない」と考える、行き場のない「失望した保守層」を大量に生み出した。
- 2.野党第一党(立憲民主党など)の「身体」の無視
- 批判勢力の限界:旧来の野党は、「批判ばかりで対案がない」と見なされ、政権担当能力への期待を失わせて久しい。安全保障や経済政策において、多くの国民が抱くリアリズムと乖離した主張は、支持の広がりを自ら阻害してきた。
- 内向きの支持層:さらに致命的だったのは、彼らの支持基盤が労働組合や特定のリベラル市民層に偏るあまり、国民全体の関心事から遊離してしまったことだ。彼らが人権やイデオロギーを語る一方で、参政党が取り込んだ、名もなき普通の人々が抱える「食は安全か」「健康は守られるか」といった“身体”の不安は、彼らの政治的アジェンダには全く入っていなかった。
- 結論:“魂”と“身体”の受け皿の不在
- こうして、自民党は「保守層の魂」を、野党は「生活者の身体」を、それぞれ置き去りにした。
- まさにこの、「魂(伝統・国守り)」と「身体(食・健康)」の両方の不安に応える政党が、どこにも存在しないという、巨大な政治的空白こそが、参政党ブームを必然たらしめた最大の要因である。「自分たちの声を聞いてくれる政党が、どこにもない」──そう感じた人々にとって、両方の不安に応えると主張する参政党の登場は、砂漠でオアシスを見つけたかのような衝撃だったのである。
第四節:参政党の源流──「大和心」と「DIY精神」の合流
世界の「気候」が整い、日本の「土壌」が耕され、そして既成政党が「政治的空白」を生み出した。しかし、種は自然には蒔かれない。そこには、明確な意志を持った「種を蒔く人」が存在した。参政党という、一見すると寄せ集めにも見える組織は、いかにして生まれ、どのような思想的バックボーンを持っていたのか。その源流は、二つの異なる流れの合流点に求めることができる。
源流その1:神谷宗幣氏と「龍馬プロジェクト」という政治インフラ
参政党の創設者であり、事務局長の神谷宗幣氏は、元々は吹田市議会議員であった。彼は、既存政党の枠組みに飽き足らず、2010年に「龍馬プロジェクト全国会」を立ち上げる。これは、全国の若手の地方議員や経営者、社会活動家などを超党派で集め、「日本の将来を自分たちの手で切り拓く」という志を共有するための、一種の「政治的プラットフォーム」あるいは「私塾」であった。
この龍馬プロジェクトの10年以上にわたる活動は、後の参政党にとって、以下の三つの重要な基盤を提供した。
- 全国的な人的ネットワーク:北海道から沖縄まで、志を同じくする地方議員や活動家のネットワークが、参政党の地方組織の立ち上げや、選挙活動の際の中核となった。
- 「DIY(Do It Yourself)」精神の醸成:「誰かにやってもらうのではなく、自分たちでやる」というDIYの精神は、龍馬プロジェクトの根幹であり、そのまま参政党の「参加型民主主義」という理念に引き継がれた。
- 思想の共有と深化:定期的な勉強会を通じて、「日本の歴史や伝統(大和心)を尊重する」「中央集権的な官僚支配からの脱却」「地域からの国づくり」といった、後の参政党の思想的骨格が、時間をかけて醸成されていった。
源流その2:各分野の「専門家」ボードメンバーの合流
神谷氏が築いたこの「政治インフラ」に、それぞれの分野で、既存システムへの強い問題意識を持つ「専門家」たちが合流することで、参政党の思想は、より多角的で、具体的な政策の肉付けを得ることになる。
-
- 松田学氏(元財務官僚):財務省の緊縮財政路線を内部から見てきた経験に基づき、「財政破綻論は嘘だ」と断じる。彼の参加は、参政党の「積極財政」という経済政策に、理論的な権威を与えた。
- 吉野敏明氏(歯科医師):現代医療や食の安全性に強い警鐘を鳴らし、「医・食・農」は一体であるべきだと主張。彼の参加は、参政党の最も特徴的な政策である「食と健康」のテーマを確立させた。
- 赤尾由美氏(実業家):「日本の国柄」や「皇統の維持」を訴え、伝統的な保守の価値観を代弁。彼女の存在は、党のアイデンティティを、日本の歴史と伝統に深く根差したものにした。
このように、参政党とは、神谷宗幣氏が長年かけて作り上げた「DIY精神を持つ、全国的な草の根ネットワーク」というプラットフォーム(土台)の上に、各分野の専門家が持つ「反エスタブリッシュメント的な思想と政策」というコンテンツ(種)が蒔かれることによって誕生した、極めてハイブリッドな組織なのである。
彼らの思想は、決して一夜にして生まれたものではない。それは、日本の片隅で、既存の政治に絶望し、しかし国を憂う人々が、10年以上の歳月をかけて、静かに、しかし着実に培ってきたものだったのだ。
第2章:参政党の戦略書──日本的アクセントのグローバル戦略
好都合な気候が生まれ、栄養豊富な土壌が広がっていたとしても、種が勝手に芽吹き、大樹に育つことはない。そこには、土を耕し、水をやり、雑草を抜く、巧みな農夫の存在が不可欠である。
第1章で、私たちは参政党が生まれるための世界的な「気候」と、日本特有の「土壌」を分析した。本章では、参政党が、いかにしてその土壌に種を蒔き、支持者という作物を育て上げていったのか、その極めて洗練された「農法」──すなわち、彼らの戦略を解剖していく。
彼らの戦略は、決して思いつきの素人芸ではない。それは、世界中のポピュリストたちが実践し、成功を収めてきた「標準的プレイブック」を忠実に実行しつつ、そこに、日本人の心性に訴えかける、巧みなアクセントを加えた、高度な政治技術なのである。
第一節:「敵」の創造という技術──ポピュリストの第一手
ポピュリズムが、大衆の心を掴むために、まず初めに行うこと。それは、シンプルで、分かりやすく、そして憎みやすい「敵」を創造することだ。国民を「清廉で、勤勉で、虐げられている私たち」と定義し、それに対置する「腐敗し、怠惰で、私たちから搾取する彼ら」という構図を作り上げる。この手法は、人々の不満や不安に、具体的な「宛先」を与えることで、複雑な社会問題を、単純な善悪の物語へと転換させる、強力な麻薬である。
この点において、参政党は、世界のポピュリストの教科書を、一字一句違わず実行している。彼らが設定した「敵」のリストは、明確だ。
- グローバリスト:国境を越えて利益を追求する国際金融資本、多国籍企業、そしてそれに追随する政治家たち。日本の富を海外に流出させ、国民の生活を破壊する元凶として描かれる。
- 官僚機構:特に財務省を筆頭とする、緊縮財政を信奉し、国民への投資を怠る「既得権益の塊」。
- 大手メディア:国民に真実を伝えず、エリート層に不都合な情報を隠蔽する「支配層のプロパガンダ機関」。
- 医療・製薬利権:国民の健康よりも、自らの利益を優先する巨大な産業複合体。
このリストを見れば、既視感を覚えるはずだ。ドナルド・トランプが「ディープステート(闇の政府)」「フェイクニュース」と叫び、ヨーロッパの右派が「ブリュッセルの官僚」を攻撃したのと、その構造は全く同じである。
「悪いのは、あなたではない。あなたから奪っている、あの『敵』なのだ」──。この単純明快なメッセージが、先行きの見えない不安の中にいた人々の心に、どれほど力強く響いたかは、想像に難くない。
第二節:デジタル時代の「教会」──メディアに依存しない「信空間」の構築
「敵」を設定した次にポピュリストが目指すのは、その「敵」である大手メディアを通さずに、大衆と直接繋がるための、独自のコミュニケーション・チャネルを確立することだ。新聞やテレビへの信頼が地に落ちた現代において、この戦略は絶大な効果を発揮する。
参政党は、この点において、日本のどの政党よりも巧みであった。彼らが築き上げたのは、単なる情報発信ツールではない。それは、外部の批判や情報を遮断し、内部の結束と信仰を強化する、いわばデジタル時代の「教会」であり、独自の「信空間(しんくうかん)」とでも呼ぶべき生態系である。
- YouTubeという「説教壇」:彼らの主戦場は、一貫してYouTubeだ。ボードメンバーによる1時間を超える長尺の演説や勉強会は、単なる政策アピールではない。それは、複雑な世界を分かりやすく解説し、進むべき道を示す「教祖」から、熱心な「信徒」への「説教」の構造を持つ。視聴者は、候補者の言葉に頷き、コメント欄で信仰を告白し、一体感を醸成していく。
- プラットフォームの使い分け:YouTubeに加え、より熱心な支持者が集うニコニコ動画の有料チャンネルでは、さらに踏み込んだ「秘儀」が伝授される。X(旧Twitter)では、教義の要約が拡散され、動員が呼びかけられ、「敵」への攻撃が行われる。この重層的なメディア戦略が、信空間の強度を、日に日に高めていくのだ。
この閉じた空間の中では、党の教義は絶対の真理として共有され、外部からの批判は、すべて「敵であるメディアによる不当な攻撃」として解釈される。この構造が、いかなるスキャンダルや批判にも揺るがない、強固な支持層を形成する源泉となっている。
第三節:「身体」の政治学──グローバリズムから「オーガニック給食」へ
参政党の戦略において、最も独創的で、そして日本社会の深層を突いたのが、この第三の技術である。それは、「抽象的な政治イデオロギー」を、「具体的な身体感覚の危機」へと翻訳する、驚くべき手腕だ。
「反グローバリズム」や「緊縮財政反対」といった抽象的なスローガンは、人々の頭では理解できても、心を、そして身体を直接動かすには、力が弱い。多くの人は、それを「自分ごと」として感じられない。
そこで、参政党はこう語りかける。 「グローバリストや、彼らと結託した政府が、あなたの身体、そしてあなたの子供たちの身体を、直接蝕んでいるのですよ」と。
- 抽象的な敵(グローバリズム) → 具体的な脅威(あなたの身体への危機)
- 食料自給率の低下 → 輸入小麦の農薬、危険な食品添加物
- 医療利権 → ワクチンの危険性、不必要な薬の投与
- 教育のグローバルスタンダード → 日本の伝統を破壊するジェンダーフリー教育
この翻訳は、絶大な効果を持つ。政治の問題が、「憲法9条をどうするか」という高尚な議論から、「明日の給食に、我が子は何を食べさせられるのか」という、母親の腹の底から湧き上がるような、根源的で、拒否しようのない不安へと転換されるからだ。
この「身体の政治学」こそが、参政党が、従来の保守政党が決して取り込めなかった、政治に無関心だったはずの女性や若者、子育て世代を、新たな支持者として獲得できた、最大の要因なのである。
「敵」を創造し、独自の「教会」を築き、そして人々の「身体」に直接訴えかける。この三位一体の戦略によって、参政党は、日本の政治に空いていた巨大な空白地帯に、確固たる橋頭堡を築くことに成功した。彼らの思想そのものを理解するためには、まず、この恐るべき戦略の巧みさを、私たちは直視しなければならない。
第3章:掲げる思想──「日本を取り戻す」というナラティブ
第2章で解剖したように、参政党の戦略は極めて高度で、現代的である。しかし、いかに優れた戦略も、それが伝えるべき「物語(ナラティブ)」が人々の心を捉えなければ、空虚な技術論に終わる。彼らの真の強さは、その戦略の根底に、現代日本人の不安と渇望に寄り添う、シンプルで、しかし力強い「思想」を据えている点にある。
本章では、参政党が支持者に向けて語りかける、その核心的な思想──すなわち、「日本を取り戻す」という壮大な物語──の内実に迫りたい。そして、その物語が、なぜ現代においてこれほどまでに魅力的に響くのかを、作家・橘玲氏が描く世界観との対比を通して、深く考察する。
第一節:奪われた「国」というグランド・ナラティブ
参政党が提示する世界観の根幹は、一つの「神話」から始まる。
それは、「かつて日本は、美しい伝統と誇り高い歴史、そして国民の健康と安全が守られた、素晴らしい国だった。しかし、戦後の歩み、特にグローバル化が進んだこの30年で、その主権、文化、そして私たちの身体さえもが、外国勢力や、彼らと結託した国内の支配層(第2章の『敵』)によって奪われてしまった」という物語だ。
この物語において、現状は「本来あるべき姿から逸脱した、異常な状態」として描かれる。そして、党の目的は、その失われたものを取り戻し、日本を「本来の姿」へと回帰させる、という極めて明快なものとなる。
この「奪われた日本を取り戻す」というグランド・ナラティブは、支持者に対して、以下の三つの強力な心理的効果をもたらす。
第一に、現状の漠然とした不安に対して「原因はこれだったのか」という、分かりやすい「診断」を与える。第二に、「グローバリスト」や「メディア」といった、憎むべき「敵役」を明確にする。そして第三に、支持者自身を、国を取り戻すための戦いに参加する「物語の主人公」へと昇格させるのである。
第二節:「日本を取り戻す」ための三本の矢
では、具体的に何が「奪われ」、何を「取り戻す」べきだと彼らは主張するのか。その思想は、大きく三つの柱(三本の矢)に集約される。
第一の矢:食と健康の主権 これは、彼らの思想の最も特徴的な部分であり、第2章で述べた「身体の政治学」の理論的支柱である。彼らは、国民の健康が、グローバルな製薬会社や食品メジャー、そしてWHOのような国際機関の利益のために、危険に晒されていると主張する。 「食の安全基準」「医療の選択の自由」は、国家が自らの責任で決定すべき最重要事項であり、グローバル・スタンダードに合わせる必要はない、と。この「健康主権」という考え方は、ブレグジットを推し進めた「Take Back Control(主権を取り戻せ)」というスローガンと、根を同じくする。それは、統治の対象を、経済や法律から、より根源的な「生命」そのものへと引き寄せた、新しい主権回復運動なのである。
第二の矢:教育と文化の主権 参政党は、日本の子供たちが、自国の歴史や神話に誇りを持てないような「自虐史観」に基づいた教育を受けていると批判する。そして、ジェンダーフリー教育などを、伝統的な家族観を破壊する「外国からの価値観の押し付け」だと断じる。 これは、アメリカで激しく繰り広げられる「文化戦争(カルチャー・ウォー)」の日本版に他ならない。国家のアイデンティティを、教育と文化の領域で「防衛」し、取り戻そうとする戦いである。彼らが掲げる「伝統」とは、この文化戦争における、最も重要な武器なのだ。
第三の矢:安全保障と外交の主権 この文脈で、参政党が最大の「外部の脅威」として名指しするのが、中国共産党である。彼らは、経済的な結びつき(土地買収や技術流出など)や、政治的な浸透工作によって、日本の主権が内側から侵食されていると、強い警告を発する。 この明確な「外部の敵」を設定することは、国内の「私たち日本人」という一体感を醸成し、より強い国家、すなわち「自主防衛」や「対中強硬姿勢」を正当化する、強力なロジックとなる。これもまた、世界の右派ポピュリストが共通して用いる、古典的で、しかし極めて効果的な手法である。
第三節:「温かい共同体」か「冷徹な現実」か──橘玲との対話
参政党が掲げるこの「日本を取り戻す」という物語は、なぜこれほどまでに人々の心を惹きつけるのか。その答えは、現代日本を冷徹に分析する作家・橘玲氏の世界観と比較することで、より鮮明に浮かび上がる。
橘玲氏がその著作で繰り返し描くのは、グローバル化によって、日本の伝統的な社会システム(終身雇用、年功序列など)が崩壊し、誰もが「知能」と「金融資産」を武器に、自己責任で生き抜くしかない、という「残酷で、冷徹な現実」だ。そこでは、国家や共同体はもはや個人を守ってくれず、剥き出しの個人が、世界規模の競争に晒される。
参政党が提供する世界観は、この「橘玲ワールド」への、全身全霊の、情念的なアンチテーゼなのである。
- 橘玲が「世界標準の競争を生き抜け」と説くのに対し、参政党は「グローバル化の奔流から身を守る、日本のための防波堤を築こう」と呼びかける。
- 橘玲が「頼れるのは自分だけだ」と突き放すのに対し、参政党は「私たち『日本人』という仲間がいる」と、共同体の温かさを提示する。
- 橘玲が「残酷な現実を直視せよ」と合理性を求めるのに対し、参政党は「誇り高い物語を信じよう」と、精神的な高揚感を提供する。
つまり、参政党の思想の核心にあるのは、冷徹な個人主義と自己責任の社会に疲弊し、そこから逃れたいと願う人々に対する、「大丈夫、ここにはまだ、温かくて、誇り高い、守られた共同体がある」という、甘美で力強いメッセージなのだ。
彼らが掲げるナショナリズムとは、単なる排外主義ではない。それは、グローバル資本主義という、顔の見えない怪物に怯える人々が、最後にたどり着いた「精神的な安全保障」の形なのである。
第4章:日本のポピュリズム──なぜ「参政党」と「れいわ新選組」は同じコインの裏表なのか
参政党という現象を、日本政治の文脈で、より立体的に理解するためには、どうしても避けて通れない比較対象が存在する。それは、同じく2019年の参院選で国政に登場し、熱狂的な支持層を形成した、「れいわ新選組」である。
一見すれば、両党は水と油だ。参政党が「伝統」や「国守り」を掲げる「右派」であるのに対し、れいわは「弱者救済」や「多様性」を訴える「左派」に見える。しかし、その表面的なイデオロギーの化粧を剥がし、その戦術、支持層の熱量、そして既存政治への対決姿勢という「骨格」を分析したとき、私たちは驚くべき事実に直面する。
それは、参政党とれいわ新選組は、敵対する双子であり、同じ「反エスタブリッシュメント・ポピュリズム」というコインの、裏と表にすぎないということだ。
本章では、この両党を徹底的に比較することで、現代日本のポピュリズムの全体像を炙り出し、なぜ同じ水源から、二つの異なる流れが生まれたのかを解き明かす。
第一節:驚くべき「戦術」のシンクロニシティ
もし、党の名前を隠して両党の活動を観察すれば、その戦術が驚くほど酷似していることに気づくだろう。
- カリスマ的リーダーへの依存:参政党が神谷宗幣氏という絶対的な「教祖」を中心に動いているように、れいわもまた、山本太郎代表という、比類なき演説能力とカリスマ性を持つリーダーの存在が、党の求心力のすべてである。両党ともに、もしこのリーダーを失えば、党の存続が危ぶまれるという、極めて脆弱な構造を共有している。
- 反エスタブリッシュメントという「共通の敵」:参政党が「グローバリスト」「大手メディア」を敵とするならば、れいわは「資本家」「緊縮財政派の政治家・官僚」を敵とする。呼び名は違えど、「国民から搾取し、真実を隠蔽する、腐敗した支配層」という敵の構造設定は、全く同じだ。
- SNSと街頭演説という「両輪」:両党ともに、既存メディアを「敵」と見なし、YouTubeやSNSを駆使して支持者と直接繋がる。そして、オンラインで醸成した熱を、リアルの街頭演説会で爆発させる。山本太郎の「辻立ち」と、神谷宗幣の「街頭演説」は、その手法と熱量において、鏡写しのように似ている。
- 熱狂的なボランティア組織:両党の活動は、金銭的な見返りを求めない、熱心なボランティアによって支えられている。彼らは、単なる支持者ではなく、自らが「党を動かしている」という強い当事者意識を持つ「信徒」であり、このボランティア組織の有無こそが、他の第三極政党と彼らを分かつ、決定的な違いとなっている。
第二節:響き合う「経済政策」──MMTという福音
さらに驚くべきは、イデオロギー的には対極に見える両党が、経済政策において、奇妙なほど響き合っている点だ。
れいわ新選組が「消費税廃止」と「積極財政」を掲げ、政府が通貨発行権を用いて、国民生活に大胆な投資を行うべきだと主張するのは周知の通りだ。 一方、参政党もまた、「緊縮財政は財務省のプロパガンダだ」と断じ、政府はもっと国債を発行して、国内のインフラや産業に投資すべきだと訴える。
両者の主張の根底にあるのは、「国債は、国民の借金ではない。政府は、自国通貨建てである限り、財政破綻することはない」という、現代貨幣理論(MMT)に近い考え方だ。
これは、日本の政治における、極めて重要な地殻変動を示している。これまで「財政規律」を金科玉条としてきた自民党や、それを批判するにしても「無駄の削減」を訴えるのが常だった旧来の野党とは全く異なる、「もっと金を使え」という新しい経済思想が、「右」と「左」の両翼から、同時に立ち上がっているのだ。
「失われた30年」の閉塞感の中で、もはや「痛みを伴う改革」や「我慢」では未来はないと感じる国民にとって、この「打ち出の小槌」のような経済思想は、左右のイデオロギーを超えて、強力な福音として響いているのである。
第三節:なぜ「右」と「左」に分岐したのか──「喪失の物語」と「党名の矛盾」
同じ水源から出発しながら、なぜ彼らは、二つの異なる川となって流れていったのか。その分岐点を決定づけたのは、第一に「私たちは、エスタブリッシュメントに、何を奪われたのか」という、その「喪失の物語」の違いである。
- れいわ新選組の物語:「経済的な豊かさと尊厳を奪われた」 れいわが語るのは、新自由主義的な経済政策によって、非正規雇用に突き落とされ、障害や病気によって社会の片隅に追いやられ、「人間としての最低限の暮らしと尊厳」を奪われた人々の物語だ。彼らにとっての救済は、国家による徹底的な「再分配」と「弱者救済」である。その思想は、必然的に「左派」へと向かう。
- 参政党の物語:「精神的な誇りと共同体を奪われた」 参政党が語るのは、グローバル化と戦後教育によって、「日本人としての誇り、美しい伝統、そして安全な食や健康が保障された共同体」を奪われた人々の物語だ。彼らにとっての救済は、国家による「伝統文化の復興」と「外部の脅威からの防衛」である。その思想は、必然的に「右派」へと向かう。
片や「パン(経済)の喪失」を、片や「魂(文化)の喪失」を嘆く。 この、どちらも現代日本が抱える、紛れもない「喪失感」に根差しているからこそ、両党は、それぞれの支持者にとって、抗いがたい魅力を放っているのだ。
そして、この分岐をさらに決定的なものにしているのが、第二の要因、すなわちれいわ新選組の党名そのものに横たわる、歴史的な「矛盾」である。
「新選組」──。この言葉を聞いて、多くの日本人が思い浮かべるのは、幕末の京都で、徳川幕府のために、反幕府勢力、すなわち「尊王攘夷」を掲げる志士たちを、容赦なく斬り捨てた武装警察組織の姿だろう。彼らの忠誠は、あくまで「徳川将軍家」に向けられていた。そして、戊辰戦争の最終局面において、彼らは天皇の軍を示す「錦の御旗」を掲げた新政府軍と戦い、「朝敵(ちょうてき)」、つまり天皇の敵と見なされた存在である。
ここに、深刻なねじれが生じる。 山本太郎代表が率いる「れいわ新選-選組」は、現代の「エスタブリッシュメント」である自民党政権を、徳川幕府になぞらえ、自らをそれに立ち向かう「幕末の志士」のように位置づけている。支持者の多くも、その比喩を抵抗なく受け入れているだろう。
しかし、歴史や伝統を重んじる保守的な視点を持つ人々、特に「皇統の維持」や「国体」といった概念に強いこだわりを持つ層から見れば、これは単なる比喩では済まされない。「天皇の敵であった組織の名前を、なぜ堂々と党名に掲げるのか」という、根本的な違和感と不信感に繋がるのだ。
彼らにとって、この党名は、歴史に対する無理解、あるいは意図的な無視と映る。「反エスタブリッシュメント」という姿勢には共感できても、「朝敵」の名を冠する党を支持することは、自らの信条に反する。
ここに、参政党が持つ「受け皿」としての強みが現れる。 参政党は、その思想の核に「皇統の維持」「日本の国柄」「神話からの歴史教育」といった、徹底した「尊王」的な価値観を据えている。
つまり、「既存政治にはうんざりだが、日本の伝統や皇室は深く敬愛している」という層にとって、れいわ新選組の党名が持つ「歴史的瑕疵(かし)」は、彼らを支持できない決定的な理由となる。そして、その層が「反エオリタ」の思いを託せる、もう一つの選択肢を探した時、思想的に「クリーン」で、むしろ自分たちの価値観を純粋培養したかのような参政党が、完璧な受け皿として、そこに存在しているのである。
れいわ新選組の党名が持つこの「矛盾」は、無意識のうちに、本来であれば取り込めたはずの、右派的なポピュリズムに親和性を持つ層をフィルタリングし、結果として、その一部を参政党へと向かわせる、一つの大きな要因となっているのだ。
第5章:支持層の解剖と未来への「時限爆弾」──誰が参政党を支え、何が彼らを壊すのか
参政党の躍進を分析する上で、多くの専門家が首を傾げるのが、その支持層の構造である。従来の選挙分析で用いられる「無党派層」という言葉では、彼らの実像を捉えることはできない。なぜなら、参政党が取り込んでいるのは、政策を比較検討して投票先を決める浮動票ではなく、それとはまったく異なる、二つの特殊な層だからだ。
本章では、この特異な支持層を解剖し、その強さの源泉を探る。そして同時に、まさにその成功が、党の未来に「時限爆弾」を仕掛けているという、深刻な内部矛盾について論じたい。
第一節:誰が参政党を支えるのか──「目覚めた無関心層」と「失望した保守層」の融合
参政党の支持基盤は、大きく分けて、水と油ほど異なる二つの層のハイブリッドで構成されている。
1.「目覚めた」無関心層
これは、これまで政治に全く関心がなかった、あるいは政治を汚いものとして敬遠してきた層である。特に、都市部の子育て世代の女性や、健康・自然派志向の若者に多い。彼らを「目覚め」させたのは、第2章で分析した「身体の政治学」だ。
- なぜ目覚めたのか:「憲法改正」や「財政政策」といった抽象的なテーマには、彼らの心は動かなかった。しかし、「子供たちが食べる給食の安全性」「毎日使うシャンプーの成分」「強制されるかもしれないワクチンの是非」といった、自らの身体と家族の安全に直結するテーマが、初めて彼らにとっての「政治」となった。
- 彼らの動機:イデオロギーではなく、「生活防衛」であり「生命の探求」である。彼らにとって参政党は、政党というより、真実の健康情報や、安全な生き方を教えてくれる「学びのコミュニティ」に近い。
2.「失望した」保守層
これは、本来であれば自民党を支持してきた、あるいはそれ以上に右派的な思想を持つ保守層である。彼らは、長年、自民党の「リベラル化」に不満を募らせてきた。
- なぜ失望したのか:「グローバルな価値観に屈し、日本の伝統や誇りを軽んじている」「中国に対して弱腰すぎる」「財務省の言いなりで、大胆な国家経営ができていない」。彼らの目には、自民党はもはや真の保守政党ではなく、既得権益を守るだけの「現状維持勢力」に映っている。
- 彼らの動機:「真の日本を取り戻したい」という、強いイデオロギーである。参政党の掲げる「国守り」「歴史教育の見直し」「対中強硬姿勢」は、彼らが自民党に感じていた不満への、直接的な答えとなっている。
参政党の巧みさは、本来であれば交わることのない、この二つの層を「反グローバリズム、反エスタブリッシュメント」という共通の敵を設定することで、一つの大きなエネルギーの塊へと「融合」させた点にある。
第二節:未来への時限爆弾──「エリート新人議員」と「カリスマ代表」の軋轢
この特異な支持構造は、参政党に爆発的な力を与えたが、同時に、極めて深刻な矛盾を内包している。その矛盾は、まさに今回の参議院議員選挙(2025年7月)を経て、当選するであろう新人議員たちによって、一気に表面化する可能性が高い。
今回の比例区名簿を見ると、医師、元官僚、経営者、弁護士といった、いわゆる「学歴や社会活動歴がしっかりしたエリート層」が名を連ねている。彼らが国会議員という「公人」となり、永田町の論理の中で活動を始めた時、党の創設者であり、精神的支柱である神谷宗幣代表との間に、深刻な「軋轢」が生じることは、ほぼ避けられないだろう。
その軋轢には、いくつかの火種が予測される。
- 火種1:政策の「純粋性」と「現実性」の対立
党の基本方針である「反緊縮財政」や「食の安全基準の見直し」は、支持者にとっては絶対の教義だ。しかし、元官僚や経済の専門家である新人議員は、国会の委員会などで、その政策の現実性や、他国との協調について、厳しい追及を受けることになる。その時、彼らが「より現実的な路線」を模索し始めれば、それは神谷代表や、純粋性を求める党員から「裏切り」「変節」と見なされかねない。 - 火種2:メディア戦略の対立
神谷代表と党の基本戦略は、既存メディアを「敵」とみなし、YouTubeなどの独自メディアで支持者と直接繋がる「アンダーグラウンド型」だ。しかし、国会議員は、法案を動かし、世論を喚起するために、既存メディアとの関係構築が不可欠となる。新人議員がテレビの討論番組に出演したり、大手新聞の取材に応じたりするようになれば、それを「敵への懐柔」と捉える強硬な支持層との間に、深刻な溝が生まれる。 - 火種3:党の「主導権」をめぐる対立
これまで、参政党は神谷代表のカリスマと、彼を中心とするボードメンバーによって、トップダウンで運営されてきた。しかし、国会議員団が形成されれば、彼らは「国民の代表」という、神谷氏とは別の正統性を手に入れる。そして、政党交付金という公的な資金も、彼らを中心に配分されることになる。「党務を執行する事務局(神谷代表)」と「立法活動を行う議員団」との間に、党の路線や資金をめぐる主導権争いが起きるのは、多くの新興政党が経験してきた道である。
この軋轢は、参政党の「成功」が生み出す、必然的なジレンマだ。 党が成長し、より多様で有能な人材を惹きつければ惹きつけるほど、神谷代表一人のカリスマで党をまとめ上げることは困難になる。
参政党が、一過性のブームで終わらず、持続可能な政治勢力となるか否か。それは、この「カリスマ創業者と、エリート新人議員団との関係」という、党内に埋め込まれた時限爆弾を、いかにして平和的に解除できるかにかかっている。そのプロセスは、党の真の成熟度を測る、最初の、そして最大の試練となるだろう。
終章:もし参政党が政権を取ったら──日本の未来、世界の分断
これまでの章で、私たちは参政党という現象の「なぜ」と「いかにして」を、世界の潮流と日本の土壌、そしてその巧みな戦略と思想の両面から解き明かしてきた。しかし、この分析を完成させるためには、最後に、一つの思考実験を行わなければならない。
それは、「もし、参政党が政権を担う日が来たら、日本はどう変わるのか」という、未来への問いである。
もちろん、これは現時点においては、可能性の低いシナリオかもしれない。しかし、彼らが掲げる理念と政策をその論理的帰結まで突き詰めてみることこそ、この新しい国民運動が内包する希望と、そして危うさの本質を、最も鮮明に映し出す作業となるだろう。
第一節:「最初の100日間」──日本を襲う衝撃
「神谷内閣」が発足したその日から、日本の政治風景は一変する。まず、財務省、外務省、厚生労働省、文部科学省といった主要官庁には、党の理念に忠実な人物か、あるいは既存の官僚機構を「破壊」することに躊躇のない民間人が、大臣や副大臣、政務官として送り込まれるだろう。
そして、矢継ぎ早に「最初の仕事」が断行される。総理による所信表明演説では、「戦後レジームからの脱却」と「真の日本の主権回復」が、高らかに宣言される。具体的な行動として、WHO(世界保健機関)のパンデミック条約からの脱退交渉開始を指示。中国共産党に対しては「人権侵害に対する、最も強い言葉での非難」声明を発表。文部科学省には、新たな歴史教科書検定基準の策定を命じる。
この「電撃作戦」は、国内の既存メディアや官僚、学術界から猛烈な批判を浴びるだろう。しかし、内閣と党は、SNSと独自の動画チャンネルを通じて「我々は、国民との約束を果たしているだけだ。抵抗しているのは、国を売り渡してきた古い支配層だ」と支持者に直接語りかけ、むしろその対立を、自らの正当性を強化する燃料へと変えていく。永田町と霞が関は、かつてない混乱と熱狂に包まれる。
第二節:日本の作り変え──「国守り」の名の下の内政
長期的な政権運営において、日本社会は、その根幹から作り変えられていくだろう。
- 経済:「財政規律」との決別
「財務省の支配」から脱却した政府は、MMT(現代貨幣理論)を事実上の国家方針とし、大規模な国債発行による財政出動を断行する。国内の食料自給率向上を至上命題とし、農家への手厚い補助金や、輸入食品への高い関税といった、強力な保護主義政策が打ち出される。経済は一時的に活性化するかもしれないが、やがて深刻なインフレと、国債の信認低下という巨大なリスクに直面する。 - 社会・文化:「伝統」の公式化
教育現場では、「日本神話」や「伝統的な家族観」を教えることが義務化され、教科書は政府の望む歴史観を反映したものへと一変する。選択的夫婦別姓や同性婚の法制化といった動きは完全に停止し、「ジェンダーフリー」という言葉は公の場から姿を消す。食品添加物や農薬、医薬品に関する安全基準は、国際的な基準から離れ、国独自の「食養生」に近い思想に基づいて再編される。社会の「文化戦争」は日常的な風景となり、賛同しない国民は「反日的」というレッテルを貼られ、社会の分断は決定的なものとなる。
第三節:「孤高の日本」──外交・安全保障の激変
外交方針の転換は、世界を驚かせることになる。
- 中国との関係:対中国政策は、「対話」から「対決」へと完全に舵が切られる。経済的なデカップリング(切り離し)が推進され、国内の中国人留学生や労働者に対する監視も強化される。台湾有事の際には、アメリカの意向を超えて、独自の防衛行動をとる可能性も示唆し、東アジアはかつてない緊張状態に陥る。
- 日米同盟の変質:同盟関係そのものは維持しつつも、「アメリカの言いなりにはならない」という「自主防衛」の旗印の下、在日米軍基地の縮小や、より対等な地位協定への改定を強く要求する。これにより、日米関係は安定した同盟から、常に緊張をはらんだ、取引的な関係へと変質していく。
- 国際社会からの孤立:WHOだけでなく、国連人権理事会など、国家主権を制約すると見なした国際機関や条約からは、次々と距離を置くようになる。日本は、国際協調の優等生から、「自国の利益」を最優先する、誇り高くも、孤立した国家「孤高の日本」へと変貌を遂げる。
総括:参政党が私たちに突きつけた「鏡」
この未来予想図は、ある人々にとっては理想郷に、またある人々にとっては悪夢に映るだろう。 重要なのは、この未来が、荒唐無稽な空想ではないということだ。それは、第1章で分析した、現代日本社会の「土壌」──すなわち、経済的な停滞、政治への不信、そして「何かを奪われている」という漠然とした喪失感──から生まれた、論理的な帰結の一つなのである。
参政党は、これらの国民の不安や渇望を、誰よりも巧みに掬い上げ、一つの鮮明な「処方箋」として提示した。彼らが「鏡」だとすれば、そこに映し出されているのは、グローバル化の波の中で、自らが進むべき道を見失い、分断され、揺れ動いている、私たち自身の姿に他ならない。
参政党という現象を、単に支持する、あるいは批判するだけで、思考を止めてはならない。 この鏡に映った自画像と、私たちはどう向き合うのか。この国を、どのような形で、次の世代に手渡していくのか。
その重い問いに、答える責任は、今、私たち一人ひとりにある。
編集部より:この記事は島田裕巳氏のnote 2025年7月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は島田裕巳氏のnoteをご覧ください。