
集英社系の教養サイトimidasに、作家の上田岳弘さんとの対談が載りました。どちらも同じ1979年生で、ともに体験した「昭和のおわりから令和まで」をふり返る歴史トークにもなっています。

上田 その明るい未来を見ていた90年代の延長上で、2000年代はインターネットの発展がトピックになったと思うんですよ。すべてとはいかないかもしれないけど、多くの問題をネットが解決していくという未来を素朴に信じる空気感が2000年代の半ばまではあった。
(中 略)
いまはそれがどうなのか。Aと言う人がいて、反Aを言う人がいると、議論するのではなくて、お互い罵りあって2つが相殺されて虚無感だけが残るのが現状なのではないか。
僕はデビューが2013年なんですが、その頃から、そういう虚無感みたいなものが来ることを予想しながら、デビュー作の「太陽」や次の「惑星」(『太陽・惑星』)、『私の恋人』(いずれも新潮文庫)という作品あたりまで書き継いでいった感じがします。與那覇 「太陽」や「惑星」には、歴史のすべてを見通せる「超人」のような人物が出てくる。でも、彼らの人生はちっとも楽しそうに見えず、すべてを「わかってる」がゆえの息苦しさしか残らない。
僕は2013年にはまだ大学で歴史学者をしていましたが、その頃の自分が鬱になってゆく感じとシンクロして今回、切実に読めました。当時はアラブの春とか、日本だと脱原発デモがあったりして、冷戦が終わるときのハッピーな感じが一瞬甦ったけど、まさに歴史の宿命ですぐに潰れてゆく時期でしたから。
1頁
段落を改変し、強調を付与
そうなんですよ。いまインターネットには2種類の人がいて、①もっと素晴らしい場所になると思ってたのに「これなのか」と感じてる世代と、②最初から「こんなもんだろ?」な世代とです。
虚無感以前に本人が虚無みたいな学者の批判を、ぼくはよく書きますけど、彼らって要は年齢的には①のくせに、②の方が承認を得やすいからって “闇堕ち” した人たちなんですねぇ(苦笑)。実例はいっぱい落ちてます。


歴史なぞを学ぶと、①どうせ世の中こうしかならないんじゃね? な諦め、ニヒリズムが生まれてしまう。で、せっかく文学から得た修辞の力も②他人を貶して愉しむことに使おうぜ、なシニシズムに走る人が出てくる。
こうして堕落したSNSの人文学者が、だいぶ前から “人糞学者” だと揶揄されてるわけですな。つまりそんなものは要らないし、これからはもっともっとバカにされてゆくのだと思います。

では、そんな時代に “ほんとうの” 人文的な教養は、なにをすべきか?
対談は上田さんが今年出した、コロナの体験を踏まえた短編集『関係のないこと』がきっかけだったので、ぼくはこんなことを喋っています。
與那覇 ミシュランなり食べログなりの「評価が高いお店」で食べることには、特別感がある。でも、本来ならもともと「私にとって特別」なお店をみんなが持っていた。受験勉強で通ったとか、初めてのデートで使ったとか、店主と顔なじみになれたとか。
一回性や個別性が消えると、そうした本人なりの価値がなくなり、みんながレビュー評価に釣られて動くことになってしまう。
(中 略)
上田さんも、初期には人類史の全体を抽象化して見渡す中編を書かれましたが、近年は『旅のない』(講談社文庫)や『関係のないこと』など、ミクロな対人関係の「思い出」を回想する文体の短編集を出されてますね。そうした変化に、一回性や個別性が消えてゆく社会への危機感を感じました。
『関係のないこと』のうち2篇は、コロナ禍を背景としたバーでの対話劇。登場人物の語る「自分の来歴」が、ほんとうか嘘かは、最後まで読者にはわからない(特に片方は、嘘の可能性が強く示唆されて終わる)。
しかし、仮に虚偽が混じっていたからといって、そこで交わされた人生をめぐる会話には、意味がなかったことになるのか? 自称ファクトチェッカーが飛んできて “FALSE!”とハンコを捺しまわる世の中が理想なのか?

そんなわけない。……という含意が、センモンカの語る「ファクト以外いらない!」みたいな空気に支配されたコロナ禍の体験と響きあうことで、じんと来る作品になっています(あくまで、ぼくの読み方ですが)。
というか、あのときファクトとかエビデンスとか言われたことの方が、嘘といって悪ければ “希望的観測”、つまりは物語に過ぎなかったこと、もうバレてますしね。とくにワクチンに関して。
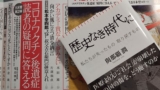

文字数の関係で略されてますが、この『関係のないこと』を読んだ後だと、2019年に芥川賞を受けた上田さんの代表作『ニムロッド』も、違った解釈でより印象的に読める、という話もしました。
ビットコインを掘ったビミョーな儲けを会社の足しにする、”ぱっとしない” 仕事の男性主人公に対し、恋人の女性は日々に海外で巨額の商談をまとめる “デキる” 人材。少なくとも、そう聞いた上で、つきあっている。

「いいよ。どうせ俺の一日に稼ぐ額なんて、紀子の三時間にも満たない」こういう台詞を気安く言える程度には気心が知れているつもりだけど、こんな風に強引に呼び出されるのは初めてだった。あまり彼女らしくない行動で、恋人としてというよりも純粋に興味が湧く。
(中 略)
克服可能なトラウマを抱えた、けれど本質的な強度を備えた女性。田久保紀子。不器用で貧乏であるために、世の中に振り回されて日常生活の些細な達成に喜びを見出すしかない人々とは一線を引いている。
講談社文庫版、70-1・95頁
(地の文で)田久保紀子の語る履歴は、そのまま事実としてとるのが、小説の素直な読み方です。が、そうでない読み方も、読者にはできる。
むしろ “こんな優秀なキャリアを私は生きてる” といった、どこか能力主義的な彼女の語りこそ、本人が人生を支えるために作ってきた “嘘” だったのかもしれない――と、半信半疑で読んでみた方が、「らしくない行動」を取り出した紀子のその後の運命に、いっそう心動かされるものがある。

そんな読書の体験から、「ファクトでなければ無価値!」とされるのは “法廷で相手と争う” ような非常事態での倫理であって、それが現実のすべてを覆い尽くすよう煽る風潮こそ、どこかおかしいと考えることもできます。
……実際、ふだん「ジッショー!!」とか言ってきた歴史学者ほど、いざ本当に実証が必要な時には使いものにならなかったでしょ?(失笑) そうなんです。人文学で磨くべきは、ほんとうは “嘘” を扱うセンスの方で。

マクロな「歴史」と、個別の「思い出」の双方をモチーフに創作している上田さんと、ポストコロナの時代の新たなモラルを探す対談にもなっています! ぜひ、多くの方の目に触れますように。
参考記事:



編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年10月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。













