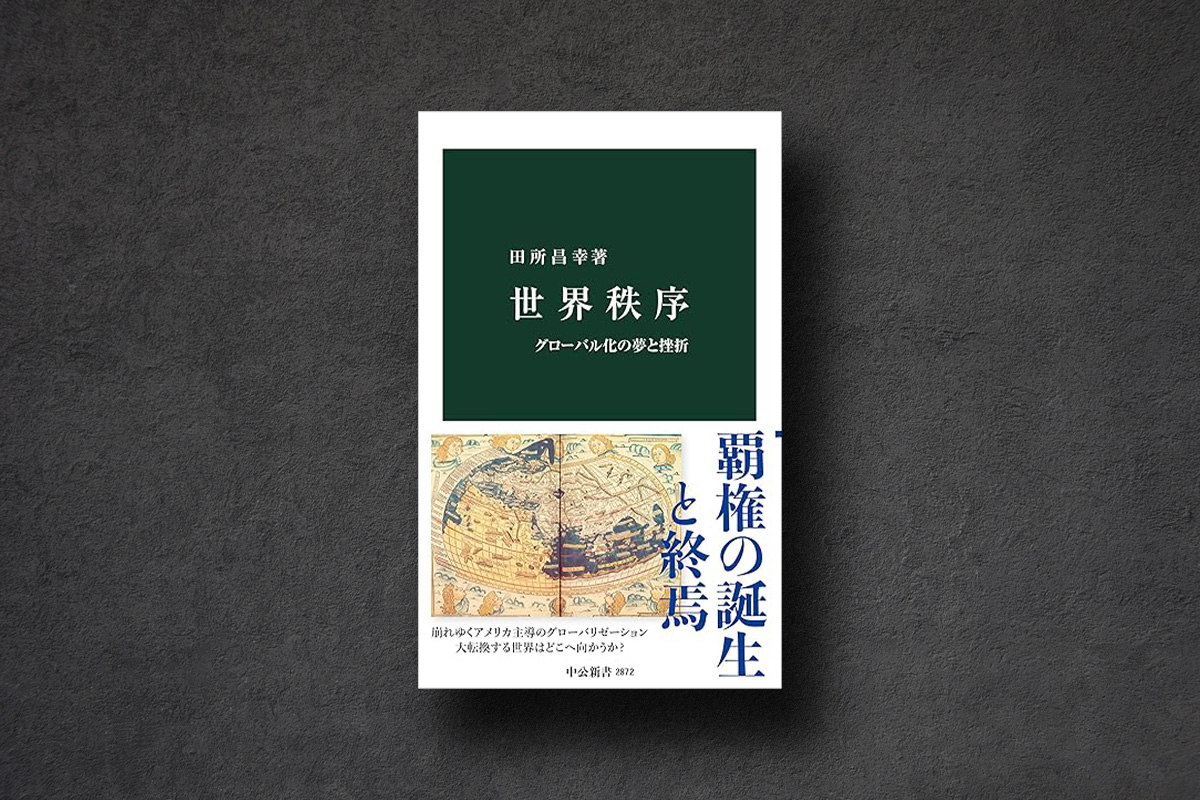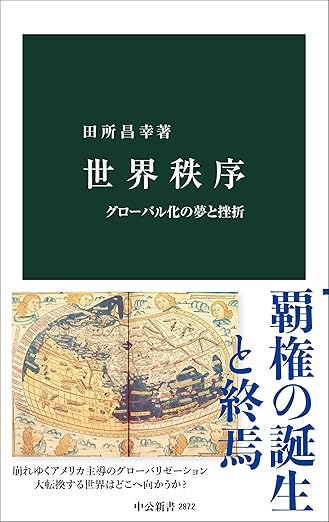1. リベラル国際秩序の動揺
冷戦終結から30年が経過し、日本人が慣れ親しんだ国際秩序は流動期を迎えている。それは、戦後の安全と繁栄の基盤となってきた自由主義的価値観(人権・民主主義・民族自決)と自由貿易を基調とした市場経済を規範とし、軍事力や威圧ではなく国際法により規律することを是とする「自由主義的国際秩序」/「リベラル国際秩序」の動揺を意味する。
筆者も指摘するように、その秩序の実践は、アメリカの国際社会における相対的に優位な国力と、そのような国際秩序を維持・管理しようとする意思を前提としていた。あえて単純化すれば、リベラル国際秩序とは、いわばアメリカ帝国的/覇権的な秩序ともいえる。
戦後日本の繁栄はアメリカの秩序経営の能力と意思に依存してきたという事実を認めるところから、世界秩序と日本(の国益)という関係の問題は始まる。
本書のテーマは、リベラル国際秩序の動揺を前に、世界史をグローバル化という観点から巨視的に捉え、世界の「秩序」を構成する条件を考察することでポスト・リベラル国際秩序(ポスト・グローバル化時代)への洞察を引き出すことに狙いが置かれている。
本書は、社会科学的なモデルを適用した分析ではなく、物語的に秩序史を追いかける考察スタイルとなっており、読むものをして自然と歴史の流れに対する洞察を磨くかせる。このことは、歴史(学)が社会科学よりもずっと「歴史」のある学問分野であり、古今東西の為政者から実際の統治や外交に応用された実践知であることと無縁ではないだろう。一寸先が読めない混迷の時代だからこそ、息の長い学問から知恵を引き出す意義があるのかもしれない。
2. グローバル帝国の消長
筆者は、世界的秩序を構成する主体として、地理的環境に加えて、権力・制度・文化という要素を指摘する。本書で紹介されるモンゴル帝国や大英帝国、そしてアメリカ(アメリカ主導によるグローバル化)について、各「帝国」が力点を置いた統治要素は異なれど、概ねいずれの要素のバランスが確保できた場合にグローバルな秩序が出現するという理論である。
モンゴル帝国は騎馬戦力という軍事力を背景に版図を拡大し、各地域に対する政治的・文化的「無関心」をもって(モンゴル中心への逆影響/輸入)帝国を構成した。しかし、文化の側面が希薄であった帝国にはやがてイスラムや中国による文化的浸透から遠心力が働き、疫病も災いして帝国システムは瓦解する。
モンゴル人は、巨大な域内をまとめる宗教的装置を持たなかったし、漢字に匹敵するような統合のための文化的装置ももたなかった。そのためモンゴル帝国は多様な人々の内面的支持を確保する文化的・規範的な力は弱く、むしろ逆に被支配者から影響を受けたといえるだろう。
(59頁)
大英帝国は、購買力の相対的に高いイギリス市場を植民地や第三国に開放し、海運や金融、保険といった自由貿易を支えるサービスを通じて富を増大させた。英国は、排他的ではなく他の国家・地域との相互的な経済成長を担保する「開かれた帝国」運営を基調としたという意味で、グローバル化史における新機軸をもたらしたともいえる。
もっとも、大英帝国による覇権の前提となる国際システムは、16世紀に始まった宗教戦争に終止符をもたらすために安定的な領域統治を実現されるために欧州で導入された主権国家体制という、形式上は平等な「主権」概念が一つ一つの国家に付与された国際システムであった。
大英帝国の相互主義的な覇権システムは、主権国家体制に適合的であり、むしろ強化する力学を内蔵していたからこそ、英国は、大した資源があるわけでもないにもかかわらず「日の沈まぬ国」として世界政治に君臨したのかもしれない。
アメリカも世界秩序モデルの観点から見れば、「開かれた帝国」を創出した英国に似ているかもしれない。特に第二次世界大戦後のリベラルな秩序経営においては、アメリカという市場を敗戦国のドイツや日本に開放し、冷戦戦略の文脈から東南アジアや韓国、やがては中国にも開放し、彼らの経済成長を支え、モノやサービスの自由な融通と文化交流を通じてリベラルな価値観(民族自決・民主主義・人権)の優位性を浸透させていった。
ソ連や中国といった共産圏に対して自由主義陣営の国益と影響力を保全するため、アジアや欧州、中東という世界の枢要にアメリカ軍を前方展開し、長い目線でみれば権力の空白を許さなかった。さらに、筆者の指摘する秩序要件である(国際)制度について、アメリカはGATT(やがてWTO)や世界銀行、IMFという国際機関を通じて自由市場を拡大・強化した。
アメリカによる、自由貿易と民主的価値観で構成されるリベラルな国際秩序の創出は、世界のグローバル化の再来を意味したが、それは、グローバル化がアメリカの国益と合致するという認識が国内で一定以上のコンセンサスを得ることを条件としていた。
そのコンセンサスはいかなる条件により成立するのか、自由民主主義の普及が世界史が到達する最終局面との命題に立ったフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』が大きな影響力を獲得したアメリカにおいて、アメリカ主導のグローバルな秩序は、冷戦後の一極集中時代にはとりわけ永遠のものと受け止められたのかもしれない。
しかし、同時代にアメリカは、アフリカや中東における国際紛争への軍事介入や国際金融危機を通じて、国力の疲弊や世界的影響力への陰りを自覚し始めると、その原因が、自らが創出・維持してきたリベラルな国際秩序にあるのではないかと批判的な検討を始めたのである。
アメリカの内省は、グローバル史の観点からすれば、中国の台頭以上に世界史的なインパクトかもしれない。現代中国の台頭は、リベラル国際秩序を前提としており、その樹液を存分に吸収することで国際・地域において覇権的なふるまいを示しているからだ。
3. リベラル国際秩序の動揺と日本
現在の国際秩序をめぐる問題の一つの焦点は、第二次大戦後から冷戦後にかけて、アメリカが相対的に優位な国力を前に創出・維持してきたリベラルな国際秩序が、その相対的な国力や威信の低下に伴い、秩序管理へ否定的な姿勢を示していることである。
もう一つは、中国の経済・軍事・外交のあらゆる側面での国際的な影響力の高まりやBRICSやグローバル・サウスのようにリベラル秩序へ必ずしも同調しない新興国が台頭してきている、主権国家体制の実質的な意味での多極化にある。
筆者は、米中関係が今日の国際政治の基本的な構造を決定づけることを前提に、米中共同統治論や新冷戦という仮説を提示しつつ、どちらかといえば冷戦期に近い形で米中関係ひいては世界秩序は変化していくとの考えを示している。その際に、米ソ冷戦期と大きく異なる側面として、新興国の台頭を受け、「新冷戦」の新しい側面として「諸国家の角逐」を上げている。
米中両陣営が、冷戦期の米ソ陣営ほどには安定した集団にならないとすると、世界は主要大国が機会主義的に合従連衡を繰り返す流動的な姿になりそうだ。ポスト・グローバル化の世界は、グローバルな関係を安定させる国際的な制度や規範も弱体化し、同盟やパートナーの目まぐるしい組み換えと大国間の露骨な実利的取引、時には儀礼や慣行を無視したとげとげしい言葉の応酬や、経済的圧力、そして軍事的な威嚇が繰り返される荒っぽい世界になりそうだ。
(130‐131頁)
事実、そのような世界は、日本が位置し、その経済的・政治的命運を左右するインド太平洋地域にすでに現出している。日本政府も公式に表明している中国という最大の戦略的挑戦は、日本一国への挑戦ではなく、戦後日本の繁栄と安定を保全してきたリベラルな国際秩序への挑戦であると認識することが、歴史的な視座であり、日本の国家戦略の形成に必要な視座でもある。
本書の中で日本は「大国でも小国でもない、中途半端な国」と形容されているが、物語的には適当な表現であろう。歴史的な著述であるせいか、本書は具体的な外交術やステートクラフトまで立ち入らず、読者への問題提起で筆を置いている。それでも筆者は、アメリカのリベラル秩序の運営の見通しが不透明になる中、世界秩序が動揺期にあるからこそ、日本は「対外政策の原則」をかみしめることの重要性を説く。
基本に立ち返れば、対外政策の原則は常に平凡かつ単純だ。友好国を増やして共存共栄の空間を発展させるとともに、心の許せない国とも無用の対立を避けることだ。限定的な力しかない日本にとっては、国際政治があまりにも競争的になるのは不都合だから、これはきれいごとではない生き残りのための戦略だ。しかし、どんな巧みな外交も、最終的には自分の身は自分で守るという覚悟に支えられなければ、役に立たない。
(164頁)
リベラル秩序の動揺と日本の国力推移の中長期的な見通しを前に、改めて、世界における日本の立ち位置や望ましい世界秩序のイメージについて考えるべき歴史的局面にある。アメリカ主導のリベラル秩序に戦後の繁栄と安定の多くを負ってきた日本としては、秩序の動揺は将来への不安を増幅させるが、日本の危機を必ずしも運命づけるものではない。
思えば近代日本にとっての「危機の時代」、幕末や敗戦後という時代は、日本は物質的なひ弱な国であるか、国際的地位は高くはないあるいは最悪の局面ですらあった。
今日の世界で、日本は人口を1億人以上有し、世界第4の経済的パワーであり、地政学的緊張と経済成長の契機が集中しているインド太平洋地域において、安定した政治・軍事的パワーとして存立している。
つまり、日本は、望むか望まないかは別として、客観的条件から世界秩序のあり方に相応のインパクトを及ぼす国際プレイヤーである。米中競争の中でそのポテンシャルを食いつぶすか、望ましい秩序に向けて強かに外交を展開するか、リベラル秩序は確かに動揺しているが、破綻している訳ではない。
中国の強国化や新興国の台頭から複雑性は増しているが、筆者のいう「対外政策の原則」に照らしても、日本が少数派に堕ちたとまでは評価しがたい。その中で日本として、どのように国益と世界秩序、外交政策の関係を整理し、粘り強く振舞うかが問われている。
多少誇張すれば、日本の国際的主体性に世界史的な余地が与えられてる時代区分であり、考えようによっては面白い局面である。
編集部より:この記事はYukiguni氏のブログ「On Statecraft」2025年12月3日のエントリーより転載させていただきました。