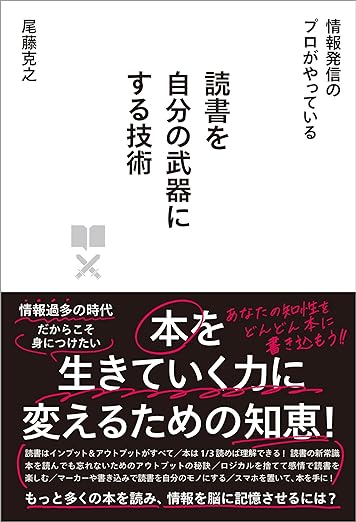ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子で、ウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手が失格となった。理由は、ロシアの侵攻で命を落とした24人のアスリートやコーチの顔写真を描いたヘルメットを着用したことだ。
IOCは五輪憲章第50条に基づき、競技会場での政治的表現を禁じている。規則に従えば、失格という判断は理解できる。しかし、この処分は本当に正しかったのだろうか。
ヘルメットに描かれていたのは、戦争で夢を絶たれた仲間たちの顔だ。2016年ユースオリンピックでともに戦ったフィギュアスケーターのドミトロ・シャルパル、ボクサーのマクシム・ハリニチェフ。オリンピアンもいれば、子どもも、ヘラスケビッチ選手の友人もいた。
ロシアの侵攻開始以降、660人ものウクライナのアスリートやコーチが命を落としている。ヘラスケビッチ選手はその一端を胸に競技に臨もうとした。これを「政治的宣伝」と呼ぶことに、どれほどの人が納得できるだろうか。
IOCの立場にも一定の理がある。追悼だからといって例外を認めれば、何が許され何が許されないかの線引きは際限なく難しくなる。制度の一貫性を保つことは、組織運営において重要な原則だ。
しかし、少なくとも「政治的主張」と「戦争犠牲者への追悼」の間には、明確な質的差異がある。特定の政策や体制を支持・批判するメッセージと、命を奪われた仲間を悼む行為を同列に扱うことが、本当に「一貫性」と呼べるのだろうか。
だが、そもそも五輪が「非政治的」であった時代など存在するのだろうか。
1936年のベルリン大会はナチスの国威発揚に利用された。1980年のモスクワ大会と1984年のロサンゼルス大会では東西陣営が互いにボイコットし合った。開催地の選定プロセス自体が政治と利権にまみれてきたことは周知の事実だ。
そうした歴史の中で、犠牲者への追悼だけを「政治的行為」として罰するのは、あまりにバランスを欠いている。
ヘラスケビッチ選手自身も、イスラエルのスケルトン選手が1972年ミュンヘン事件の犠牲者11人の名を刻んだキッパを開会式で着用したことや、米国のフィギュアスケート選手が亡き両親の写真を会場に持ち込んだことを挙げ、「自分のケースとの違いを説明できる人はいない」と訴えた。
もちろん、開会式と競技中では適用される規則の文脈が異なるという反論はありうる。だが、問題の本質は場面の違いではなく、追悼という行為そのものをIOCがどう扱うかにある。
さらに皮肉なのは、この失格処分がIOCの意図とは正反対の結果をもたらしたことだ。ヘラスケビッチ選手の行為は世界中に報じられ、24人の犠牲者の存在はより多くの人の目に触れることになった。
ゼレンスキー大統領は「勇気を持つことは、メダル獲得よりも価値がある」と称え、ウクライナで2番目に高い民間勲章である「自由勲章」の授与を発表した。IOCが守ろうとした「非政治性」は、処分によってかえって巨大な政治的議論を生んでしまった。
1968年のメキシコ五輪で、米国の黒人選手トミー・スミスとジョン・カーロスは表彰台で黒い手袋の拳を掲げ、処分を受けた。
当時は非難されたが、今では人権運動の象徴として称えられている。ヘラスケビッチ選手が「メダルよりもはるかに大切なものがある。この人たちの命と記憶に比べれば、メダルには何の価値もない」と語った言葉は、同じ重みを持つのではないか。
ルールの一貫性と、そのルールが現実の前で妥当かどうかは別の問題である。戦争で奪われたアスリートたちの命という動かしがたい事実を前に、形式的な規則の適用だけで正義を語ることはできない。
五輪が本当に平和の祭典であろうとするなら、戦争の犠牲者から目を背けることではなく、その現実と向き合うことこそが求められているはずだ。
尾藤克之(コラムニスト、著述家、作家)
■
22冊目の本を出版しました。
「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)