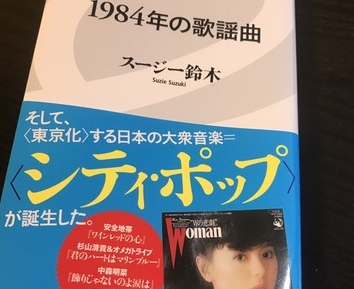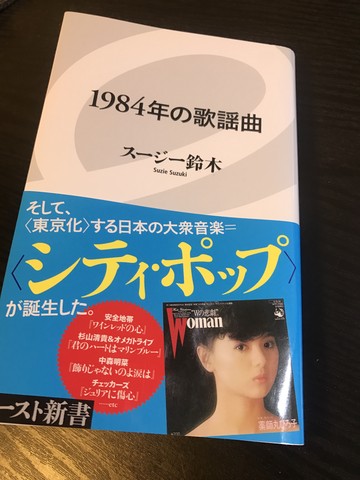
日常的に音楽を聴いている。まさに”NO,MUSIC,NO LIFE.”だ。そうなのだけど、やたらと音楽を聴いているなと感じる年はある。いや、いつもかかっているものだし、1日は24時間だからそれ以上聴けるはずがないのだけど。でも、この感覚、わかってくれるかな?
私にとって、そんな年の一つが、1984年だった。とにかく、この年は音楽を聴いていたように思う。当時、私はシングルデッキのラジカセを持っていて。ダビングもできないし、レコードの音をおとすことすらできなかったが、いつもラジオにかぶりついて音楽を聴いていたように思う。
当時、私は10歳、小学校4年生だった。もちろん、音楽に興味を持ち、聴き始める時期であり。やや生意気になる盛りなのだが。とはいえ、この年は音楽が面白かったように思う。邦楽も洋楽も。
「やっぱり、あの年の音楽ってよかったよね。面白かったよね」と、スージー鈴木の『1984年の歌謡曲』を読んで確信した。単に私の主観じゃなかったのだ、と。
バブル前夜である1984年は、日本の歌謡曲においても大きな転換点だった。「歌謡曲」と「ニューミュージック(と呼ばれていた音楽)」は「対立」するのではなく、この年に「融合」する。同時に「シティ・ポップ」と呼ばれる「東京人による、東京を舞台とした、東京人のための音楽」が登場した年でもあった。キャッチコピー的な歌詞と、複雑なアレンジ、コードが街に流れた時代でもあった。
そうか、そうだったのか。札幌市のはずれで、ラジオの向こうから聴こえてきた音楽たちの、独特の「内地」のにおいというか。都会的で、大人っぽい雰囲気は「シティ・ポップ」だったのか。
ただでさえ、良い思い出に満ちた年を振り返り、その種明かしがされるのだから、たまらない本である。友人との読書会にもオススメだ。酒の肴にも、お茶のデザートにもピッタリな本である。
改めて、この年は稀有な年であった。大沢誉志幸『そして僕は途方に暮れる』、吉川晃司『モニカ』、郷ひろみ『2億4千万の瞳~エキゾチック・ジャパン』、小林麻美『雨音はショパンの調べ』、薬師丸ひろ子『Woman ”Wの悲劇”より』、安全地帯『ワインレッドの心』『恋の予感』、中森明菜『飾りじゃないのよ涙は』、SALLY『バージンブルー』、チェッカーズ『ジュリアに傷心』・・・。全部、1984年の曲なのだ。松田聖子も売れていた。サザンも最初の活動休止に入る前だった。他にも書ききれないくらいの沢山の名曲が・・・。
ポスト松本隆競争のような時代であり、売野雅彦が作詞を手掛けた曲はこの年のシングルだけで400万枚以上となり。松田聖子に中森明菜が迫っていった年であり。大沢誉志幸も提供曲が売れまくり。井上陽水も第二次ブームだった。吉川晃司が鳴り物入りでデビューした年でもあり。細野晴臣も頑張っていた。
こういう奇跡の年って、たまにあるんだな。
と言いつつ、音楽のパッケージコンテンツの売上はここ数年と同じくらいだったんだな。これって、音楽の楽しみ方が変わり続けているっていうことだろうか。
もう1984年には戻れないけれど、青春(の前か)の種明かしをしてくれる素敵な本。読み終わったあと、いてもたってもいられず、大沢誉志幸を聴いている。ありがとう。
編集部より:この記事は常見陽平氏のブログ「陽平ドットコム~試みの水平線~」2017年3月12日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。